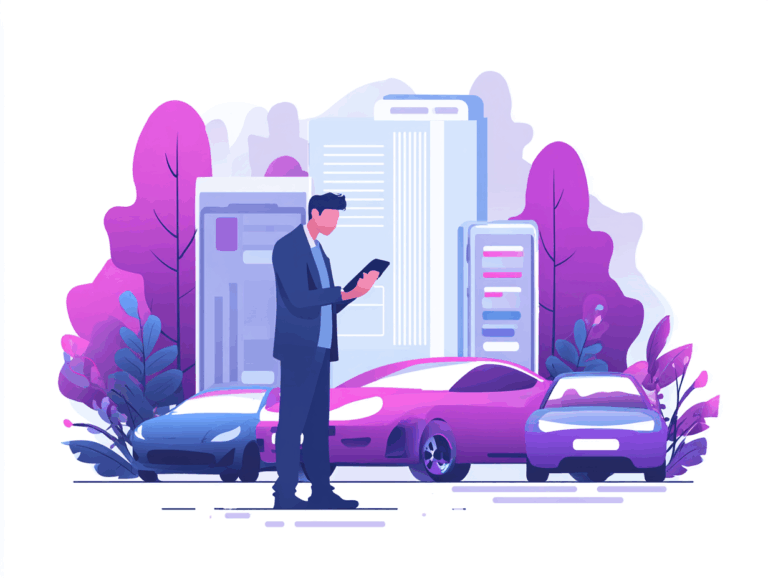伊藤:H.RさんのLPのフィードバックにいきましょうか。どうですか、作ってみて。
H.R:この間、送っていただいた画像、ブランドサイトのこういう順番で作ったらいいよとか、ベネフィットに着目しましょうとかっていうところをちょっと意識しながら自分では作ったつもりです。
伊藤:随分良くなった気がしますね。
H.R:本当ですか、よかったです。
伊藤:どの辺が一番苦労しましたか。
H.R:一番自分で時間かかったのは、ベネフィットが何だろうっていうのを考えるところが時間がかかりました。あとはこれの中でも実際にまだちょっとブレてるかもしれないんですけど、お客さんがトータルサービスを求めているお客さんなのか、空き家の賃貸管理のみを求めているお客さんなのかっていうのが、空き家の賃貸管理が一番利益になるからそこにやりたいんですけど、それだけで引っかかるってどうなんだろうと思って導入を一括にしたんですけど迷って。それは自分の中でベネフィットっていうところで、空き家の一括管理のベネフィットのプッシュが思いつかなかったので、空き家のベネフィット、ちょっとずつブレているような気もしなくはないんですけど。
H.R:あとは利用シーンっていうところが結局組み込めていなくて、この間のところで利用シーンっていうのがあるといいよっていう話だったんですけど、そこはちょっと流れ的にうまく組み込めなかったなっていう感じです。
伊藤:利用シーンイコール、別の言い方をすると、ケーススタディみたいな感じなので、5人兄弟のなんとかさんみたいなのとか、そういうケーススタディみたいな過去のやり取り、実績もあってもいいし、ちょっと架空のものでもいいんで、Aさんの場合みたいな形で出す場合も結構多いかなと思います。
伊藤:Y.Kさんは何かお気づきになったことはありますか。
Y.K:枠なしの写真が多いと思うんですが、イラストなんかもあったほうがいいなと。あと文字はまた工夫されると思うんですけど、文字の大きさは別にして書体は3種類ぐらいの色に揃えられたほうがいいかなって、そんなふうに思いました。
H.R:文字はたぶん1種類。
Y.K:あ、これ1種類。
H.R:1種類かもしれない。
Y.K:写真はどこで?
H.R:写真は伊藤さんに教えていただいたACフォトから全部拾ってきました。
伊藤:何が聞きたいですか。
H.R:これでいいのだろうかっていうところが聞きたくて、これがどうですかとか一個一個っていうよりは流れ的に、自分の中でいろんなサイトをとにかく真似して拾って作ったんですけど、デザインも本も作ったんですけど、無料相談の位置とかはここでいいのかなっていうのはあります。
H.R:で、もしこれでいいよってなった場合、今これがただの画像なので、それをここから、いかにして広告にしていくのかっていうところは、この講義中に運用もあるんですけど、教えていただけたらいいなっていうふうに思います。
伊藤:ベネフィットが一番H.Rさんが悩まれたということで、これをどういうふうに広告にしていくのかっていうのは、空き家とか不動産の整理をしてるのは、子どもに迷惑がかからないようにっていうことで、今の世代で処分したい、なんとかしたい。自分が生きてるうちになんとかしたいっていうのを、子どもに迷惑がかからないようにっていうことで。
H.R:確かにそういったおっしゃられてるお客さん結構いらっしゃいますね。だいたい60代から70代の人が、それを言ってるんじゃないですかね。息子さんが40代から50代働き盛りで、昔は親のうちに同居が当たり前だったんで、
Y.K:僕らの世代は。それが子どもに迷惑はかけられないっていう、そういう気持ちがベネフィットのひとつかなっていうことと。
H.R:若い方だと建物に愛着がないですよね。
Y.K:ないですね。壊して売れますかって聞いて、うちに来るんじゃなくて、解体業者さんに行けって言ってやったことがあるけど。実際行ったかどうか知らないですけど。
Y.K:50代、60代、70代の方たちは、子どもに迷惑をかけたくないっていう気持ちが強い。それがベネフィットかなと思いました。
H.R:非常に参考になります。ありがとうございます。
伊藤:それこそ、もう5年ぐらい前になると思うんですけど、Y.Kさんといろいろテストとか調査したことがあって、その結果わかったのが、やはり空き家を処分したいよっていう中で、3分の1は話がまとまらないっていうデータがあるんですね。つまりやっぱり家族の間で合意が取れず、売却できないよね、残したいよねっていう話になるんですね。
H.R:その層に関しては、リフォームした賃貸でっていうところが新しい提案になってくるかなと思います。
伊藤:ページの中身に関してはいくつかフィードバックすると。ここが多分前回のトップだったんですね、ファーストビューだったんです。
伊藤:ネガティブなものって、実はあんまり最初の方に持っていかない方がいいんですね。なので、真ん中か真ん中よりちょっと下ぐらいに配置したらいいんです。そうでないと、この情報、嫌だななんとなく、心理的に見たくないなっていう。
伊藤:なので、ページの上の方にはいいことを書くんですよ。夢をとか期待を持たせるように書いて、でもそのままだとやっぱりサービスとしては成立できない。一定の制約があるものが。下の方でリアリティを見せた方がより成約率が上がるんですね。
伊藤:なので、この真ん中より。
H.R:マイナスばっかですね、今。
伊藤:そうですね。なので、先ほどY.Kさんがおっしゃった安心感みたいなとか、簡単にできますよみたいなのを上の方に持っていって、リアリティの方はどんどんより下の方に持っていくっていう構成がいいかなと思います。
伊藤:で、ファーストビューがちょっとリアリティすぎるんで、もう少し家族が仲良くにこやかにしてるような感じのもの。ハウスメーカー的な要素のもので全然いい。ファーストビューはもうちょっと頑張りましょう。
H.R:はい、わかりました。ちょっと暗いですね。
H.R:なるほど、なるほど。そうですね、もう一気にリアルになっちゃって。
H.R:リアルな。もう考えたくないっていうふうに思っちゃう。
Y.K:はい。なるほど。
伊藤:で、もう一個が、ここ。ここがセカンドとかサードぐらいでいいです。私がやってますよと。思いを込めて、魂込めてやってるんですっていうのが意外と響くんですね。
H.R:じゃあもうちょっと前半に。
伊藤:前半に、3つ目ぐらいのところに社長が出てて、私がやってるからどうぞお任せくださいって。アパホテルみたいな感じ。
Y.K:アパホテル。この人なんか親切そうだなとか、一生懸命やってんだなっていうのがあって、そのあと下のほうのページ見てくれるような形になるかなと思います。
伊藤:ファクトがあって、一般的にはみんなサイトもそうなんですし、LPもそうなんですけど、きれいなデザインされたページ作りたがるんですよ。なぜか無駄なお金をかける。そうではないんですね。
伊藤:やはり、いろいろ調べた中で一番最初に思い出されることがやっぱり大事なんです。なのでちょっと色がきつめだったりとか、コピーがきつめだったりとかするほうがインパクトがあって思い出されやすいんですね。
伊藤:いろいろ調べたけど、このサービスを思い出してもらわないといけないわけです。
伊藤:全然名前出てこない。そこも重要だと思います。思い出してもらうにはあんまりきれいなページって必要ないんですよね。なのであえてこのちょっときつめのトーン。どっちかって言うと原色系に近いので、きれいなページのセオリーからはちょっとはみ出てるとは思うんですけど、この色合いぐらいのほうが僕は良いと思う。
伊藤:ちょっとトーンをアース系に気持ちを落としてもいいかなとは思いますけど、基本的にはこれぐらいのインパクトがあったほうが売れるページになるかなと思います。以上です。
H.R:ありがとうございます。
伊藤:1個質問に答えてなかったです。このボタンの部分。CTA、Call to Actionの部分なんですけど、ブログのほうで使っているボタンのウィジェットに設定できるので、それを設定するといいかなと思いますし、この絵自体をボタンとしてリンクを貼るみたいな設定をできるツールもあると思うので、それでやるといいかなと思います。
伊藤:ボタンを押すと一番下に問い合わせのフォームがあって、そこに入力して問い合わせにつなげるわけですね。ポイントはいくつかあって、このボタンは基本的にはファーストビューにも入れましょう。ここでもう問い合わせしたいっていう人もゼロではないので、この辺に1個配置しましょう。
伊藤:もう1つポイントがあって、全体で2個か3個ぐらいボタンはあったほうがいいかなと思うんですけど、これってこのコンテンツの色と同化しちゃってるんですね。なのでここだけあえて真っ白にするとかグレーにするとか、背景と違和感作ってここだけで一画面、スマホの一画面とかPCの一画面になるようにしましょう。
伊藤:明らかな違和感を作って立ち止まらせる必要があるわけですね。よく使うのはやはり背景が真っ白になって、このボタンだけが存在するみたいな形が多いです。
H.R:今ちょっと詰まっちゃってるんで、そうですね。もっと間隔を、余白をいっぱい取って真っ白にして、これだけが目立つ。っていうところをやると、結構問い合わせは増えるかなと思います。
伊藤:あとは何か質問ありますか。
H.R:デザインとかのほうは、今いただいたアドバイスで直していこうと思うので、思いました。いざこれを広告として使おうってなると、たくさん質問があります。
伊藤:分かりました。あとY.Kさんおっしゃったフォント一つだっていうと、見やすいんですけどちょっと飽きるので、2、3種類は使ったほうがいいかなと思います。
H.R:分かりました。
伊藤:では、次回までにどうしましょう?
H.R:そうですね。今日教えていただいたやつをちょっと使って、実際ので、今ちょっと知識だけって感じで、これを数字として活用して何かをするっていうことはまだ難しいなと思ったので、そういったところをもうちょっと詳しく教えていただけると嬉しいなと思います。
H.R:はい。LPについては、また直してくるので、直すので。
Y.K:素晴らしい。
伊藤:LPはどうしましょうか。当初は、ペライチでやりましょうかみたいなお話もあったと思うんですけど。
伊藤:はい、LP。LPはペライチでもできるし、ブログのツールで別ページを作って作ることもできます。ペライチのほうが構成は簡単なんですけど、あんまり細かい手入れはできないというデメリットもあったり、あとは月額で費用がかかる場合とかもあったりするんで、ただ最短でやりたいってことであればペライチでやるのもいいでしょうし、いろいろ細かい調整したいなってことであればブログツール側でもできるので。
伊藤:どっちが良さそうですか?
H.R:ペライチは何となく触ってみて、公開までやってみたことがあるので、ただその時は既にある型のものを中に入れ替えただけみたいな、文章を書いただけみたいな感じだったんですけど、せっかくこういう機会で一緒にやっていただけるっていうことなので、それよりかはブログのほうでいろんな設定とかっていうのを教えていただきながらやれると、今後急いでやるときはペライチで、時間コストかけられるときはブログのほうでっていうふうにやっていけるのかなと思っているのですが、どうでしょうか。
伊藤:そうですね。ちょうどY.Kさんの左官のほうのサイトも、ブログのアップロードはどなたか他の方にっていうスケジュールになってるんで、その方はもし参加できれば参加していただいてもいいですし、後々その録画しておいたものを見ながら作業を進めていくっていうことも良いかなと思います。
Y.K:ペライチはペライチ、僕もそんなに1,2回しか触ったことないんで、教えられるほどではないんで、ブログツールのほうでLP作る方法みたいなものをご用意しておきたいと思います。
H.R:ありがとうございます。
伊藤:本日は以上になりますが、何か言いたいことがあればお願いします。
H.R:ありがとうございました。