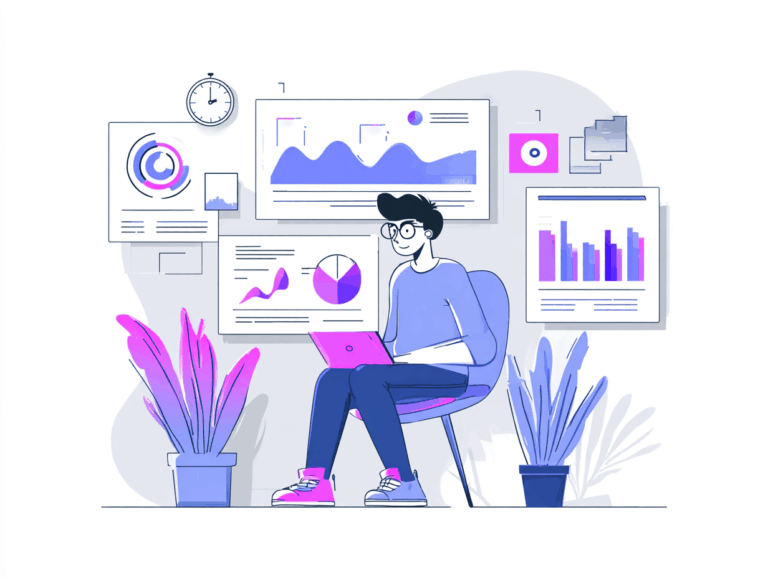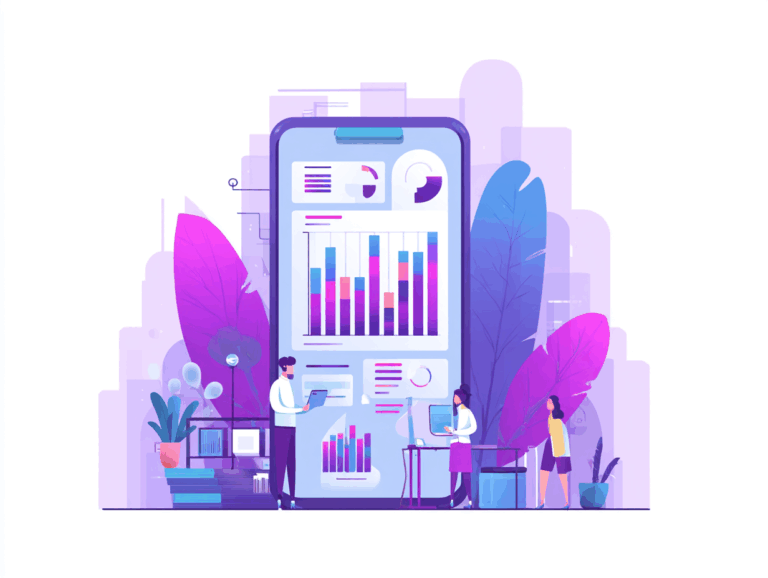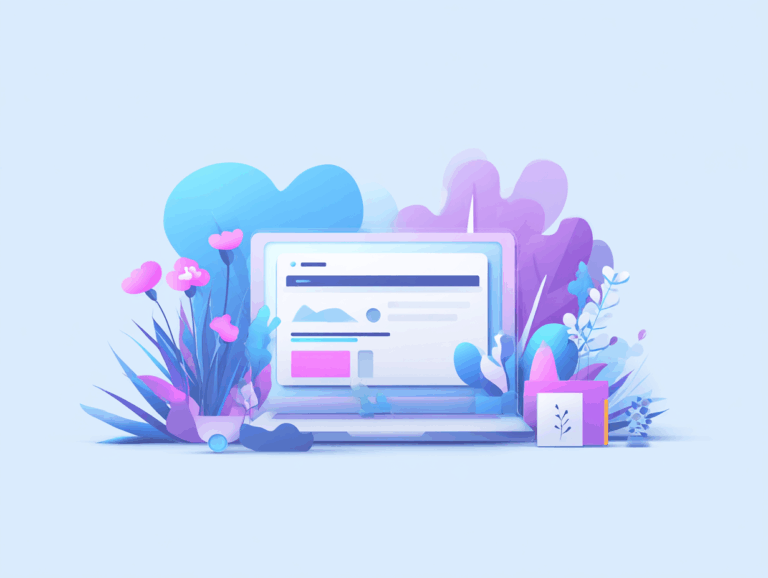事業を始めたばかりの経営者にとって、「何から手をつけるべきか」は永遠の課題だ。立派なホームページを作る前に、まずはランディングページから始めてみてはどうだろうか。単一のページで単一の商品を売る。シンプルだが、これこそがビジネスの核心を見極める最良の方法なのである。今回の講座では、実際の事業者たちとの対話を通じて、ランディングページの本質と実践的な活用法を探っていく。
こんな方に読んで欲しい
- スタートアップ・個人事業主
- 限られた予算と時間でマーケティングを始めたい
- どの商品・サービスが市場に受け入れられるかテストしたい
- 本格的なWebサイト構築前に効果的な集客方法を知りたい
- 既存事業者(中小企業経営者・店舗オーナー)
- 新しい商品やサービスを市場投入する前にテストマーケティングを行いたい
- デジタルマーケティングに取り組みたいが何から始めればよいかわからない
- フロントエンド商品とバックエンド商品の戦略的な活用を学びたい
- マーケティング担当者・Web担当者
- ランディングページの構成要素と最適化手法を体系的に学びたい
- コンバージョン率向上の具体的な改善策を知りたい
- 実際の事例を通じてPASONAの法則やベネフィット訴求の実践方法を理解したい
伊藤:はい、では本日も始めていきたいと思います。画面を共有させていただきます。
伊藤:では3回目ということでですね。なかなか忙しくなってくると、資料をご用意するのもなかなか厳しいものがあるかなと思っていますので、後期はできれば皆さんのケーススタディみたいな話に持っていけると僕も楽でいいし、皆さんより持ち帰るものが増えてくるかなというふうに思います。
伊藤:3回目の本日ですが、「ランディングページを作ろう」というテーマにいたしました。戦略上やっぱり早めにランディングページを作って試しておいたほうがいいですよっていろんな効果を見込めるし、そうですね。ランディングページ自体がその事業ドメインの方向性を決めていくためにいろんなテストを使っていけるよということになってくると思います。
伊藤:まずはじめにですね。ランディングページとはということですが、ランディングページを、Y.Kさんは使ったことあるんですけど、他のお二方、ランディングページという言葉は聞いたことあるよ、あるいは全く聞いたことない。どちらでしょうか。O.Mさんいかがですか。
O.M:ちょっと分からないです。
伊藤:分からないですよね。H.Rさんはいかがですか。
H.R:聞いたことあります。
伊藤:聞いたことあるけど詳しくは分からないよという。
H.R:縦の最初の一発目のページみたいな認識でいます。
伊藤:そうですね。ランディングページとは何かという。英語で最初に到達するページということです。ランディング、着陸する地点というイメージになります。通称LPといいます。広い意味ではユーザーが最初に到達したページのことを指します。狭い意味では広告用に特別に作成した専用のページということになってきます。
伊藤:広い意味で言えば、ブログの記事に最初にユーザーが到達しているかというところ分析をかけて、今後のブログの記事をどう展開していくかというヒントになりますし、広告の方はですね。LPを作成してそこに広告、飛び先をランディングページにすることで、様々なサービスをテストしていけるということになってきます。
伊藤:ランディングページをいくつか、左官のほうでおやりになっていますが、どんな感想をお持ちですか。
Y.K:ホームページとランディングページで、要望書のところにも書いたんですが、僕はランディングページだけでもホームページの代わりになるのかなと思っているので、やっぱり広告に特化した専用ページということなんで、まずランディングページ作って、ランディングページにSNSをつなげて、それで実績ができたらホームページっていう流れが何か頭の中に出来上がっているのと、やっぱりランディングページって広告に特化したページなので、ユーザーさんにはすごくリスティング広告と合わせて使えば有効だという認識です。
伊藤:分かりました。ありがとうございます。まさにこの次の単元になりますね。ランディングページ何がいいのっていうところですと、1つの単一のページなので、すぐにテストをスタートすることができるということですね。通常のサイトとは切り離されている構造で運用をスタートすることができます。
伊藤:なので、サービスの概要だとか、それからブログ記事だとかっていうのを用意するのを充実させるのは結構大変なんですね。半年とか1年かかってくるんですけれども、ランディングページであれば、いわゆるペライチのページのみなので、すぐに実行できてテストがしていけるという形になります。
伊藤:LPの仕組みですけれども、原理原則で言うと単一ページ、色々ポチポチ押して違うページに飛んだりしません。それから基本的には1つのページで1つの商品を売っていくということが定義になってきます。
伊藤:皆さん、ジャム理論というのを聞いたことあるでしょうか。聞いたことあるよという方。アメリカのコロンビア大学の有名な実験になります。スーパーでジャムの試食をお客さんにさせます。ジャムが5種類試食できるところと、ジャムが20種類試食できるパターンで実験をしたんですけれども、売上の件数が上がったのは5つの試食をさせた方でした。
伊藤:つまりどういうことかというと、いろいろあると選べなくてお客さん離脱するということなんですね。なので、このことからも分かるように必ず1つのページで1つの商品を売り切るというところがランディングページの仕組みになってきます。
伊藤:やっぱり総合的なサイト、ブログ記事もあったりとかサービスの概要ページがあったりすると、ぽちぽち押してるうちにお客さんは頭が飽和状態になって離脱してしまうということがウェブのマーケティングでもよく言われているので、必ず単一ページ、単一商品というところでぜひランディングページを作っていってください。
伊藤:では、どんな商品を並べたらいいということですね。実はウェブサービスに限らずですけれども、本当に買ってほしい商品、こちらが売りたい商品というのはいきなり売れないことがほとんどです。なので、商品の属性を分けてください。バックエンド商品とフロントエンド商品という言い方をしていきます。
伊藤:バックエンド商品とは何か。価格が高くて本来売りたいものですね。一般的なラインで言うと3,000円以上のものはバックエンド商品に分類されるので、その手前にもう少しハードルが低い商品、サービスを提供する必要があると言われている。
伊藤:反対にフロントエンド商品ですね。価格が安いということ。売るのではなく見込み客を集める感覚で展開することが多いですね。例えばサンプル品、無料サンプル差し上げますよとか、お試しセット、詰め合わせセットを特別価格で提供します。あるいはですね、もうちょっと説明が必要な商品だったりすると、例えば家を建てるためのノウハウを提供します。ダウンロード無料ですよみたいな形で、リストだけ最初に集めるみたいなパターンが多く見られます。
伊藤:ではですね、ここで皆さんに今からご自身のサービスが、バックエンド商品は何?それからフロントエンド商品に相当するものはどんなものがあるかというところを、ちょっと考察いただければなと思います。Y.Kさんいかがでしょうか。Y.Kさんの場合、二つサイトをやられていて、左官のほうもあれば、コワーキングスペースのほうもあると思いますが、どんなバックエンドとどんなフロントエンドがあるでしょうか。
Y.K:左官のほうのサイトで実際にランディングページを出させていただいて、これは伊藤さんにお世話になって、タイル工事をワンプライスで提供するというもので、タイルの貼り替えのランディングページなんですが、それがフロントエンドで、日給5万だかを、格安で1日2日でタイルが貼り替えられますよという商品、そういうランディングページを出させていただいて、実際の話ですね、問い合わせが10件以上あって、そのタイル工事が売れたのが1件もないんですよ。
Y.K:すべてタイル工事LPから左官工事で1件は80万ぐらいの工事を受注されたということで、フロント、バックエンドはやはり3万円以上で書いてますけど、僕らの場合はフロントエンドが3万の商品ですけど、実際に行ってみてリアルでお話をすると、ここもあれもそれもということで、左官工事がそれにひっついてくるという、そういうバックエンド、フロントエンドの商品です。
Y.K:もう一つのサイトは、レンタルキッチ、レンタルオフィス、コワーキングスペース、フリースペースというふうにあるんですが、価格はそこそこ並み、この地域、そんなにそういうオフィス、レンタルスペースがないので、地域に合わせて決めました。来ていただく方がですね、レンタルオフィスで来てもまた違うもの、違う発想でいろいろお話をいただくので、部屋を借りる、スペースを借りるというところから、また違うところに移ってくる、バックエンド商品ということがそこに当たるのかなと思います。
Y.K:フロントエンドは場所貸しですけど、バックエンドにはまた違うもの、ランチ営業をしたりとか、相談事業をしたりとか、そんなことになってくるのが、ローカルビジネスのフロントエンド、バックエンドということです。伊藤さん、ちょっと僕のしゃべりがうまくできなかったら、何か補足説明していただければと思います。
伊藤:そうですね。場所貸しみたいなものは、この後やりますけど、いわゆるコモディティ化している商品サービスになるわけですね。他所でも同じようなクオリティのものはやってるサービスはある中で、バックエンドの部分ですね。例えば、誰かとコラボレートができるとか、集客ができるとか、あとはセミナーなんかを定期開催していて、賢くなれると。そういうものがおそらくバックエンド商品に相当するものかな。ここはいわゆる味付けの部分なので、Y.Kさんの個性を発揮していってですね、それがイコールこの場所の魅力、他所にはない魅力になってくるのかなというふうにお見受けしております。
伊藤:では、H.Rさんいかがでしょうか。フロントエンド、バックエンド、いろんな買取の形態であったりジャンルであったりという部分を1年以上やられてると思うんですが、いかがでしょうか。
H.R:バックエンドは買取単体で考えると、多分貴金属とかブランド品になって、フロントエンド商品は雑貨等々になるのかなと思います。で、不動産との全体のことを考えると、バックエンドは、遺品整理から不動産、空き家の売買まで全部つながるのがバックエンドなのか、それともその中で買取がもうすでにフロントエンドで不動産がバックエンドになるのかなと思いながら今考えている。
伊藤:そうですね。背景には不動産屋の活動があるので、不動産とか空き家みたいなもののバックエンドを持ちながら、そのフロントエンドとして買取センターがあるわけですね。で、買取自体もフロントエンドとバックエンドという形で分けていくと、より商売が加速していくヒントになるかなと思います。高級ブランド品とか貴金属ってやっぱり儲けが大きいわけですか、
H.R:そうですね。利益も取れるし、早いので必ず業者さんが買ってくれるっていう面で流れが早いので、在庫は不良在庫になってしまうことが多いので、必ず売れるという点で利益が出やすいです。
Y.K:必ず売れるってなるもんね。
伊藤:そうですね。フロントエンドイコール入口商品といったりしますけれども、そこを高速で回転させることでバックエンドの動きが良くなるということがあるので、ジャンル特性とか季節消費材とか、いろんな買取の場合いろんな条件があると思いますが、その辺りを工夫していただけるといいかなと
伊藤:最後、O.Mさんになります。これまでやられていた壁紙スクールの観点でもいいですし、これから展開されるウェブサイトのことでもいい、どちらでも構いませんか。フロントエンドとバックエンドの解説をお願いします。
O.M:そうですね。実はあまり意識をしたことがなくて、お話を聞いていて、用意しなくてもいいんじゃないかなというふうに私自身そんなことを思っちゃってて、あえてフロントエンド商品を出さなきゃいけない理由というのは、私の今までの過去の経験の中で、あまりやりたくなかった商品群というようなイメージです。
O.M:それぞれ売りたいものに対しての、それぞれの価値をどう見せるかということで考えてて、しなきゃいけないのかなというふうに。逆にこのフロントエンド商品を作ろうとするがために無理が来てしまったり、逆に忙しすぎてしまったりとか。それが本業になってしまって、本来やらなきゃならないことがおろそかになってしまったりとか。
O.M:というような形で、フロントエンド商品を見つけようとするがために、そこに時間を費やされてしまうんじゃないのかなというようなことを、実はお話を聞いていて感じてしまいました。
O.M:ちょっと趣旨が違うかもしれないですけど、サイトで何かを売るというときは、何でも広告でもチラシでも同じように、目玉商品というのはあるのかもしれないですけども、これから私がやろうとしていることに関しては、フロントエンド商品をあえて作ろうとはしないだろうなというふうに私自身は感じています。はい、以上です。
伊藤:忙しくなればやめればいいし、忙しくなれば単価を上げればいいだけなので、たぶん全くやらないというのは非常に悪手になる可能性が強いですね。
伊藤:おそらくフロントエンドに近いものは、のり付き壁紙の物販というところはおそらくフロントエンドに近い。全員が全員、高級品とか輸入壁紙に興味を持つ方だけではないんですけれども、そういう方が口コミで広げていただけるというところにチャンスがあるんですね。
伊藤:フロントエンドの役割というのは、実績を上げてたくさんいい評価がつくというところなので、必ずしも安売りはやりたくないよということであれば、そっちからのほうに舵を切っていただくということが、販売促進につながっていくのかなというふうに思います。
この項のまとめ
- ランディングページは「単一ページ・単一商品」の原則で、迅速なテストマーケティングを可能にする
- フロントエンド商品(3,000円未満)で見込み客を集め、バックエンド商品(高単価)で収益を最大化する戦略が重要
- ジャム理論が証明する通り、選択肢を絞ることで顧客の購買行動を促進できる
- 左官業では3万円のタイル工事LPから80万円の左官工事受注につながる実例がある
- コモディティ化した商品でも、独自の付加価値やコラボレーション要素をバックエンドに組み込むことで差別化が可能
伊藤:続いて参ります。では、LPにはどんな情報を記載すべきかということですね。PASONA(パソナ)という書き方があります。結構使い古された、もう20年以上前からある方法なんですけれども、いまだに有効なので、もしLPを作るときはその観点で書いていっていただけるといいかなと思います。
伊藤:こんな内容になります。Pがプロブレム、問題点ですね。こんな問題ありませんか、みたいな問いかけをしていきます。2番目がアフィニティ、親近感ですね。なんか共感を呼ぶような要素を入れてくださいということになります。それからそれに対してソリューションですね。どんな解決方法がありますよという提案をしていきます。
伊藤:それからオファー。特に重要なのが、機能とかメリットではなく、後ほどやりますが、ベネフィットを伝えることが重要だと言われています。それからナローダウンですね。これは2つあると思います。一定期間で割引してますよ、みたいなセールストークもありますし、もう1個はすごくいい商品なんですけど、みんながみんなにお勧めする商品ではありません。
伊藤:但し、こういう方とかこういう方であれば絶対満足していただけますみたいに、あえて全員に好かれないセールストークをしたりするわけです。それから最後、アクションになります。コンバージョンによってアクション変わってきますけれども、直接的な購入であったりとか、ホワイトペーパー。ノウハウをまず教えてあげますよということでリストを得る。
伊藤:それから最近だとオンラインセミナーとかSNSのフォローに誘導するみたいな形を取るパターンが多いです。パソナの法則の説明になりますが、Y.Kさん、何かお感じになったことありますか。
Y.K:ウェブで一番売れるのがハゲデブエッチなんで。これハゲデブエッチのランディングページを見たりとかすると、このハゲデブエッチってそうだなと思いましたっていうことですね。
伊藤:そうですね。なので今まではいわゆるセールスのためのランディングページをご覧になったときに、主観的な分析しかできなかったはずなので、このパソナの視点で今後LPをご覧になっていくと、ああ、こういうことをやりたいんだな、伝えたいんだな、みたいなことが分析的に分かってくるかなというふうに思います。
伊藤:AIの生成のシステムが間もなく導入とお聞きしていますが、ランディングページは作れたりしそうですか。それともブログのみ。
H.R:ブログのみです。ランディングページに関しては、こないだドメイン寄せてどうしますかとか言っていた方たちが作ってくれるんですよ。ホームページみたいな感じで、ランディングページって言うんですかね。ホームページを作ってくれて、その中でウェブをAIで回していくっていう感じになります。
H.R:今、ランディングページは最初の打ち合わせが終わって叩き台を作っていただいていて、20日に最初の案が出来上がってくるっていう感じです。
伊藤:ウェブサイトやブログとランディングページは別物なんですね。先ほど申し上げた単一ページ、単一サービスになるので、もしその機能がそのシステムでできないのであれば、例えばペライチみたいなもので作って、そこを集客のツールとして運用していくといいかなと思いますし、LPの機能をつけてよって言えば、その中で構築できる可能性もあるので、一度問い合わせしてみるといいかなと思います。
伊藤:特にH.Rさんの場合は、どの方向性に進んでいくのかっていうところが、まだ見えてない部分があるので、サイト全体を作るのめちゃくちゃ時間かかる、お金もかかる、人が動くってことはお金がかかるということなので、ぜひランディングページをいくつか試してみて、打率のいいものを事業ドメインに選ばれるといいかなと思います。
Y.K:まずやってみて、どこに需要があるか探すのにも、ランディングページが適してるよってことですかね。
伊藤:そうですね。スピーディーにできるので、それをぜひテストとして使っていくといいかなと思います。
H.R:はい、わかりました。やってみます。
Y.K:H.Rさん、ひとつ質問いいですか。今、サイトを作成を依頼してるのは、どちらに依頼してるんですか、今。
H.R:NMという企業で、うちの電光掲示板、電子看板を売り込みに来てくださった会社が、それと込みで看板とウェブと両方マーケティングをできますよっていうことで、AIを使ったやつをやりませんかっていうところに一括でお願いしていて、そこの下請け、担当の会社のところがウェブページを作ってくれています。
Y.K:基本ソフトはワードプレスですか、WixとかStudioとか、それはプラグインで追加機能をするときにいろいろ違うんですけど、それはご確認されたのか。
H.R:そうですね、ちょっとまだわからないので。
Y.K:以前ホームページ作ったときにPHPだかなんかでやられて、プラグインっていうか追加機能をクラスするときに、やっぱりワードプレスとかStudioとかWixのほうが使いやすかったなっていう、ちょっとそれを思い出しただけです。
H.R:そう、今作ってもらってるやつにプラスで何か付け加えることができるかもしれないっていう感じですかね。
Y.K:今作ってるやつに拡張機能って、例えば決済機能ですとか、決済とか写真の動画、あとはスライドとかいろんなもの、いろんな機能が追加できるのが、システムを組まなくてもアプリを持ってきてつなげるだけでできるっていう、そういうのがワードプレスとかWixとかStudioとかそういうものかなって、今そんな認識なので、今度作られるのが、どういう基本ソフトって、伊藤さん、これ基本ソフトっていう言い方で、基本アプリっていう言い方が正しいのかどうなんでしょうか。
伊藤:CMSと言われる。
Y.K:ああ、CMS、はいはい。思い出しました。
伊藤:おそらく今の段階で何かが明らかになってないっていうことは、独自のシステムなんだろうなと思います。独自のシステムじゃないなら、よそに逃げられちゃう。自由に何かを追加したりっていう機能があるとお金が発生しないので、要はこのシステムいいシステムだなと思ったら、骨抜きにして逃げられないようにするはずです。自社のシステムとして。
Y.K:もう囲い込むための独自のシステムを持ってる可能性があるんですね。そうですね。なので決済追加するよって言うと何十万取られて、あれやこれや細かく金抜かれる可能性はあるかなとは。
Y.K:H.Rさん、一回CMSは何ですかって聞いてみたらいいと思います。
H.R:はい。ちょっと聞いてみます。
伊藤:パソナ、使い古されたセールストークではありますが、何かご意見ご感想などございますでしょうか。
O.M:このランディングページというのは、集客をするために仕掛けとして必要ですよという話なのか、それとも見に来ていただいた方に対して、文章であったり写真であったりというようなものを構築しながら、滞在時間を長くしてもらおうとするものになるんですか、このランディングページというのは。
伊藤:ランディングページは、広告を出して広告を踏んだ人の飛び先になります。なのでSEOの効果はあまりありません。
O.M:ってことは、そこに見に来ていただいた方の滞在時間を長くして、このサイトに興味を持ってもらうための文章なりを構築していきましょうという話になるということですか。
伊藤:興味を持ってもらうというところだとちょっと解像度が悪いんですね。具体的に言うと、このアクションを促すための専用のページということになってきます。当然、広告を踏んだ人は他にもSNSだったりいろんなもので調べたりするので、そのときに我々ご自身がやっているサービスに出会う可能性はありますけれども、基本的にはこのページで刈り取るっていうのが目的になります。
伊藤:そして何らかのアクションを興味を持ってもらうだけじゃなくて、行動させるためのページなので、ぶっちゃけて言うと押し売りのページになる。押し売りのページを作ってるのに綺麗なデザイン、後でやりますけど、見た目のいい、綺麗な感じのページを用意しても全く売れません。なので押し売りのページと割り切ってください。
伊藤:O.Mさんがこれからやられるサイトであれば、問い合わせだったりサイトへの登録を促したりっていうところになるかなと思います。
O.M:わかりました。
Y.K:YouTubeの広告から、よくあるダイエットサプリみたいなやつのイメージしておけばいいですかね。
伊藤:そうですね。SNS広告も今ありますし、それからリスティング広告もありますし、画像とか映像を見せるディスプレイ広告みたいなものもありますけれども、それをサイトのトップに紐づけてしまうと、いろんなページがあっていろんなサービスがあっていろんな情報があるので、お客さん混乱して離脱してしまう。広告が無駄打ちになってしまうんですね。
伊藤:興味のある方を広告でクリックさせて、必ず何かしらのアクションを誘導するのがLPの目的になります。
H.R:すみません。いいですか。具体的にこれで合ってるか。具体的だと私はよくナイトブラが出てくるんですけど、普通のそのやつから入って、ランディングページがその商品を売るページだけで、そこからさらに飛ぶといろんな商品が出てくるのがブランドのホームページみたいな、その間のつなぐその商品のみのカートにすぐつながるのがランディングページですかね。
伊藤:そうですね。先ほどのお話とつながるんですけども、いわゆる–
伊藤:ハードルが低い商品をLPに設定するんですね。でもLPを見に来たお客さんで、我々のサービスに関心が高いということであれば、バックエンド商品を見せていくというパターンも十分あり得ると思います。
伊藤:例えばですね、LPでタイマーをかましている場合があって、3分以上見ているユーザーに対してはスペシャルオファーみたいな、クーポン券を差し上げますよみたいな。なので、LPの中でお客さんを選別していく場合も結構今はあります。
H.R:ありがとうございます。
伊藤:これLPのお話ですけれども、サイト全体にも関わるお話になります。抜け漏れがないほうがいいわけですね。なのでご自身でLPを作ったりとかラフを書いたりする場合に、どんな要素が求められるかというとですね、こういうふうにまとめている人がいました。
伊藤:4つの軸ですね。必要性、優位性、信頼感、安心感というところで、それぞれ構成要素があるので、これまた後で共有しておきますけれども、LPの中でなるべくこういう要素を入れ込んでいったほうがいいんですね。ウェブサイトのほうでもこれらの要素をいろいろと散りばめて構成していくほうがいいと言われています。
伊藤:ベネフィットとか、割と初心者が見落としがちなのが、お客様の声を割と上に持ってきがちなんです。この横軸に沿って、あとは上から順に沿って展開していくほうがいいと言われています。
伊藤:要はですね、お客様、最初からリアルな話をするとですね、引いてしまうケースがあると思います。例えば、不動産でいうと、駅から近くて新しくて安くてみたいな話、そんな物件あるわけないんですけども、そんな物件ないですよって言って、ボロボロの安い物件を出さずにですね、ちょっとずつトークを広げながら最後リアルに落とし込んでいく、みたいな形なので、お客様の声とかFAQっていうのは実は割と下のほうになってくるわけですね。
伊藤:ブランドサイトのコンテンツという構成ですけれども、LPにも通じる部分があるよということになります。
伊藤:あとはですね、LPで最も重要だと言われて、これはブログのほうでも関わりがありますけれども、ファーストビューにこだわろうということですね。ファーストビューとは何でしょうか。Y.Kさんお願いします。
Y.K:ぱっと見、最初に目に入ってくる。ファーストビューを最初に見るということなんで、ランディングページに来たときに一番上の写真とか動画とかのことをファーストビューっていうように。そんなふうに解釈しますけど。
伊藤:そうですね。そのページにお客さんが飛んできて、最初の1画面に映る部分。ここが非常に重要だと言われています。
伊藤:伝えなきゃいけない要素は、そのサービスや商品が一体誰のためのサービス、商品なのかっていうところを分かりやすく伝えてあげたほうがいいですね。後ほどやりますけれども、いわゆる30代女性みたいなゆるい解像度ではなく、もっと明確に前回やりました1%マーケティングですね。100人に1人しか刺さらないけど、超深く刺さるようなものを用意してあげてください。
伊藤:それから冒頭のリード文の面白さ、引き込み具合がですね、そのページを全部見てくれるか、途中で離脱してしまうかっていうところの大きな要素になりますので、冒頭のそのリード文を充実させるということもかなり重要になってきます。
この項のまとめ
- PASONA法則(Problem・Affinity・Solution・Offer・Narrowing・Action)に沿った構成で訴求力を最大化
- ファーストビューでターゲットを明確にし、30秒以内に「自分のためのサービス」だと認識させることが重要
- 機能やメリットではなく「ベネフィット(生活や人生の変化)」を伝えることで心理的訴求力を高める
- 必要性・優位性・信頼感・安心感の4軸で構成要素を配置し、お客様の声やFAQは後半に配置する
- インサイト(深層心理)に訴えかけ、顕在ニーズだけでなく潜在的な後ろめたさや欲求を刺激する
伊藤:時間結構経過してるので次、どんどんいきます。では、LPの勝ちパターン、負けパターンがあるので、そこをちょっとご紹介できたらなと思います。
伊藤:成功するパターンですね。一つがリミットを設ける。今月だけスペシャルプライスです、みたいなことですね。価格で訴求していく。他所は1万円だけど、うちは5,000円で提供してみます、みたいなことですね。
伊藤:それから3つ目。メリットや機能、性能ではなくて、ベネフィットを伝えるということですね。ベネフィットとはどんな例があるでしょうか。
H.R:ダイエットであれば、ダイエットで実質的に65キロが60キロになりましたので、5キロっていう体重減ではなくて、それは数値的なメリットなので、満足感なので。
H.R:ベネフィットっていうのは、痩せたから例えば履きたかったズボンが履けるとか、痩せたから人からきれいになったねって言われるとか、そういうことをベネフィットっていうふうに、お金では表せないこと、心理的な満足感をベネフィットというふうに表現すると思います。
伊藤:そうですね。生活が変わるとか人生が変わるとか、心理的な心情が変わるみたいなところを訴求したほうがいいですので、そのための裏付けで性能とかメリットがあるわけですね。そこを取り違えてしまうと、かなり打率が落ちてしまうので、気をつけていってください。
伊藤:それから、インサイトに訴えかけるというようなことも最近言われています。インサイトって何?最近いろんな番組でやったりするんで、ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、本人が欲しいと思っているものは顕在ニーズという定義です。それに対して提案されて初めて気づくものが潜在ニーズですね。
伊藤:インサイトは更にその下の深層心理ですね。例えば、健康的な食事をしなければいけない、健康的な生活をしなければいけないと分かっていても、実際にはやれてない人、僕みたいなダメ人間がいるわけですね。ただ、そういう人に対しては、実はこのサプリメントを飲めば、そこがかなり改善されるんです。要は、後ろめたい自分を刺激してあげるということですね。こんなことも最近ではよく行われています。
伊藤:それから、今度は失敗パターンですね。あれもこれもは駄目ということですね。先ほど、LPとは何というところの定義にも合致しますけれども、単一のページで単一のサービスなので、例えば、Aセット、Bセット、Cセット、5種類あるよりは、1セットとか2セット、3セットのほうが売上が高くなるわけですね。
伊藤:原理原則は1パーセントマーケティングというところなので、みんなに好かれようとすると、1個も売れないという形ですね。なので、1パーセントマーケティングで、深くぶっ刺さる商品を展開していく必要があるわけです。
伊藤:それから、デザインにこだわってしまうと、先ほど言ったように、ああ、なんか綺麗なページね、素敵なサービスね、でも俺と関係ねえやっていう話になりがちなんですね。原理原則としてはですね、制作会社の人はデザインは詳しいですけども、商売人ではないんですね。なので、丸投げするととてもひどいページ、訴求力がないページになります。
伊藤:訴求力が落ちる原因は何かというと、絵空事だからですね。デザインが悪いのではなくて、売れないときは商品が悪いんじゃないか、ということをぜひ再検討してください。それから基本的には短期決戦に向いてない商品というのは、LP作ろうが、広告を引っかけようが、売れないものは売れないんですね。
伊藤:売れないパターン2つあります。前回やりました、ニーズが顕在化していない商品。これは短期決定は難しいので、広告売ってもダメよねという話になります。どうするかというと、楽天みたいなモール店で売れれば、まだ販売できるチャンスがあります。
伊藤:それからLPで直接的には売れないので、先ほどのホワイトペーパーとか、あとはメルマガ登録しませんか、みたいな形でワンクッションを置くというのも1つの手になります。
伊藤:もう1つはですね、コモディティ化している商品という形になります。コモディティ化、H.Rさんは聞いたことありますか。
H.R:わかんないです。
伊藤:分かりやすく言うと、どこでも買えちゃう商品ということですね。なので、例えばここでしか買えませんよというような商品が、魅力的な商品があれば、その独自ドメインのサイトで登録して、お客さんは買いますけれども、これが楽天でもAmazonでも売ってるんだったら、じゃあそっちでもいいよねっていう話になってしまうわけです。
伊藤:なのでコモディティ化している商品であれば、モール店で売ったりっていう手もありますけども、ただし価格競争が非常に厳しいので、その商品が1個売れたとしたら、利益いくらなのっていう話ではなくて、広告宣伝費として捉えるべきですね。お客さんの入り口商品として捉えて、展開していくといいでしょう。
伊藤:それから先ほどありました、滞在時間ですね。増やしたほうがいいんじゃないですかという話がありましたけれども、LPのそもそもの目的というのは、販売とかアクションを起こさせることになりますので、基本的には滞在時間20秒以下は不合格なので、改善していったほうがいいんですけれども、求められるべき指標というのがいくつかあります。
伊藤:代表的にはこの3つですね。滞在時間、30秒から60秒あれば十分だと思います。じゃあこれが2分間になれば2倍売れるかというと、そういうものではないんですね。
伊藤:ではどういう要素を改善していくかというと、先ほどあった冒頭にあなたのためのサービスが必要というところを強化していくんですね。前回やりましたね。デモグラフィックではだめですよねという。要は青いゾーンの分類ではもう通用しなくなっているので、この価値観であったりとか趣味、趣向性みたいなところを明確に打ち出してあげる必要があるわけです。
伊藤:それから使用例なんかをたくさん写真を見せてあげることも、この合格ラインに持っていくためには必要なアクションかなと思います。ただ一方でですね、画像が多すぎるとページのスピードが落ちるので、それが離脱につながってしまうという可能性もあるので、サーバーのスペックと相談しながら適切な枚数を選んでいきましょう。
伊藤:それからアンケート方式であなたは何々タイプですみたいに分類させてあげるものも、お客さん楽しみながら挑戦してくれるので、結果的に滞在時間の改善につながったり。
伊藤:滞在時間と並行して重要な要素、エンゲージメント率というのがあります。お客さんが興味を持ってもらった率というのがあります。これは大体80%以上あればいいかなと思います。100%を目指したところでですね、じゃあその分売れるかというと必ずしもそうではないということですね。
伊藤:数値を改善するためには先ほど申し上げたファーストビューの工夫が必要になります。もう一つがページのサイトスピードを改善するというアクションですね。ファーストビューに来る画像のメモリー、重さを少し軽くしてあげるとかの措置が必要になってきます。
伊藤:それからコンバージョンレートですね。コンバージョンレートとは何でしたでしょうか。O.Mさんお願いします。
O.M:何回見に来てくれたかでしたっけ。
伊藤:それはセッション、訪問回数ですね。訪問回数は計算式の中には入ってる。関連はあるんですけども。O.Mさん、コンバージョンレートわかりますか。
Y.K:訪問数の成果の率、コンバージョン率っていうのは、100人来て10人だったら10%。そんな評価の基準だったと思います。
伊藤:日本語で言うと転換率と言ったりしますけれども、CVR、コンバージョンレートですね。コンバージョン率、先ほど申し上げたアクションですね。購入の場合もあれば問い合わせの場合もあったり、あるいはSNSの登録であったりする場合もあります。
伊藤:それを訪問数で割った、セッション数で割った数がコンバージョンレート。要は売れたりアクションしてもらったりする打率のことを言います。これが大体1%から5%ぐらいであれば合格点かなというところになります。
伊藤:ただ、これコンバージョンレートの分母の方をセッションにするのは、ちょっとあまり良くないなというふうに私は感じています。月間ですね、何十万とか何百万の来訪者がある場合はこの計算式でいいんですけども。
伊藤:基本的に小さいサイトはユニークユーザー、何人来て何人アクション起こしたかということで見ていった方がいいかなと思います。飲食店の売上分析の客数じゃなくて組数で見た方がいいよみたいなところに近い部分があります。
伊藤:ではこれをどうやって改善していくかというところなんですけれども、先ほど申し上げた単一のサービスより内容をシンプルにして分かりやすく伝えてあげていった方がいいでしょう。
伊藤:それからスペック的な説明に走りがちなんですけれども、ヒューマンタッチの部分がかなり重要だと言われています。専門性や実績ももちろん大事なんですけれども、人柄だったりですね。
伊藤:最近分かっているのは小さな共通項でユーザーはサービスや商品を選別しているらしいんですね。なので練馬に住んでますとか、飲みすぎた次の日はプチダイエットで断食してますみたいなところが刺さったりするわけですね。
伊藤:可能な限り店長さんだったり代表者のパーソナルな部分は出しておいた方がいいでしょう。
伊藤:先ほどありました絵空事で終わらせないということですね。冒頭には夢物語としてこんな素敵なサービスなんですよ、商品なんですよというふうに伝えておいて、後半のほうではしっかりリアルを見せていく。より購入に近い方には具体的な事例を見せてあげたほうがいいというふうに言われています。
伊藤:私の方で今日ご用意したのは以上ですけれども、何かご意見ご質問などございますでしょうか。
Y.K:最後のところで絵空事から最後リアルを見せるっていう、最初に夢を語ってそれからリアルを見せるっていうのはいいなと思います。
Y.K:実際のレンタルスペースのビジネスでも、絵空事でこんなふうに起業できたらいいんですね。だけど起業はこんなに難しいんですよっていう。絵空事から夢物語で空想させて、リアルを見せて、覚悟を決めさせるっていう、そういう流れの順番になりました。ありがとうございます。
この項のまとめ
- 成功パターン:リミット設定、価格訴求、ベネフィット重視で「押し売りページ」として割り切る
- 失敗回避:「あれもこれも」の複数選択肢、過度なデザイン重視、ニーズ未顕在化商品の直接販売を避ける
- 重要指標:滞在時間30-60秒、エンゲージメント率80%以上、コンバージョン率1-5%を目標値とする
- 小規模サイトではセッション数よりもユニークユーザー数を分母としたCVR計算が実用的
- ヒューマンタッチ要素(代表者の人柄や小さな共通項)を含め、絵空事から現実的な事例へ段階的に誘導する構成が効果的