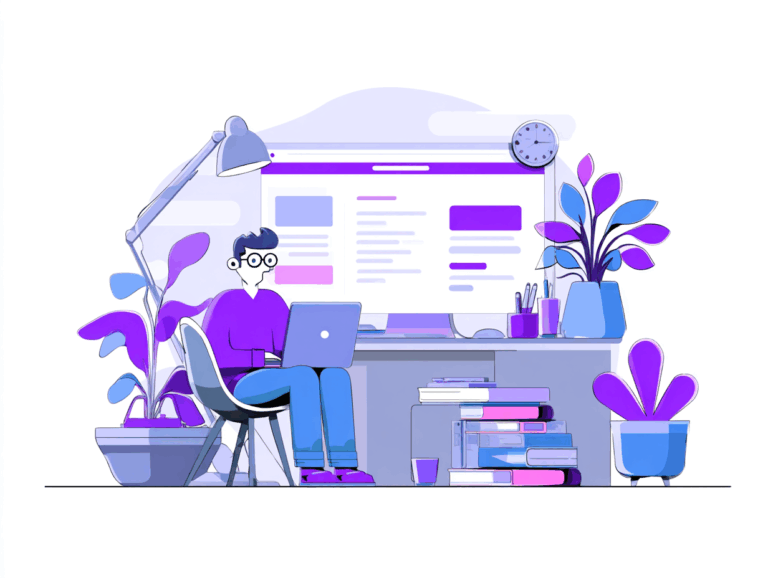
「なぜLP外注は失敗するのか? 内製化・インハウス時代に発注者が持つべき視点」
※この記事はオンラインサロンの内容を元に作成しています。
目次
LP外注でつまずく前に——「内製化」と「発注者の視点」を武器にする
「ランディングページ(LP)をプロに外注したのに成果が出ない——」。多くの企業が直面するこの外注失敗の背景には、デザインと戦略の乖離があります。見た目は美しいのに、ターゲット設計やペルソナ設定、明確なコールトゥアクション(CTA)、測定可能な KPI/KGI が欠けている。結果、**コンバージョン率(CVR)**が伸びず、改善の糸口も掴めないまま終わってしまう——これが“お絵かきLP”問題の正体です。
同時に、ツールの進化が招いたオペレーター化問題も深刻です。言われた作業は速いが、仮説検証やプロジェクト進行管理、UI/UX改善まで統合的にリードできる人材は少数派。だからこそ、発注側が発注者の視点を磨き、制作会社選びの基準を持ち、必要に応じてインハウス化/内製化へ舵を切ることが、最短で成果に到達するルートになります。
本記事は、マーケティング初心者のWeb担当者や意思決定者に向けて、LP外注の落とし穴と回避策を解説します。E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を踏まえた情報設計、SEOと広告の使い分け、競合や他業界から学ぶベンチマーク分析の要点、そして現場で機能するWeb担当者育成の勘所まで——“外注に依存しない成果設計”を、一次情報ベースで丁寧に紐解いていきます。
中小企業の経営者・発注者
LPやWeb制作を外注したものの成果が出ず悩んでいる人。
今後の投資判断として「外注を続けるか、内製化に舵を切るか」を考えている層。
企業内のWeb担当者・マーケティング初心者
上司や経営層から「成果を出せ」と任されているが、制作会社の提案の良し悪しを判断できない人。
発注者の視点やKPI/KGI設計など、最低限の基礎を学びたい層。
フリーランス・Web制作者
ただの「オペレーター」から脱却し、クライアントに信頼されるエキスパートになりたい人。
UI/UX改善やベンチマーク分析など、成果に直結する観点を取り入れたい層。
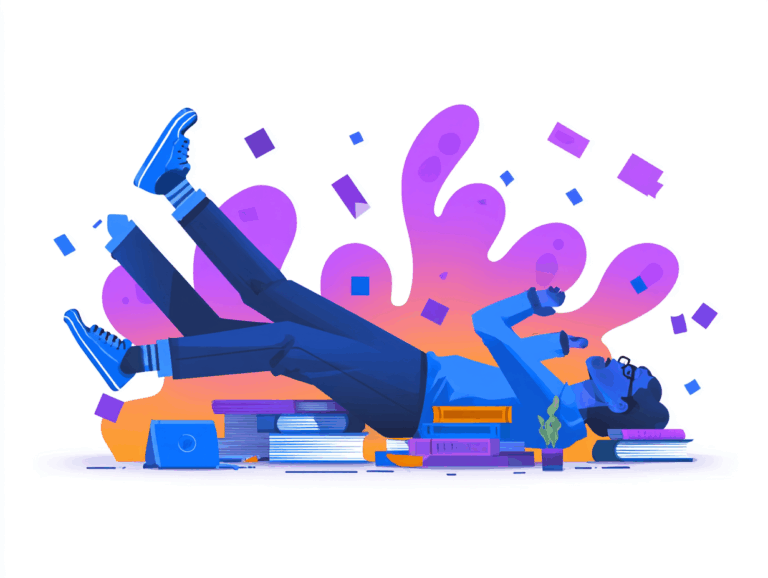
「お絵かきLP」に終止符を。WEB発注者と担当者が今、学ぶべきこととは?
外注したはずのランディングページ(LP)が、全く成果を生まなかった——。これは多くの企業が経験する典型的な外注失敗のひとつです。デザインは洗練されているのに、ターゲット設計やペルソナ設定が曖昧で、**コールトゥアクション(CTA)の位置も不明確。結果としてコンバージョン率(CVR)**は上がらず、KPI/KGIを測定する前に施策が空回りしてしまいます。
こうしたページはしばしば「お絵かきLP」と揶揄されます。PhotoshopやAIツールの普及で誰でも形だけのデザインは作れるようになりましたが、問題はUI/UX改善や課題解決の設計力が伴っていないことです。つまり「作れる人」は増えたのに、本当に成果を出せるエキスパートはむしろ減少しているのです。
では、どうすればこうした失敗を避けられるのでしょうか?
答えは、発注者と担当者の双方が最低限のマーケティング視点を持つことにあります。たとえば、
相手の言語力や説明力から、実力や理解度を見極める
ポートフォリオをただ眺めるのではなく、制作の意図や戦略を質問して深掘りする
ベンチマーク分析を行い、成功事例との違いを把握する
といった姿勢が不可欠です。
E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)が重視される時代、見た目がきれいなだけのLPは淘汰されます。発注者側も「任せきり」ではなく、判断基準を持ち、必要に応じてインハウス化/内製化へとシフトしていくことが、長期的な成果につながるのです。
この項のまとめ
- 成果が出ないLPは「お絵かきLP」:デザイン重視で戦略やターゲット設計が欠けている。
- 外注失敗の典型例:CTA不明確、ペルソナ設定不足、CVRが改善しない。
- 本質的スキル不足:ツール普及で「作れる人」は増えたが、UI/UX改善や課題解決に強いエキスパートは減少。
- 発注者・担当者の視点が必要:言語力や説明力で実力を見極め、ポートフォリオの裏付けを確認する。
- 内製化・インハウス化の重要性:E-E-A-Tが重視される時代、自社内でマーケティング視点を持つ人材育成が成果の鍵。

外注したのに成果が出なかった。あるLP制作の苦い経験
私がオンラインサロン勉強会を始めたきっかけは、私のクライアントがLP制作を外注して成果が全く出なかった体験にあります。社内にノウハウがなかったため「プロに任せれば安心」と考え、評判の良い制作会社に数十万円規模で依頼してしまったのです。制作期間は約2か月。完成したランディングページは見た目こそ美しく、デザイン的にも「成功作」と評価されました。
しかし、公開後の結果は衝撃的でした。
問い合わせゼロ
受注ゼロ
平均エンゲージメント時間は30秒程度
つまり、投資に見合う効果がまったく得られなかったのです。
原因は明確でした。
ターゲット設計が曖昧で、誰に向けたページか分からない
**CTA(コールトゥアクション)**が不明確で行動を促せない
UI/UXの導線設計がなく、滞在時間を伸ばせない
KPI/KGIの設定もなく、改善の指標がなかった
要するに、このLPは「お絵かき遊び」に過ぎなかったのです。
この経験からチームが学んだのは、制作物のクオリティは発注金額に比例しないということ。高額案件でも、制作者が戦略的思考やマーケティング視点を持たなければ成果は生まれません。発注者側も「任せきり」にせず、相手の言語力や説明力を通じてスキルを見極める必要があるのです。
この苦い失敗が、「発注者と担当者こそ最低限の知識を持つべきだ」と痛感させ、オンラインサロン勉強会の立ち上げにつながりました。
この項のまとめ
- 外注したLPは成果ゼロ:問い合わせも受注もなく、平均エンゲージメント時間は約30秒にとどまった。
- 投資と成果が比例しない:数十万円規模を支払っても、戦略のない制作では効果が出ない。
- 主な失敗要因:ターゲット設計不足、CTAの不明確さ、UI/UX設計の欠如、KPI/KGI不在。
- 「お絵かき遊び」問題:見た目は綺麗でも、マーケティング視点が欠けたLPは機能しない。
- 発注者の責任:任せきりではなく、相手の言語力・説明力を確認し、戦略的思考を見極める必要がある。

これからの流れは、アウトソーシングから“内製・インハウス”へ
なぜ「お絵かきLP」のような外注失敗が繰り返されるのでしょうか? 背景には、Web業界の構造的な変化があります。
かつては制作を外注すれば、一定の成果が得られる時代もありました。しかし、業界が高度化・分業化した結果、個々の領域に特化したスペシャリストは増えた一方で、戦略から実装まで統合的に判断できるエキスパートが不足しています。つまり「ページを作れる人」は多いけれども、「成果を設計できる人」は極端に少ないのです。
さらに、成果を左右するのは「何をつくるか」よりも「誰に届けるか」。このターゲット設計を誤ると、どれだけデザインが美しくてもコンバージョン率(CVR)は伸びません。ある企業では、外注したLPの平均エンゲージメント時間が30秒程度しかなかったのに対し、社内で内製化して改善した結果、1分以上に伸びたという事例もあります。
今後のトレンドは明確です。
アウトソーシングは縮小し、必要最低限の部分に限定される
社内に専門人材を招き入れるインハウス化が加速する
AI活用を前提に、社員自身が学びながら施策を回す内製化が主流になる
特にAIや自動化ツールの進化で、知識やノウハウの取得ハードルは大幅に下がりました。その結果、発注者側が判断軸を持ち、Web担当者育成に力を入れる企業こそが、長期的な成果をつかむのです。
この流れを受けて、私は「単なる制作依頼」から「学びと実践の場」へと軸足を移し、オンラインサロン勉強会を立ち上げました。SEOと広告の使い分けやベンチマーク分析、そして実務で使えるUI/UX改善の知識を共有し、各社が自走できる体制づくりをサポートするためです。
この項のまとめ
- 業界構造の変化:Web業界は高度化・分業化が進み、統合的に成果を設計できるエキスパートが不足している。
- ターゲット設計の重要性:何を作るかではなく「誰に届けるか」が成果を左右し、誤るとCVRが伸びない。
- 内製化の成功事例:外注LPでは滞在30秒だったが、内製で改修した結果、1分以上に改善した事例がある。
- 今後の主流:アウトソーシングは縮小し、インハウス化と内製化が企業の成果を左右する鍵となる。
- AIと人材育成の融合:AI活用により知識取得のハードルが下がり、Web担当者育成を進める企業が成果を上げやすくなる。
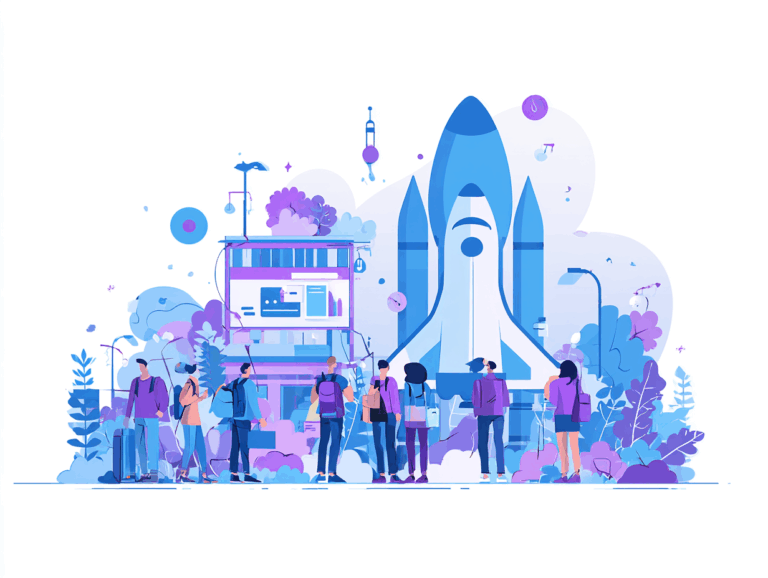
発注者・担当者が持つべき視点
外注した制作物が「お絵かきLP」になってしまうか、それとも成果につながるLPになるか。その分岐点は、発注者や担当者の視点にあります。任せきりにせず、最低限の判断軸を持つことで失敗を大きく減らせます。
まず重要なのは、相手の言語力と説明力を見極めることです。制作会社やフリーランスと打ち合わせをするとき、言葉が表層的で抽象的に感じる場合は要注意です。知性は言語力に比例すると言われるように、きちんと論理的に説明できる人こそ、課題の本質を理解している可能性が高いのです。
次に、ポートフォリオの確認です。ただ「見た目が良い」かどうかではなく、「なぜこの構成にしたのか」「どんなターゲットを想定したのか」「CTAの配置をどう工夫したのか」といった、戦略的意図の有無を質問しましょう。ここで曖昧な回答しか得られない場合、その制作者はオペレーター化している可能性があります。
さらに、制作段階ではUI/UX改善やベンチマーク分析の観点を持つことも大切です。競合や成功事例を調べ、KPI/KGIを明確に設定したうえで、どの部分を改善すれば**コンバージョン率(CVR)**が伸びるのかを見極める。このプロセスを共有できるパートナーを選ぶべきです。
最後に強調したいのは、**E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)**を意識することです。特にBtoBや中小企業では「信頼性」が成果を左右します。情報の透明性、実績の開示、レビューや顧客の声を取り入れることで、LPの説得力は格段に増します。
発注者や担当者がこうした視点を持つだけで、外注の質は大きく変わります。そして、いずれはインハウス化/内製化を視野に入れ、自社の人材を育成することが長期的な成功につながるのです。
この項のまとめ
- 言語力と説明力の確認:抽象的な会話しかできない相手は要注意。論理的な説明ができるかが実力の指標になる。
- ポートフォリオの裏付け確認:デザインの見た目だけでなく、ターゲット設計やCTA配置の意図を質問して判断する。
- オペレーター化の回避:言われた通りに作るだけの制作者では成果が出にくい。戦略的思考を持つパートナーを選ぶ。
- UI/UX改善とベンチマーク分析:競合や成功事例を参考にし、KPI/KGIを設定してCVR向上の施策を検討する。
- E-E-A-Tの意識:専門性・権威性・信頼性を高める情報発信を行い、発注側も内製化・インハウス化を見据える。
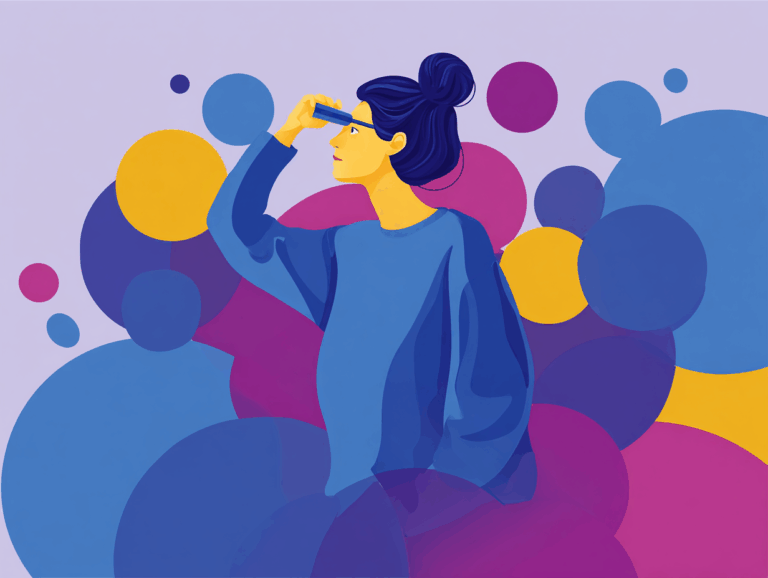
まとめ & 次アクション
ここまで見てきたように、LP外注の失敗は決して珍しいことではありません。見た目が整った「お絵かきLP」では、ターゲット設計やCTAの設計が不十分で、成果につながらないケースが多発しています。外注失敗を避けるには、発注者と担当者自身が最低限のマーケティング視点を持つことが欠かせません。
特に、以下の3点を意識することで成果は大きく変わります。
UI/UX改善の基準を理解する
KPI/KGIを明確に設定する
E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を意識した発信を行う
今後のトレンドは、確実にインハウス化・内製化へと進みます。AIや自動化ツールの進化により、知識の取得コストは下がり、Web担当者育成の重要性が増しています。外注そのものがなくなるわけではありませんが、「任せきり」から「協働型」「自走型」へシフトすることが求められるのです。
次のアクションとしておすすめしたいのは、まず自社の現状を棚卸しすることです。
外注依存度はどの程度か
社内にマーケティングの知識を持つ人材はいるか
競合のベンチマーク分析と比べて何が不足しているか
これらを整理することで、内製化をどこから始めるべきかが明確になります。そして、少しずつでも自社でSEOと広告の使い分けや改善施策を回せる体制を築くことが、中小企業や個人事業者にとっての最大の武器となるでしょう。
この項のまとめ
- お絵かきLPの限界:デザイン重視で戦略やターゲット設計が欠けると成果につながらない。
- 発注者・担当者の責任:最低限のマーケティング視点を持つことで外注失敗を回避できる。
- 成果を変える3要素:UI/UX改善、KPI/KGIの明確化、E-E-A-Tを意識した発信が不可欠。
- 内製化・インハウス化の重要性:AIの進化で知識取得コストが下がり、自走型の体制構築が求められる。
- 次のアクション:外注依存度や人材状況を棚卸し、ベンチマーク分析を通じて不足点を把握する。
編集後記
Web集客を目指す皆さんへ。成果が出ない外注や「お絵かきLP」の失敗は、誰もが一度は通る道です。大切なのは、その経験を糧にして課題を見極め、自ら学び直す姿勢を持つこと。インハウス化や内製化の流れは追い風です。迷いや不安を感じても、挑戦を重ねることで必ず実力は積み上がります。あなたの一歩が未来の成果につながるはずです。

メタ思考のグリアに参加しませんか?
毎月第三火曜日に開催!無料枠はどなたでも参加できます。
[無料枠] 17:00~17:30 [有料枠] 17:30~18:30

講師紹介
株式会社ボンセレ 代表取締役
伊藤 祐介(いとう ゆうすけ)
❖ プロフィール
東京出身の“氷河期世代”。
身長182cm、見た目は大きめ、中身は細かめ。
公務員からスタートし、フレンチレストラン、築地魚河岸、ワインショップなど、業種も業界も超えて現場を経験。のちに広告代理店、EC支援、WEB制作へと軸足を移し、現在は複数企業のWEB戦略を支援。実務と現場視点に根ざした教育者です。
❖ 専門領域
WEBマーケティング/EC戦略立案
コンテンツ企画・制作
広告運用(SNS/検索)
顧客接点の設計とCRM支援
❖ 教育観・講義スタンス
「右腕は、育てることができる」。
人は“経験”だけでは変わりません。
変化するのは、思考のプロセスを鍛えたとき。
私は現場から、企画・広告・制作・接客・分析まで、すべての工程を実践してきました。だからこそ、「考えて動ける右腕」を育てるには、手を動かし、振り返り、問い直す場が必要だと考えています。
❖ 右腕育成にかける思い
「社長の想いを言語化し、現場に翻訳する存在」が右腕です。
単なるWEB人材ではなく、“経営を理解し、支える人材”を育てたい。
ひとつの強みを見つけ、自分にしかできない貢献の形を築く――
それが、このプログラムのゴールです。
❖ 私のルーツ
仮説実験授業(板倉聖宣 提唱)
科学的な思考法とディスカッションベースの学びに影響を受ける。プログラミングとの出会い
高校時代にBasicからスタート。VBAでの業務改善からWEB制作へ。
❖ 好きなこと
食べること・飲むこと・考えること。
最近のブームは激辛料理(ブートジョロキア)。
この記事に関連する「良くある質問」
-
質問: LP外注が失敗する主な原因は何ですか?回答:
主な原因は「お絵かきLP」問題です。デザインは美しくても、ターゲット設定やペルソナ設計が曖昧で、CTAの配置も不明確。結果としてコンバージョン率が上がらず、KPI/KGIを測定する前に施策が空回りしてしまいます。
-
質問: 制作会社を選ぶ際のチェックポイントは?回答:
相手の言語力と説明力を確認することが重要です。ポートフォリオを見る際も「なぜこの構成にしたのか」「どんなターゲットを想定したのか」といった戦略的意図を質問し、明確な回答が得られるかを判断基準にしましょう。
-
質問: 内製化・インハウス化のメリットは何ですか?回答:
AIや自動化ツールの進化により知識取得のハードルが下がり、社内で継続的な改善が可能になります。外注では平均滞在時間30秒だったLPが、内製化により1分以上に改善した事例もあります。長期的な成果とコスト削減が期待できます。
-
質問: 発注者が最低限持つべき視点とは?回答:
UI/UX改善の基準理解、KPI/KGIの明確な設定、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を意識した発信の3点です。これらの視点を持つことで、「任せきり」ではなく協働型の関係を築け、成果につながるLPを作れます。
-
質問: 内製化を始める際の最初のステップは?回答:
まず自社の現状を棚卸しすることです。外注依存度の確認、社内のマーケティング知識を持つ人材の有無、競合とのベンチマーク分析を行い、何が不足しているかを整理することで、内製化をどこから始めるべきかが明確になります。


