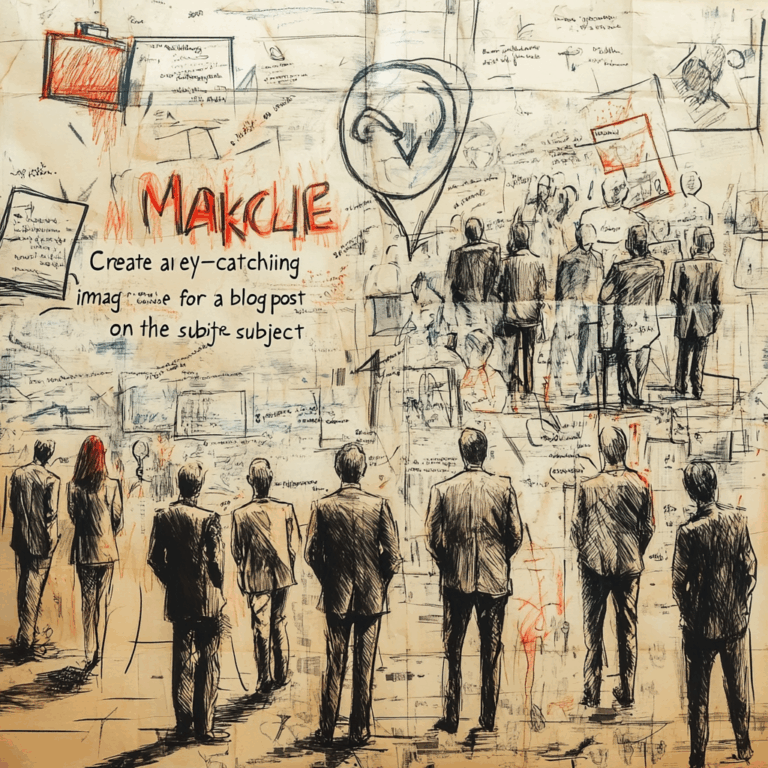
マーケティングはなぜ難解なのか?
※2024年9月の時点の情報となります。
「マーケティングって、難しそう…」
そんなふうに感じていませんか?
このブログでは、実際に行われた初心者向けマーケティング勉強会の内容をもとに、「マーケティングとは何か」「どうやって始めたらいいのか」「職人や中小企業にもどう役立つのか」について、わかりやすく解説します。
講義では、不動産・内装・職人業などリアルな現場で働く方々が、集客やブランディングに関する悩みを持ち寄り、それぞれの課題や工夫をシェアしました。
この記事では、そんな勉強会の中で話された【5つの重要ポイント】を初心者向けに整理しています。
✅ この記事はこんな方におすすめです:
マーケティングを一から学びたい
SNSや広告をどう使うか悩んでいる
自社のサービスや技術を“正当に評価”してもらいたい
「いい仕事してるのに、なぜ売れない?」と感じている
今すぐ役立つヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
参加者の自己紹介とプロジェクト背景の共有
伊藤: それでは皆さまお揃いになりましたので、第1回のウェブ勉強会を始めたいと思います。
伊藤:急遽決まった初回ですので、十分な準備ができておりません。今日は皆さんのご紹介からです。ウェブを通じて今までやってきたこと、これからやろうとしていることを自己紹介と情報共有という形でお話しいただければと思います。まず最初に、そもそも「マーケティングとは何か?」というテーマについて簡単な講義を行い、その後は各自の進捗共有とレビューという形で進めてまいります。
伊藤: では早速ですが、H.Rさんから自己紹介をお願いできますでしょうか。
H.R: はい、東海地方で買取屋をやっています。H.Rと申します。よろしくお願いします。
H.R: Y.Kさんと伊藤さんには、立ち上げのときにいろいろとアドバイスやお手伝いをしていただきました。この買取屋は、私の父が社長を務めている不動産業と一緒に運営している買取専門の店舗になります。以上です。
伊藤: 補足いたしますと、買取屋はY.Kさんの古民家レンタルスペースの隣町にある買取専門店です。販売は行わず、BtoBで商品を売却し、そこから利益を得ている業態です。実店舗を持つ企業様で、サイト制作が必要だったため、立ち上げに際して私とY.Kさんで昨年サポートさせていただいた経緯があります。
伊藤: では続いて、N.Tさん、自己紹介をお願いいたします。
N.T: はい、N.Tと申します。東京在住です。現在、伊藤さんと一緒に内装店のポータルサイトを立ち上げようという形で準備をしています。このサイトでは、いわゆる職人さんのような方々が、正当な評価を得られにくい状況の中で、こだわった工事をしっかり評価してもらえるような環境を作っていきたいと考えています。そんな想いで、サイト立ち上げの準備を進めています。よろしくお願いいたします。
伊藤: よろしくお願いします。補足させていただくと、N.Tさんは過去10年間、壁紙スクールを運営されていて、「貼り方教室」は以前、Y.Kさんのところで実施されていたかと思います。集客手段としてホームページを活用されてきたご経験も豊富なので、この勉強会では全くの新規というよりは、「学び直し」のような立ち位置になるかと思います。
N.T: よろしくお願いします。
伊藤: 続きまして、Y.Kさん、お願いいたします。
Y.K: ありがとうございます。T市で「レンタルスペース」を運営しています。ウェブマーケティングによる集客を行っており、もう一つは左官職人さんのブランディングサイトを、伊藤さんのご指導のもとで現在運営しています。これまで営業職を何十年もやってきましたが、ウェブマーケティングの実践はここ2年ほどですので、改めて勉強し直したいと考えております。以上です。
伊藤: ありがとうございます。「左官職人さんのブランディングサイト」という点では、N.Tさんと同様に、エンドユーザーと職人さんをマッチングさせるサイトという意味で、サイトのジャンルとしては共通しています。一方、H.Rさんのほうはポータルサイトに近い形式で、遺品整理や不動産売却など、より包括的な情報発信をされる予定です。また、H.Rさんのところでは生成AIを活用してコンテンツを量産していく構想がありますので、その情報も皆さんにとって有益になるかと思います。
伊藤: ではここで、お三方に簡単な質問をさせていただきます。まずはH.Rさん、「ウェブマーケティング」あるいは「マーケティング」にはどんなイメージをお持ちですか?
H.R: 広く浅くやれるイメージがありますね。近いところだけでなく、遠いところにいる人にも情報を届けられるような。すごく広い範囲に見せられるイメージです。
伊藤: なるほど。周辺領域の見込み客も含めて広くリーチできるというメリットがあるということですね。ありがとうございます。続いて、N.Tさんにご質問です。マーケティングをやる上で、どんな作業が必要だと思いますか?
N.T: いろんなサイトがある中で、やはり「信頼性」が最も重要だと感じています。最近では詐欺的なサイトや芸能人を騙ったものなども問題になっていて、やはり閲覧者が「このサイトは安心だ」と感じられるような表現が大事だと思います。以前、私が壁紙スクールをやっていた際に、「なぜこのサイトを選んだのですか?」と聞いたところ、「東京都の助成金を受けた事業であると書いてあったので信頼できると感じた」という答えをいただきました。つまり、信頼性がカギになるのだと思います。
伊藤: ありがとうございます。非常に的を射たご回答だったと思います。良い商品やサービスがあっても、現在はSNSやAIの普及により、膨大な情報が生成される時代です。良いものがあっても、見つけてもらうのが難しいという現実があります。一方で、15年ほど前にはウェルク事件という出来事がありました。簡単に言うと、専門家でない人が書いたまとめサイトがGoogleの検索上位に来てしまうような、検索アルゴリズムの歪みが問題になった出来事です。「Neverまとめ」のようなサイトが当時は検索上位に来ていましたが、後にBANされました。これからAIが加速していく中で、信頼性のない情報が量産される危険もあります。今後、「AIとどう付き合っていくか?」という点も、次回以降の勉強会で扱いたいと思います。
伊藤: ではY.Kさんにご質問です。マーケティングの効果が出るまでには、どれくらいの期間が必要だとお考えですか?
Y.K: 効果ですね。期間的には3ヶ月から半年ぐらいでしょうか。マーケティングの出来が良ければ、そのくらいで「問い合わせがある」とか、「アクセスが増える」、「SNSでのいいね数が伸びる」といった効果が出てくると思います。
伊藤: ありがとうございます。おっしゃる通り、「何をもってゴールとするか?」によって評価も変わってくるかと思います。不動産のように「問い合わせが入ればOK」という場合もあれば、サンプル品やお試し商品の申し込みをゴールとする場合もあります。一方で、本当に売りたい商品というのはなかなか売れなかったりもします。つまり、マーケティング戦略には「短期で成功を狙える施策」と「長期的に仕込む施策」の両方が必要です。このあたりも今後の講義でしっかりお伝えできればと思っています。
マーケティングの基本概念と構成要素を確認
伊藤:それでは、レジュメをご覧ください。まず「マーケテイングとは何か?」という概論部分です。マーケティングの目的は「商品やサービスが売れる仕組みづくり」という事になります。一般的にマーケテイングとは広告と言うイメージがあるけれども、そうではありません。では、マーケティングを構成する要素は何でしょうか?ステップと言っても良いかも知れません。
Y.K:注目を集めて買ってもらう。
H.K:ゴール設定をして始める。
伊藤: なるほど、ありがとうございます。そうですね。それらを包括して順序立てて説明すると……N.Tさん、正解をお願いします。
N.T: まず市場の把握をして、そこにマッチした商品を提供する、ということですか?
伊藤: はい、素晴らしいですね。皆さんの答えをすべて足し合わせると、こんな感じになると思います。まず「調査」、これが非常に大切です。「そもそもニーズはあるのか?」というところですね。それから「ゴール設定」。これはH.Rさんが仰った、「何をもって成功とするか?」という部分です。これらを踏まえて「分析」を行い、そこから商品やサービスが決定される。これが、いわゆるマーケティング思考、マーケットインと呼ばれる考え方ですね。
伊藤: つまり、「この商品があるから売りつけてやろう」という発想は、実はマーケティングとは相反する考え方なんです。だからこそ、この順序が非常に重要になってきます。その後にY.Kさんが仰った「注目を集める」、つまり認知を広げるというステップに繋がるわけです。
伊藤: 先ほども申し上げたように、「マーケティング=広告」ではない、という話もこのマーケットインの流れで理解いただけると思います。
伊藤: ただし、従来は「調査」「分析」「販促」はすべて別々に外注していたケースが多くありました。しかし、ウェブの進化によって、それらすべてを内製化できるようになってきました。つまり、広告を出せばその効果分析のツールも揃っていて、結果を見ながら改善(ブラッシュアップ)もできる、というふうに、すべてがオールインワンで完結する時代になったわけです。
伊藤: ですので、「マーケティング=広告のツール」と考える方もいらっしゃるんですが、実はそれは誤解なんです。なぜそう言い切れるかというと、広告やウェブのルールはおおよそ3年から4年で大きく変化するんですね。
伊藤: つまり、今の時代は「インチキを許さない」方向に進んでいます。先ほどN.Tさんがおっしゃったように、信頼性の高い情報だけが表示される時代になりつつある。ルールが変われば、広告のテクニックだけでは乗り切れない波が来るのです。
伊藤: ですから、広告活用にもデメリットはあります。「お金がなければ広告が打てない」、「広告費が嵩むと利益が出ない」、さらに「広告だけでは信頼は得にくい」ということも近年明らかになってきています。
伊藤: ただし、メリットも当然あって、広告を使えば結果が早く出る。SEOよりも即効性があるため、「短期施策」と「長期施策」をうまく使い分けることで、柔軟な戦略が取れるわけです。また、認知度アップにもつながるという利点があります。
伊藤: 改めて、このセミナーの目的は、新しいマーケティング知識の習得です。ウェブのテクニックに走らず、本質を理解することを目指します。そのために、時間の制限もありますが、できる限り古典的なマーケティング概念を取り上げたいと思っています。
伊藤: たとえば、「マッカーシーの4P」、そして「P.コトラー」などですね。これらについては、動画や書籍も紹介しながら触れていければと思います。
もちろん、ここまでの内容は座学寄りの話になりますが、中心となるのは皆さんの進めているプロジェクトです。
つまり:
・各自の進捗の共有
・課題の洗い出し
・他者からのレビューの受け取り
この3つが本セミナーの核です。座学はこれらを支えるための知識を補うものに過ぎません。
伊藤: また、以前にも個別にお伝えしましたが、「なぜ隔週開催にしたか」という点についても改めてご説明します。確かに、毎週開催すれば知識の定着には良いのですが、「1週間経っても何も進捗がありません」という状況は避けたいのです。
伊藤: 必ず何かしらのアクションを起こし、それに対する結果が出ている状態を、毎回の報告で共有できるようにしていただきたいと思います。ではここまでのご説明で、ご意見やご質問などはございますか?
H.R: 今のところ、特にありません。
N.T: 大丈夫です。
Y.K: 私も大丈夫です。
個々の課題と方向性の明確化
伊藤:それでは、各メンバーの課題の共有をお願いします。
H.R: 買取と不動産のシナジー効果が出ていない、まずはAIを活用して認知を広げたい。
伊藤:買取から不動産に誘導したいのか、それとも不動産から買取に誘導したいのか?
H.R: 遺品整理から不動産につなげたい、すでに不動産が決まっているケースが多い。
Y.K:現状のWEBでは出来ないのか?
H.R: それぞれのWEBは残したまま、入口のポータルサイトを作る。そこから分岐する流れを作りたい。
伊藤:N.Tさん、何かご意見ありますか?遺品整理とか生前贈与の経験がある方を知っているか?
N.T: 知り合いには居ないが遺品整理はかなり需要があると聞いている。関東でも空き家は増えてきている。
伊藤:非常に良いご意見でした、つまりターゲットが本人なのか、それともご家族なのか?そこを明確にして事前調査をしていく。そこで勝敗が分かれる可能性が高い。
H.R:突然当事者になる、予備軍みたいな方に情報を提供していきたい。
伊藤:ありがとうございます。それではN.Tさんこれからはじめるプロジェクトの背景についてお願いします。
N.T: 職人が儲からない仕組みになっている、社会的な問題が背景にある。
N.T: やはり「こだわりを持って、きちんと仕事をしてくれる職人さん」と出会いたいと思っている。たとえば役員宅や施主の自宅の工事など、日々の現場をこなすだけではなく、ユーザー対応も丁寧にできる職人さんを求めています。でも、そういう職人さんに出会う機会がなかなかないし、どこにいるのかも分からない。
N.T: 私の知人の内装工事店さんには、本当にいい仕事をされている方々がいて、その方々を集めたサイトを作ることで、価格以外の価値を評価してくれるお客様と出会ってもらえたらと思っています。
N.T: もちろん、いろいろと課題はあると思いますが、まずはそうした「いい仕事」をしている方々が土俵に上がれるようにして、普段もらっている単価の2倍、3倍を受け取れるような状況になってほしい。そして環境が変わってきたら、「俺もそのサイトに載せてよ」と逆に言ってもらえるような流れができれば、「このサイトにはこういうことができる工事店が掲載されている」という形が作れると思うんです。
N.T: 最近の例ですが、私たちが関わっている内装業界のレベルを少しでも上げ、正当な評価を受けられる環境を整えたい。すぐに成果が出るとは限りませんが、半年〜1年、じっくり取り組みながら、問題点を洗い出していきたいです。
N.T: 例えばホットペッパー、かつては「路面店でなければ飲食店は儲からない」と言われていた時代に、社員が全国のおいしいと評判の店を調査して、飲食店検索サイトに掲載することで、路地裏の名店でも商売が成り立つような状況を作りました。同様に、埋もれている良い工事店さんに日の目が当たる仕組みを作りたい。そのような思いで、現在伊藤さんにサイト制作をお願いしているところです。以上です。
業界事例や比喩を交えた深掘り議論
伊藤: ありがとうございます。非常に理想的な構想ですね。今の話を聞いていて、良くも悪くも「玉石混淆」な業界だと感じました。ビジネスモデルとしては、UberEatsではなくUberの原型に近いですね。アメリカでは、運転手の質が不明でも「とにかく始めてみよう」という思想でスタートしたのがUberでした。
伊藤:一方で、選ばれた人材だけを厳選して紹介するという考え方では、かつてフジテレビで放送されていた**「料理の鉄人」が例として挙げられます。この番組が放送されたことで、大学卒の人たちが料理人を目指すという変化も起きました。つまり、Uber的な大衆モデルと、**カリスマ型ブランディングモデル(料理の鉄人型)**の両方に意味があり、N.Tさんが目指すのは後者に近いのではと感じました。
伊藤: Y.Kさん、今のお話を聞いていかがですか?
Y.K: 正当な評価を受ける世界を作りたいというN.Tさんの理念にはとても共感しました。ただ、職人さんたちがそこにどこまで努力してくれるかは未知数でもあり、だからこそ楽しみでもあるなと思いました。
Y.K: もうひとつ、ハウスメーカーさんが「レベルの高い職人さんと出会いたい」と言うのは、屋根業者さんやサイディング業者さんではあまり聞きませんが、左官屋さんでは何度か言われたことがあります。そこで質問ですが、内装の仕上がりの善し悪しって、一般の人にもわかるものなんでしょうか?
N.T: 実は、ユーザーさんからすると「平らな壁に平らに貼られている」のが当たり前だと認識されています。ですので、「この職人さんはすごいな」と素人が感じることは、そこまで多くないかもしれません。
N.T: ただ、我々プロが見ると「納めが上手い」「仕上げが綺麗」といった部分が分かります。けれども、ユーザーさんには判断しづらい。だからこそ、私は施工前後の振る舞いや態度こそ重要だと思っています。
たとえば:
・契約時の説明の仕方
・養生の丁寧さ
・挨拶、現場での言動
・作業後の片付けや道具の整理整頓
・アフターメンテナンス
といった、技術以前の接遇力や姿勢が評価につながると考えています。
N.T: ですが、職人さんに聞くと、「そんなこと教わったことがない」「見積もりの仕方すら習っていない」「現場で“元気に挨拶しろよ”と言われたぐらい」だと話す人が多くて……。そうした方々が独立しても、そもそも教えられていないから難しいんですよね。だからこそ、明文化されたルールや指針が必要で、それを可視化したいと思っています。
N.T: ある企業の社長さんと話す機会があり、私は内装店の紹介サイトを作ります。ぜひ貴社にも参加していただきたいとお話したところ、その社長さんが最後に言ってくださったのが「このサイトに掲載される工事をするなら、俺たちは恥ずかしくない仕事をしないとな」という言葉でした。これは現場レベルではなかなか言いづらい内容かもしれませんが、**「掲載される工事店としての誇り」**が、社員や協力業者さん全体の意識を変える可能性がある——そう信じて、この活動を進めたいと考えています。
伊藤: 非常に良いご質問でした。先ほどUberを例に出しましたが、日本でのUberは**“失敗”**とされていますよね。理由は「日本のタクシードライバーの質が高いから」。でも本当にそうでしょうか? 最近は減りましたが、タバコ臭い車内や、対応が雑なドライバーに当たることもあります。N.Tさんが注目しているのは、そういった“細部のクオリティ”を気にするお客さんに刺さる世界観なんですよね。つまり、「壁紙の割り付けがズレてても気にならない人」は対象外だけれども、“気になる人”に選ばれる価値を届けたいということだと理解しています。
N.T:Y. K.さん、これ見たことありますか?「ゴールドカード」って書いてありますけど。名古屋のタクシー会社が出しているやつですよね?
Y.K :富士タクシーさん?
N.T: はい、富士タクシーの優良ドライバーにだけ配られるカードですね。
N.T:そうそう。偶然そのタクシーに乗ったときに運転手さんからもらって、大事に財布に入れて持っています。
Y.K: 名古屋では有名ですよ、富士タクシーのゴールド。滅多に見かけませんけどね。
N.T:このカードを持ってるドライバーさんは、それだけ評価されているということですし、乗客にも信頼されてるんだろうなと感じました。ドライバーもこのカードを持つことで、サービス意識が自然と高くなるんじゃないかなと思います。
N.T :平成26年にもらったものなんですけど、今でも財布の中に入れてます。再び出会えたら嬉しいなと……。
伊藤: H.Rさん、今のN.Tさんのお話の中で「一休.comのような」という例が出ました。これ、実は非常に重要です。マーケティング用語ではこうした参考サイトのことを**「ベンチマークサイト」**といいます。 つまり、「目指すべき世界をすでに実現しているお手本のようなサイト」を見つけて、分析対象とするという考え方です。
伊藤: 現時点で結構ですので、H.Rさんが目指したいマーケティングをすでに体現しているようなサイト、ジャンルが異なっていても構いませんが、何か思い当たるものはありますか?
H.R: ……ないです。
伊藤: そうですね。であればこそ、この勉強会での情報共有が非常に大切になってくると思います。一つポイントとしては、「デザインの良さ」だけでなく、そのサイトがどういうターゲット層を想定しているか、また**UI設計(ユーザーインターフェース設計)**にどんな工夫がなされているか、などを見ていけると良いと思います。
H.R: UI設計って……「使い方」みたいなことですよね?
伊藤: そうです。たとえばメニューの配置とか、注目記事の見せ方とか、訪問者が操作しやすくなるための設計全般のことを指します。そのあたりにも興味があれば、後日詳しくお伝えできればと思います。
伊藤: では、Y.Kさん。今取り組んでいること、これから取り組むことの背景についてご説明いただけますか?
Y.K:まず、N.Tさんとよく似ているのが左官のブランディングサイトですね。そちらのほうが今回のウェブ勉強会には合っていると思うので、今回は左官のサイトについてお話させていただきます。
Y.K: このサイトは、5社で3年少し前に立ち上げました。目的は、左官職人さんのブランディングサイトとして、彼らの持つ技術を正当に評価してもらえる環境を作りたいというものでした。
Y.K: 左官業は、基本的に「仕事が勝手に入ってくる業種」と言われています。つまり、特別に営業をしなくても、現場に入ることができる。しかし、これからBtoBではなくCユーザー(コンシューマー)への対応に移行していく中で、どう動けばよいのか分からないという声が多く、そこでを始めました。
Y.K: 本当にやる気のある左官屋さんたちなのですが、「ブログを書きましょう」「写真をアップしましょう」「動画を撮ってコメント付きで投稿しましょう」といった呼びかけに対して、ヤンキー高校の野球部の掛け声のように元気はあるけど、誰も動かない。そんなジレンマがありました。
Y.K: やはり職人さんというのは、困っていてもケツに火がつかないと動かない方が多いのかなと。ただ、今は時代が変わってきて、当たり前だった状況が崩れてきています。
崩れる前に、少しでも自分たちを変えていこう、ということで伊藤さんと一緒に取り組んでいます。
Y.K: 私たちの動きは、確かにタイムラグがあるかもしれませんが、「きちんとやった人たちが正当に評価される世界」をCユーザー対象に作ることを目指しています。以上です。
伊藤: ありがとうございます。左官のサイトは、N.Tさんの構想と同じくD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)型マッチングサイトですね。
一方で、K町の古民家カフェのようなローカルビジネスはH.Rさんの事業と近いジャンルにもなります。ハイブリッドで進められると、より広い視野で戦略が立てられると思います。
伊藤: 内装仕上げの仕事が増える中で、左官の仕事は減少傾向にあります。これは、寿司業界にも似ていると私は感じています。寿司職人の世界では、10年15年と修行してようやく独立できますが、その環境自体が厳しくなってきている。
つまり、超高級店と回転寿司の二極化が進んでいて、「中間層がなくなってきている」のです。
伊藤: 左官業界も同様で、「中間価格帯の仕事がなくなっていく」のではないかと。だからこそ、他業界のマーケティング構造を参考にしながら取り組んでいけるとよいと感じました。
伊藤: では、そろそろ1時間になりますので、ここからはざっくばらんに「こんなことをやってほしい」「こんな進め方が良いんじゃないか」といったご意見をお聞きしたいと思います。N.Tさん、進め方や内容について、ご要望があればお願いします。
N.T: 先日伊藤さんとお話した中で、「用語集」みたいなものを作ろうという案が出ましたが、すでにいろんなメーカーさんが出されている資料があるので、労力の割にメリットが少ないかなと感じています。
N.T: それよりも、私のYouTubeでもたまに取り上げているように、「壁紙がうまく剥がせない」「接着が悪い」といった悩みに答えるような、ヤフー知恵袋的なQ&A形式のコンテンツの方が良いかなと思っています。 その方向で何か構築できたらいいなと考えています。
N.T: また、Y.Kさんのお話を聞いていて思ったのですが、将来的には内装屋さんに限らず、大工さん・左官さん・屋根屋さんといった他職種の方々も含めて、「一休.com」のようなサイトが作れたら素晴らしいなと思いました。
N.T: 結果として「安かろう悪かろう」ではなく、「安心して任せられる」職人さんに出会える仕組みが求められていると思います。いつかそういう方向に進めたらいいですね。
N.T: ちなみに、有名ブランドの内装工事を請け負っているような方にも「ぜひ載ってください」と声をかけたのですが、 「うちは孫請けなので、環境が整っている場所で貼ってるだけ。こだわって仕事してるわけじゃないですよ」と言われたこともあります。
N.T: なので、すべての職人さんを無理に持ち上げることは不可能です。ですが、こだわりを持って仕事をしていて、事業を大きくしていきたい、職人さんを育成したいという方々には、積極的に参加していただきたいと思っています。
N.T: やりたくない人に無理に載ってもらうのではなく、「俺も載りたい」「その方針に共感したから参加したい」と自ら手を挙げてくれる人たちと一緒に進めていきたい。今はそう考えています。
伊藤: Y.Kさんはすでに用語集なども作成されてますし、質問箱のような機能も運用されています。その点も踏まえたうえで、N.Tさんのご意見について、どうお感じになりますか?
Y.K: そうですね。N.Tさんには、ぜひ自分の信じる方向に優先順位をつけて進めていただきたいと思います。それが一番やりがいにもつながると思いますし。
Y.K: ただ、実際のところ質問箱ってなかなか質問が来ないんですよね。だからこそ、質問が来る仕組みを考えなければならない。
私はこの勉強会を通じて、たとえばInstagramでの自動投稿の方法とか、実際に私もInstagram広告を出していて、ある投稿がもうすぐ1000いいねに届きそうなんです。
Y.K: 今、最も利用者が多いのはInstagramだと思います。ですから、集客手段としてInstagramを活用し、質問サイトに誘導する。その流れが重要だと思いました。
Y.K: 私自身、この勉強会ではInstagramの使い方や、テキストの書き方・写真の撮り方などを重点的に学びたいと考えています。以上です。
伊藤: ありがとうございます。おっしゃるとおり、以前は「ウェブコンテンツ= 広告」というシンプルな構成でしたが、今ではSNS+SNS広告+LP+動画+SEOと、いろんな手法を組み合わせていかないと難しくなってきています。
伊藤: 「これ一つやれば成功する」という時代ではなくなってきており、合わせ技で一本取るようなマーケティング構成が必要です。
ブログも書くし、SNSも投稿し、広告も出す。そんな多層的な取り組みが、ようやく成果を生む時代になってきたのだと思います。
伊藤: そうした前提をもとに、皆さんの関心や実行したいことに深く寄り添ってサポートできればと思っています。
伊藤: H.Rさん、 何かご要望などあれば、どうぞお願いします。
H.R: 今回の主な目的として、不動産と買取の一本化を社内で伝えてもらいました。
なかなか一対一では言い切れない部分もあると思うんですよ。「片付けろよ」「もっときれいにしろよ」みたいなことは、たぶん口うるさく言っているつもりではあるんですが、やはり「この会社はあのサイトに載っているんだ」と社員や協力業者さんに思ってもらうことで、意識改善ができるような環境が、少しずつでも作れるのではないかと。そんな期待も込めて、今頑張って取り組んでいるところです。
伊藤: 非常に良いですね。
H.R: 私としてはまず、マーケティングの基礎をきちんと学びたいと思っています。皆さんの取り組みを見ながら学びたいのですが、知識不足を痛感しておりまして、宿題や課題があれば積極的に取り組みたいと考えています。
H.R: それと、今回の不動産や買取とは別に、私が個人的に取り組んでみたいと思っていることがあります。先日伊藤さんにお会いしたときにもお話ししましたが、今、着物が売れない状態で、加紋入りなどもありほぼ仕入れゼロのような状態。大量に捨てられていっている現状があります。
H.R: でも私は、日本の着物って本来すごく良いものだと思っていて、そこにアーティストさんが絵を描いたりして、海外向けに再販していくようなことができないかと考えています。 着物単体では弱いかな……という迷いもあるのですが、実は私、瓦屋の娘でして、内装業や左官業の話にも強く共感しています。
H.R: 最近は買取屋をやりながら、K町に住んでいる大工さんたち——日本の伝統工法(墨付け・手刻み)で作業をする若い大工さんたち——と関わる機会も増えていて、棚やお祭り用のピンボールなどを作ってもらっています。彼らも「大工だけでは食べていけない」と言っていて、小物を作ったり、自分で仕事を取ってきたりしています。
H.R: また、瓦を使ったティッシュケースなどを制作する職人さんもいて、そうした方々と一緒に着物や瓦・木工などの伝統技術を活かした小物を海外向けに販売してみたいと思っています。
H.R: 両方同時にやるのは少し大変かもしれませんが、マーケティングの基礎を学んでいくことで、そちらにも応用できるような力をつけたいと考えています。
H.R: 今日のN.TさんやY.Kさんのお話を聞いていて、「これがうまくいったら本当にすごいことが起こるんじゃないか」と思いながら、ワクワクして聞いていました。
伊藤: ありがとうございます。 そうですね。ウェブの基本原則として、やはり「信頼性と専門性」が非常に重要だと言われています。
伊藤: その意味で言うと、「着物」と「遺品整理」を同じサイトに載せるのは、ややジャンルが異なるので分けた方が良いかもしれません。 遺品整理と生前贈与ですら、テーマが微妙に違ってきますからね。
伊藤: ただ、生成AIという武器がある今の時代なら、まずは下書きの状態で構成をつくって、ミニサイトをコピペで作るような形もありだと思います。 たとえば、「着物専用のミニサイト」をサッと立ち上げてしまうような方法も検討してみてください。
伊藤: では、お時間となりましたので、次回は9月2日開催となります。原則として第1週と第3週の実施を予定していますが、祝日などがある場合は、皆さんのご都合を伺ったうえで調整していきます。
伊藤: なお、「毎回参加が難しい」という方もいると思いますので、ビデオやテキストで記録を残し、後からでも振り返れるようにしたいと考えています。
伊藤: では、次回までの課題をご自身で設定してください。N.Tさんからお願いします。
N.T: はい。前にお話したように、まず顧客の同意が得られている内装店さんを10社以上掲載することを目標としています。そのために説得と掲載許可の取得を進めていきます。
N.T: 先ほど皆さんにご説明した内容をもとに、Excelで必要な項目を入力していただくよう依頼していますので、それを9月2日までにフォローし、あわせて問題点や進捗の共有ができればと思います。以上です。
伊藤: ありがとうございます。では続いて、Y.Kさん、お願いします。
Y.K: はい。次回までの課題として、自分が目指しているのは集客の情報発信だということを再確認しました。現在、Instagramを運用していますが、投稿が止まってしまっています。 また、伊藤さんが運用している左官サイトのSNSに、私がまだコメントをしていないので、まずそれを行います。
Y.K: さらに、レンタルスペースのInstagramにも自分なりに投稿してみて、皆さんからフィードバックをもらいたいと考えています。良い悪いはともかく、まずは動くことから始めます。以上です。
伊藤: ありがとうございます。そうなんですよね。 かつては「広告を出しておけば一定の集客ができた」時代でしたが、今は本体(SNS投稿)を更新していないと、広告だけでは「この会社サボってるな」とお客様に思われてしまいます。だからこそ、全体をまんべんなく運用していくことが大切です。
次回までの課題設定と今後の方針
伊藤: 最後に、次回迄のアクションプランの設定をお願いします。
H.R: はい。まずはベンチマークサイトですね。いろんな業種を見ながら、自分がどんなホームページを作りたいのかを探したいと思います。
伊藤: そうですね、ベンチマークサイトを決めて行きましょう。
H.R: それから……何から勉強したらいいのかがまだ見えていない部分もあるので、もし可能であれば伊藤さんから個別に宿題を出していただけると助かります。頑張って取り組みたいと思います。
伊藤: わかりました。今日の午前中に全10回のカリキュラムをざっくり組みましたので、それに対して必要な準備やステップは個別にお伝えします。
伊藤: おそらく、この1時間だけではとても足りない内容になりますので、補足や深掘りしたいことがあれば、遠慮なくメールや個別アポでご相談ください。
H.R: ありがとうございます。
伊藤: はい、それでは少し時間オーバーしましたが、今回はこれで終了といたします。
全員: どうもありがとうございました。
この記事のまとめ
如何でしたでしょうか?
今回の第1回ウェブ勉強会では、集まった皆さん一人ひとりが、自身の事業や想いを真摯に語る姿がとても印象的でした。「売るため」のマーケティングではなく、「信頼されるため」の仕組みづくり。その本質を改めて考える、貴重な時間になったのではないでしょうか。
“正当に評価されたい職人さんたちの声”、“遺品整理を通じて届けたいご遺族への思いやり”、“古き良き日本の伝統に新たな価値を与える挑戦”——どの取り組みも、情報発信の根底には「人への尊敬と誠意」がありました。
これから始まる10回の学びが、ただのスキル習得ではなく、事業の根幹を支える「軸」となるよう、次回も共に歩んでいければと思います。


