
ECとCMSの違い、各種越境ECのツールを比較したディスカッション
※2024年11月の時点の情報となります。
円安が進む中、多くの中小企業経営者が「外貨を稼ぐ」という新たな挑戦を模索しています。本事例は、買取店とリペア事業を営むH.R氏が越境ECへの参入を検討する過程で浮かび上がった課題と、その解決に向けたディスカッションを記録したものです。障害者協働という独自の価値提案を持ちながらも、プラットフォーム選択や戦略構築に悩む姿は、多くの経営者が直面する現実的な課題を映し出しています。
目次
こんな方に見て欲しい
1. 越境EC参入を検討中の中小企業経営者
国内市場の縮小や円安を背景に、海外販売を検討している経営者。プラットフォーム選択や戦略構築の参考として活用いただけます。
2. 既存事業の海外展開を模索するリペア・リユース業界関係者
中古品やリペア品の海外販売における法的制約や市場性について、実践的な知見を求めている事業者に有用です。
3. 社会的価値と収益性の両立を目指すソーシャルビジネス経営者
障害者雇用などの社会的価値をビジネスモデルに組み込み、それを海外市場でどう活かすかを考えている経営者に参考となります。
1. 相談の背景
H.Rさんは現在、買取店事業でメルカリとヤフオクを活用した販売を行っているが、円安進行により外貨獲得の必要性を感じている。障害者の方々との協働によるリペア事業も手がけており、越境ECへの展開可能性を模索している。一方で、eBayでのクレジットカード申請経験はあるものの、本格的な越境EC参入には知識不足を感じており、具体的な戦略構築を求めている状況にある。
2. 相談の要点整理
事業現状
- 買取店事業をメルカリ・ヤフオクで展開
- 障害者の方々と協働したリペア事業を実施
- eBayでの販売経験あり
課題認識
- 円安進行に伴う外貨獲得の必要性
- 国内市場の将来的な縮小への懸念
- 越境ECに関する知識・経験不足
求めるもの
- 越境EC参入の具体的戦略
- 適切なプラットフォーム選択
- 独自ドメインとモール型の使い分け
3. 問題点の抽出
問題点1:プラットフォーム理解の不足
H.R氏はeBayを越境ECカートとして認識していたが、実際にはオークション・モール系サイトであることを理解していなかった。越境EC用カートシステム(Shopify、LiveCart等)と既存のマーケットプレイス(eBay、Amazon等)の違いや特性を正確に把握できていない状況が見受けられる。
問題点2:商品特性に応じた販売戦略の未整理
現在扱っている商品(ブランド品、リペア品)が独自ドメインとモール型のどちらに適しているかの判断基準が不明確。特に、障害者協働によるリペア事業のブランディング価値を活かした独自ドメイン展開の可能性について、具体的な戦略が構築されていない。
問題点3:法務・物流面の制約への認識不足
越境ECにおける輸出規制、検疫制限、税務処理等の法的制約について十分な理解がない。特に中古衣類などの取り扱い商品に関する各国の輸入規制や、送料を考慮した価格設定戦略についての検討が不十分である。
弊社からのフィードバック
H.R氏の事業には大きな可能性を感じています。障害者協働というユニークなストーリーは、海外市場でも十分に差別化要因となり得ます。まずは商品特性を整理し、モール型での市場テストを行いながら、独自ブランディングを活かした独自ドメイン展開を段階的に進めると良いのではないでしょうか。法務面の制約は事前調査で回避可能ですし、アジア市場の成長を考えると今が参入の好機です。一歩ずつ着実に進めていく事で将来が見えてくる予感がします。

越境ECを始めるべき理由と成功のための基本要素
この項のまとめ
- 日本経済の縮小や円安進行により、外貨を稼ぐ手段として越境ECの重要性が増している
- アジアの中間層が急拡大し、2030年までに世界の中間層消費の57%を占めると試算されている
- 送料はアジア主要都市でも比較的安く、3万円前後の商品なら売れる可能性が高い
- 植物や中古衣類など、国や品目によって輸出制限があるため、事前調査が不可欠
- Shopifyを筆頭に、LiveCartやMagentoなど様々なECカートがあり、用途に応じて選定が必要
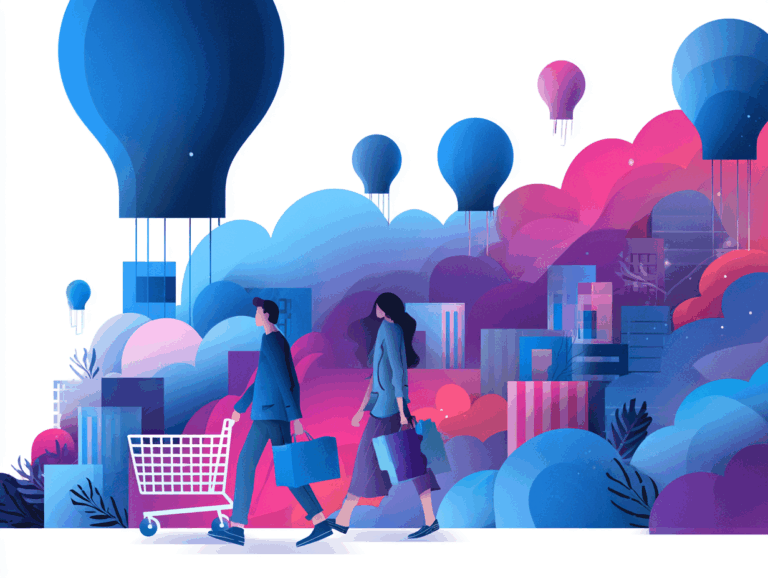
ブログツールとECサイトの違いと使い分け戦略
この項のまとめ
- ブログツール(CMS)はコンテンツ作成・管理が得意で自由度が高いが、決済機能は弱い
- ECサイトは決済や安全性に優れ、月額費用を払うことで運営の安定性が得られる
- SEOやページデザインに優れるCMSとECを組み合わせる「ハイブリッド型」運用も増加中
- モール型は集客力が高く入口商品向き、独自ドメインはブランディングやオリジナル商品に有効
- 商品特性や顧客層に応じて販売チャネルを使い分けることで、越境ECの成功率が高まる
編集後記
如何でしょうか? 本記事では、買取店が越境ECに挑む意義と、その可能性について深掘りしてきました。国内の経済的な制約や円安といった要因を逆手に取り、アジアの中間層市場へアプローチすることは、もはや一部の先進企業だけの選択肢ではありません。むしろ、ストーリー性や社会性を帯びたブランドが、世界中の誰かの心を動かす時代が到来しています。 「安く仕入れて高く売る」だけでは届かない価値──それを届けられるのは、想いや背景を丁寧に編み込んだ商品だけなのかもしれません。リスクを恐れず、小さくても確かな一歩を。未来の顧客は、今ここにいないかもしれませんが、あなたの準備を待っているかもしれません。越境ECという広大な海原へ、風を捉えた航海が始まりますように。

メタ思考のグリアに参加しませんか?
毎月第三火曜日に開催!無料枠はどなたでも参加できます。
[無料枠] 17:00~17:30 [有料枠] 17:30~18:30

講師紹介
株式会社ボンセレ 代表取締役
伊藤 祐介(いとう ゆうすけ)
❖ プロフィール
東京出身の“氷河期世代”。
身長182cm、見た目は大きめ、中身は細かめ。
公務員からスタートし、フレンチレストラン、築地魚河岸、ワインショップなど、業種も業界も超えて現場を経験。のちに広告代理店、EC支援、WEB制作へと軸足を移し、現在は複数企業のWEB戦略を支援。実務と現場視点に根ざした教育者です。
❖ 専門領域
WEBマーケティング/EC戦略立案
コンテンツ企画・制作
広告運用(SNS/検索)
顧客接点の設計とCRM支援
❖ 教育観・講義スタンス
「右腕は、育てることができる」。
人は“経験”だけでは変わりません。
変化するのは、思考のプロセスを鍛えたとき。
私は現場から、企画・広告・制作・接客・分析まで、すべての工程を実践してきました。だからこそ、「考えて動ける右腕」を育てるには、手を動かし、振り返り、問い直す場が必要だと考えています。
❖ 右腕育成にかける思い
「社長の想いを言語化し、現場に翻訳する存在」が右腕です。
単なるWEB人材ではなく、“経営を理解し、支える人材”を育てたい。
ひとつの強みを見つけ、自分にしかできない貢献の形を築く――
それが、このプログラムのゴールです。
❖ 私のルーツ
仮説実験授業(板倉聖宣 提唱)
科学的な思考法とディスカッションベースの学びに影響を受ける。プログラミングとの出会い
高校時代にBasicからスタート。VBAでの業務改善からWEB制作へ。
❖ 好きなこと
食べること・飲むこと・考えること。
最近のブームは激辛料理(ブートジョロキア)。


