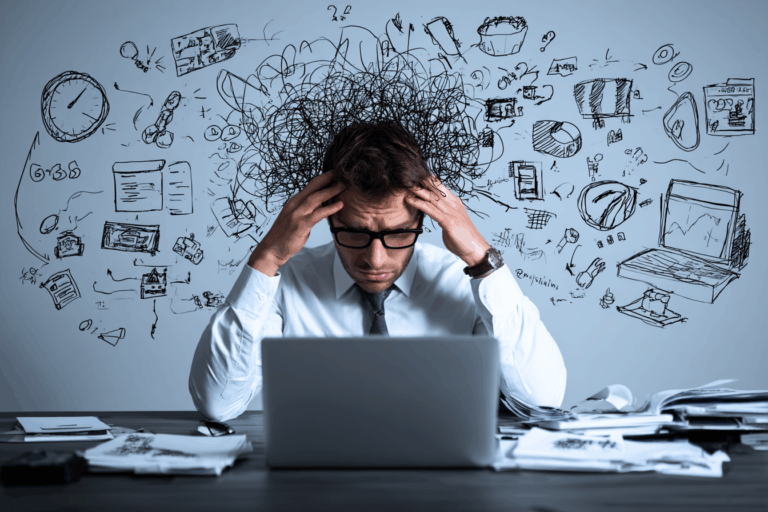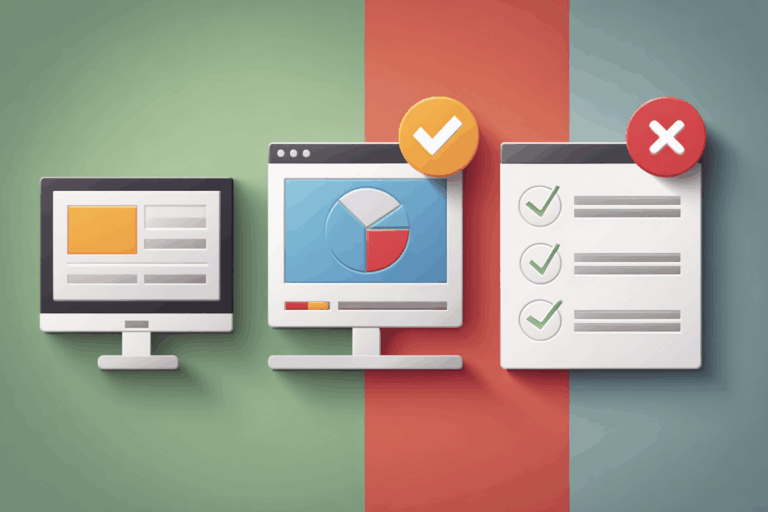伊藤:はい、では本日第2回目ということでですね、前半座学で「Webマーケティングが難解か?」というテーマでの講義ですね。難しく思われがちなんですけども、実は重要なポイントを押さえていれば難しくないですよっていうような内容になります。H.RさんとY.Kさんは1年前も受けていらっしゃるので、記憶の片隅にはあるでしょうし、T.Yさんは普段ECの運営をやられているので、その中で実践されてることもあると思いますけども、抜け漏れであったり、知ってるけど、あんまりやってなかったねっていうところもあると思うので、前半30分は聞き流していただいて、後半のフリートークのところでは、H.RさんとT.Yさんの課題の共有とディスカッションというような形で進めさせていただきます。
伊藤:では早速、Webがなぜ難解だと思われてしまうのかっていうところをお話ししていきたいと思います。画面ご覧になれてますでしょうか。第2回ですね、Webマーケティングはなぜ難解と思われてしまうのかということですね。多くの人が勘違いし間違えてることをいくつか押さえてみました。こんな感じですね。Webをやることの最大のメリットって何だろうっていうこと。それから2つ目は、デメリットもあるよねっていうことですね。Webマーケティングの前提としては1%マーケティングなので、そこに沿った考え方で実践をしていきましょうということになります。4つ目、数値を追う前に、数値ももちろん重要なんですけども、その前に整理しておくことがあるよねっていうことになります。最後が本日のおさらいという形になります。では早速いってみましょう。
伊藤:1つ目ですね、Webの最大のメリットは何かというと、これ問題出せればよかったですね。Y.Kさん、いかがですか。
Y.K:はい、情報の蓄積が1つ目ですけども。
伊藤:どんなことがあるでしょうか。
Y.K:情報蓄積はユーザーの名簿とかユーザーの情報の蓄積だと思いますが、嗜好とかその辺の分類まで来るといったらユーザー情報の蓄積ではないでしょうか。
伊藤:はい、それも1つですね。顧客リストが重要だよねっていうのはWebに限ったことではなく、どんな商売でも一緒なんですけども、意外とそこを忘れがちなので、顧客リストをしっかり貯めていこうねっていうところは、しっかりやったほうがいいかなと思います。そのためのツールとかもいくつかあるので、全10回の中でご案内できればなと思います。2つ目はコンテンツの蓄積ですね。いわゆるブログ記事のようなもので、潜在ニーズから訴求可能なユーザーさんを集めるという方法ですね。それからもう1つが購入者レビューですね。専門品とか家電であったりとか、趣味に近いようなもの、マニアックなものっていうのは、似た属性のユーザーがどういう感想を持っているかっていうところが重要だったりしますね。独自でやろうとするとなかなか難しいので、この辺はモールなんかに任せる場合が多いのかなと思います。あと最近だと、GoogleマップとかGoogleマイビジネスに書き込んでもらうみたいな施策になってくるかなと思います。
伊藤:では、Webの最大のメリット2つ目。これは「商圏の突破」。どんな例があるかというと、EC物販であれば、その商売の商圏、例えば飲食店で言うと半径500メートルって言われてますけれども、そこよりも遠くまでリーチできるということですね。あと、広い意味で言うと情報販売なんかも含まれてくるかなと思います。ローカルから抜け出すのが難しい場合は、情報商材を売るのもひとつの方法と思います。何らかの情報を提供してお金を取るっていう方法も1つあるかなと思います。この勉強会みたいな形でセミナーをやってとか、あとはコンサルみたいな形でお金を取ったり、あるいはフロントエンドですね。フロントエンド商品として利用していくっていう形も取れるかなと思います。
伊藤:では、Webの最大のメリット2つ目。これは「商圏の突破」。どんなものがあるかというと、物販であれば、その商売の商圏、例えば飲食店で言うと半径500メートルって言われてますけれども、そこよりも遠くまでリーチできるということですね。あと、広い意味で言うと情報販売なんかも含まれてくるかなと思います。ローカルから抜け出すのが難しい場合は、情報商材を売るのもひとつの方法と思います。何らかの情報を提供してお金を取るっていう方法も1つあるかなと思います。この勉強会みたいな形でセミナーをやってとか、あとはコンサルみたいな形でお金を取ったり、あるいはフロントエンドですね。フロントエンド商品として利用していくっていう形も取れるかなと思います。
伊藤:ここまでで何かご質問とかご意見などあればお願いします。T.Yさんいかがですか。
T.Y:OKです。
伊藤:では続いていきましょう。反対にWebのデメリットというものもあります。これがすごい厄介なんですよね。検索ニーズを事前に把握するのが結構難しいんですね。これは担当者に対しても言えますし、新しいサービスや商品を売っていくって時に、検索のニーズを把握した状態で始めることっていうのはなかなか難しかったりするんですね。重要なポイントがあって、1つはクリックされる前、もう1つはクリックされた後ですね。皆さん、ページのデザインを良くしたら売れるんじゃないか、みたいなことをよく初心者の方はおっしゃるんですけども、実は素敵なページを作っても、クリックして見ていただけなければ何の意味もないんだよねっていうことなんですね。
伊藤:皆さん、GA4はすごく大好きみたいでよく見てくれるんですけども、サーチコンソールは結構敬遠されがちなんですね。でも実は、経営の指標でいうと、BSに近いものがサーチコンソールにあたるので、ここの戦略をしっかり立てるっていうことが重要であります。イコール、キーワード対策という事になる。それからですね、ニーズの違いがなかなか理解できない場合があります。ニーズの違いというのは2種類ですね。顕在ニーズと潜在ニーズと言われるものです。顕在ニーズというのはどんなものがあるか。既に欲しい商品やサービスということですね。具体的に言うと、ユーザーはもうAという商品を買うことが決まっているという前提になります。この場合にユーザーの行動はどうなるかというと、ショップAでもショップBでも扱っている商品であって、どちらの店で買おうかなっていうのが、顕在ニーズと言われています。最短で今すぐ客を取り込むというのが、WEBマーケティングの一丁目一番地なんですね。すぐにやるべきことになります。ただ、ここは見落としがちな部分なんですね、皆さん。一方で、ここだけで勝負をやっていくと、値下げ合戦に巻き込まれていくので、これもしっかりやりながら、違うものもお客さんに提供しようねっていうところで、二つ目は、潜在ニーズを掘り起こしましょうということですね。
伊藤:実は、潜在ニーズには、二つあってまだ知らない商品、あるいは知っているけど、過去に買ったことがないという商品。それから、そういう商品カテゴリがもともとなかったっていう場合もあります。で、買ったことがないので、商品AとBの違いが分からない状態ですね。まあ、そういうお客さんに関しては少し時間がかかるので、長期施策として分類をします。で、こういうお客さんに対しては、どういう施策が取れるでしょうか。Y.Kさん、どういう施策がありそうですか。
Y.K:定期的に公式LINEに登録していただいて、定期的に忘れられないように情報を一方通行でもいいから提供するということでしょうか。
伊藤:そうですね。LINEとかSNS、あるいは古い方法だとメールマガジンなんかもありますけれども、そういったもので定期的に情報を配信して、ユーザーの理解を深めていくということが必要になってきます。では次ですね。潜在ニーズの2つ目。その人にとって全く新しい商品である場合は、まだまだ客になるので、ここは認知の段階にあるお客さんなので、おそらくこの段階だとメールマガジンとかSNSのフォローというのは、なかなかハードルが高いんですけれども、こういうお客さんに対しても定期的に、例えばディスプレイ広告みたいなもので認知を高めていくという施策の対応が求められています。
伊藤:さて、Webのデメリット3つ目ですね。ランニングコストの高騰というのが挙げられると思います。もともとリアルの店舗と比べると、Webマーケティングはイニシャルコストが非常に安いんですけれども、その分ランニングコストは高いと言われてきました。具体的に上がってきたのが制作費、それから広告費ですね。制作費自体はですね、Web業界バブルみたいなところがあって、根拠のない販売価格の高騰というのがかなりあるかなと思います。なので、しっかりしたサービスを提供している会社なのかというところの見極めが非常に重要になってくると。どうしても見た目で選びがちなんですけど、しっかり機能面をチェックしておいてねっていうことですね。具体的に言うとですね、半年ぐらい前にご相談があったのが、ある会社に、リニューアルを頼んだらしいんですけど、URLが変わってしまいますっていうお話だったんですね。それで私が調査した結果、変わらないでコンテンツを維持できる方法が見つかった。なのでよかったなと思うんですけれども、WordPressのテーマとか、あるいはShopifyのテーマによってはですね、テーマを変えることでURLが全く変わってしまうっていうことが起きたりするんですね。なので、事前にテーマやシステムを購入決定する際には、専門家にチェックをしていただいた方がより安心なのかなと思います。URLが変わってしまうということは、Webにおいては、死と同じ、価値がゼロになってしまうので、ゼロになってしまわないような仕組みを選んでいきましょうということになります。
伊藤:それから広告費ですね。クリック単価というのは年々上がってきています。15年前、私がこの業界に入った頃は、ワンクリック50円ぐらいが当たり前だったんですが、もちろんジャンルによって違うんですけども、クリック単価10倍ぐらいになってるなっていうのは感覚としてあります。それから広告単価だけではなくて、外注する際の契約費用も結構上がってきているので、この辺りはやりながらですね、なるべく内製化していく方向にいってるのかなというふうに思います。
伊藤:では、こうしたWebマーケティング費の価格高騰に対して対策があるとすれば何と何でしょうか。基本の2つ、わかる方いらっしゃいますか。
T.Y:2つですか。1つオーガニックですか。
伊藤:ああ、なるほど。オーガニック流入を増やす。
Y.K:内製化ではないでしょうか。
Y.K:広告費をかけないコンテンツ。ブログですとかの定期的な、月1ブログアップみたいなことで、ちゃんと活動してるサイトだということをSEOで認識させる。
Y.K:ちょっと焦点ぼけましたか、伊藤さん。
伊藤:ぼけてはいないですけど、T.Yさんと同じ内容なので。
伊藤:H.Rさんわかりますか。
H.R:同じことが一つは思い浮かんでたんですけど、もう一つはわからないです。
T.Y:SNSから流入ですかね。
伊藤:それも一つですけど、ランニングコストの高騰に対しての対策ということで、今言われたオーガニックとSNSというのは別の話で、今は広告の話になるんですけど、この要素を挙げてみました。CPAとLTVを上げましょうねっていうこと。これを改善していくんですね。CPAというのはこれですね。コストパーアクション。顧客の獲得単価をどう下げるかっていうことなので、そういう意味ではクリック単価を下げるという事、まあオーガニックを増やしましょうというのと、SNSでも流入を増やしましょうねっていうのも、間接的なCPAの改善に含めても良いかな。
伊藤:それからLTV。Lifetime Valueの略ですけれども、結局何が起きてるかっていうと、お客の奪い合いが起きてるんですね。なのでお客さんの奪い合いにお金を使わずに、一人来たお客さんをなるべく長い時間再利用してもらって利益を残しましょうねっていう戦術になってくるかなと思います。それから対策の2つ目としては、Webではないんですけど、実店舗のサービスがある場合はですね、なるべくそこに呼び込んでファン化をするっていうことですね。Web上だけでお客さんを取り合っていくと価格競争になるし、お客さんは価格でしか訴求されていかないので、なかなかファンになっていかないんですよね。なので可能であれば定期的にイベントを開催して、対面で接客することで自社の価値を高めていくっていうのも一つ、戦略としては非常に重要かなと思います。特にですね、ネットショップしかやってないような企業って割とあって、そういうところってイベント力弱いんですよね。なので実店舗の既にある機能を活かしていくっていうのも戦術の一つかなというふうに思います。
伊藤:はい、では次まいります。「1%マーケティングを理解しよう」ということですね。ちょっと絵を見せます。こんな感じですね。対照的な広告になります。左側はNIKEのエアマックスですね。右側は近所のダイエットサポートしますみたいな広告になります。皆さん大体左側なんですよね。こういうのをやりたがるんですけど、こういうのをやると効果がないわけじゃないんですけど、めっちゃ時間とお金がかかるよねってことなんですね。最初にお勧めするのはやはり右側のほうを主体にしていく方が良い、これどっちが、という二元論じゃなくてウェイト付けの問題であったりするんですけど、最初にやるべきは右側なんですね。近所の八百屋さんとかラーメン屋さんが手書きで書いたような文字がみっちり書いたもののほうが、実は売上に直結することが多いんですね。これ広告の話なんですけど、これはコンテンツも同じになります。
伊藤:これらは、イメージ型広告とレスポンス型広告という分類になります。イメージ広告は何かというと、メリットがあります。認知を広げるには非常にいいよと言われてるんですけども、デメリットとしては長期間かかります。長期間、認知を広げていった先にようやく商品が売れるよねってことです。いわゆるテレビ広告みたいなイメージだと思います。テレビ広告は具体的に商品を紹介する場合もあれば、企業イメージを売るような広告もあると思います。そちらのほうが多いかなと思います。イメージで商品を売っていきましょうねっていうのは、どちらかというとオールドメディアのスタイルになると思います。反対にレスポンス型広告だと、メリットはこんな感じですね。すぐに商品が売れる。反対に短期策なんですね、レスポンス型の広告というのは。ずっとやってるとブランディングできないし、基本的には押し売りなので嫌われていくよってことですね。なので最初はレスポンス型で凌ぎながら、徐々にイメージ広告のウェイトを増やしていきましょうというのが、一般的な手順になります。
伊藤:1%マーケティングは元々、アメリカから始まっています。100人に利用して全員に好かれる必要はないんですね。1人しか買わなくてもOKというのが、元々のWebの戦略的な販売方法になります。顧客リストがあれば打率低くても売上があがるよねっていうことですね。先ほどY.Kさんが言われたように、繰り返しアプローチでゴリ押しして、商品を売っていくというのが基本になります。なので、ここに対するアレルギーというのが社内にあると、あんまりWebマーケティングが成功しない可能性があるんですね。初期はどうしてもやっぱり押し売りになってきてしまう、イメージ広告だけでは企業体力持たないんですね。なのでこのあたり、担当者の理解と社内の理解というのを作っておく必要があるかなと思います。
伊藤:次いきます。コンテンツ属性の違いですね。コンテンツの使い分けるということになります。こういう言い方はあまり一般的では無いんですけど、僕がお伝えしているのは、コンテンツの種類には2種類あるという事。それは「きっかけコンテンツ」と「説得コンテンツ」になります。きっかけがなぜ必要かというと、良い商品やサービスを作るよりも、知ってもらうことのほうが難しい時代になってですね。1日の情報量というのは、こんなふうになってますね。現代の1日分は江戸時代の1年分であり、平安時代の一生分であると言われてるんですね。なので情報量がバーッと増加してしまった結果、知ってもらうためのコンテンツを作る必要が出てしまった。どんな媒体があるかというと、広告、SNSなんかがありますね。広告についてはこの後の回で詳しくまたお伝えできればと思います。SNSはいろいろメリットがあるんですけども、拡散性が強いというメリットがありますけれども、ストックできないというデメリットもあるので、このあたりもバランスが必要かなと思います。オールドメディアも、こんな感じですね。衰退していってますけれども、新聞の折り込み広告なんかはローカルの環境では、まだまだ有効な場合もあるかなと思います。
伊藤:説得コンテンツに参ります。情報自体が具体的で、ユーザーメリットがあるというコンテンツを作っていきましょう。押し売りではなくて、お客さんが役に立つ情報を書きましょうねということですね。とはいえですね、売るための嫌われる勇気も必要ですね。1%マーケティングをベースに執筆をしていきましょう。先ほどもありましたように、本当に怖いのは嫌われることではなくて、存在自体を忘れられてしまうことですね。あとは、バシバシメルマガ等を送ってもですね、ブロックしないお客さんをベースに初期は考えていきましょう。全員に好かれようとすると何もできないねということになってしまうからですね。どんなツールがあるかというと、DMであったり、ブログを中心にしていきましょうということになります。
伊藤:最後になりますね。「平均の1%に騙されるな」ということで、ロングテールという概念があります。ロングテールとは何だったでしょうか。Y.Kさんお願いします。
Y.K:ロングテールは、ベルをイメージしてもらうと思うんですが、やっぱり平均値のところが一番高くて、細く長く右・左のほうに続いてる。需要は低いけど長く続くことをロングテールだと思いますが。
伊藤:ベルカーブではなく片側ですね。ECの売り上げもキーワードも同じなんですね。たくさん売れるものってやっぱり競合が多いわけです。たくさん売れるけどもあんまり儲からないね、という世界。逆にロングテールのほうはニッチ。マニアックな商材であったりマニアックな情報なんですけども、競合が少ないので、お客さんニーズが非常に高いんですね。ネットならではの考え方ですけども、ショートヘッドとロングテールをバランスよく組み合わせることで、売り上げと利益を担保する。ショートヘッドだけだと儲からないんですけど、ショートヘッドを作ると認知が広がるので、結果的にこの長い尻尾ができるようになる。ショートヘッドが小さいと尻尾も短くなってしまうので、店舗の売上やアクセス数をゴジラのように考えていただいて、大きいゴジラをどうやったら作れるかなというところを考えていただけるといいかなと思います。
伊藤:それから、数値を見る前に必要なことというのがあります。Web施策には全て数値化されますけども、その前に確認しておく要素がありますね。数値の良し悪しを論じる前に、以下のことを事前に調べておいてください。つまり、有効な施策さえしっかりすれば物が売れるんだという考え方だと、ちょっと危険な考え方になる。つまりカテゴリーや商売の属性によって、商流というものが必ずあるわけです。商流を変えられるサービス、ビジネスであれば、ネットでやるとハマるよねということですね。具体的には、アパレルとかコスメとか、一般的な小売業というのは、中間マージンをカットできるので、商流を変えられるよねということになるんですね。反対に、商流の変えられないサービスであると、Webでどんなに頑張っても、ビジネスに繋がりにくいということですね。例としては、薬事法の問題がある医薬品。もう一つが、設備とかだと、工事とデリバリーの問題があるので、ネットだけでは解決しないよね、ということになってくるわけですね。商流を必ずチェックしましょうということになります。
伊藤:それから、コンテンツを作る前に、チェックすべきことですね。どうしてもですね、自分たちが言いたいことをメインにしてしまう場合が多いんですね。でもその前に、お客さんが知りたいことを用意した上で、我々が言いたいことをそこに乗せて伝えていくということが重要です。それができているかというのを定期的にチェックされたほうがいいかなと思います。パーセンテージで言うと、言いたいことというのはだいたい1割ぐらいにしておいてください。それから、E-E-A-Tを満たしているかということも非常に重要になってきます。E-A-T、H.Rさん覚えてますか。
H.R:価値のある情報とかみたいなやつでしたっけ。
伊藤:Y.Kさん、分かりますか。
H.R:専門性ですとか信頼性ですとかの、頭文字を取ったものだと思いますけれども。
伊藤:そうですね。もともとE-A-Tと言われてたんですね。専門性、信頼性、権威性と言われていました。そこに現在では、エクスペリエンスですね。自身の専門家としての経験を伝えなさいと言われています。つまり自分が何者で何の専門家なのかっていうところを、Web上では非常に評価されてるっていうことですね。たとえば僕がスイーツの記事を書いたとしても、スイーツ専門外なんで、それはあまり評価されないよねっていうふうになってきてるということですね。なのでご自身のコアなサービスの部分をしっかり発信していきましょうということになります。
伊藤:それからもう一つの要素が、YMYL になります。Y.Kさん何の略でしたでしょうか。
Y.K:Your Money, Your Lifeで、ユーザーさんは自分のお金のことと自分の生活のことしか興味がないっていうことを、YMYL というふうに言うのではなかったかなと思いますが、いかがでしょうか。
伊藤:それはそうなんですけど、誰にとってもそうだと思いますけど、Googleの評価として、ユーザーのお金や生活に役立つ情報をWebで出しなさいっていうことなんですね。なので、インチキな情報はBANしますっていうふうに、ざっくりした言い方だと当てはまるかと思います。
伊藤:30分以内に終わろうと思うんですけど、なかなか終われないですね。ここ、重要な点ですが、デザインの価値は5%程度と言われていて、テキストで如何にストーリーを伝えていくかっていうのが実は非常に重要なんですね。嫌われる勇気を持って初期は押し売りしてくださいということですね。それからWeb戦略をきちんと整理しましょうねということで、ロングテール理論というもの、あとはストックとフローですね。SNSは瞬間風速強いけども流れていってしまう。反対にブログというのは非常に地味で成長が遅いですけども、ストックできるので、将来的には大きな力になってくれるということですね。なのでバランス、今どのフェーズに自分達がいるのかという整理が必要になってくると思います。長期と短期できちんと整理しながら進めていってください。
伊藤:長期策はブログ、説得コンテンツであり、SEOが効けば「きっかけコンテンツ」にもなるということですね。短期でやると広告とかSNSだけになるけれども、広告においては特にそのままもちろんコンバージョンに繋がればいいですけど、難しい場合は、テストマーケティングとしては非常に有効なので、そういう使い方もしてみてください。
伊藤:あとはSNS。最初は優先度低いのでちょいちょいでいいと思います。フォロワーがたまってくれば少し意味が出てくると思いますけど、あんまり最初は一生懸命やらなくていいかなと思います。
伊藤:AIで機能が生成できる時代、この1年でだいぶなってきました。なので、よりリアルで何かをやるということが、ウェイトが上がってくるかなというふうに思います。そのための企画や課題整理も、この勉強会でやっていけたらなというふうに考えています。
伊藤:本日ご用意したのは以上ですが、皆さんからご感想や質問があればお願いします。T.Yさんいかがですか。
T.Y:ウェブと実店舗の考え方の違いのところで、実店舗でいくとA or Bみたいな、施策がどうしてもクローズドになっちゃいがちなところがあると思うんですけど、ウェブでいうとA and Bみたいな話があると思うんですよね。その辺りを解説もらいたいなと思いました。
伊藤:そうですね。今までの実店舗の考え方であったりとか、オールドメディアの考え方だと、やっぱりどんどん絞っていくんですね。つまり絞っていくことで、商売の効率が良くなるんです。
伊藤:例えば店舗でいうと、ディスプレイって無限に飾れるわけじゃないんですね。棚の面積って決まってるので、競合を排除していかに棚を取りにいくかみたいなことは、問屋さんとかメーカーさんも常に考えているんですね。
伊藤:ただウェブの場合何が違うかっていうと、ディスプレイする必要がないんですね。バックヤードに全部箱詰めて置いて、売れたら用意するっていう感覚なんですね。この感覚がリアルの生活の中でなかなか身につかないんですね。
伊藤:どっちかにしよう、どっちが売れるかっていうことをどうしても考えてしまうんですね。両方やるのはめんどくさいなって思っちゃうんですけども、WEBの場合はそうではないですね。
伊藤:ネット商売の場合はまず一旦出してみる。ミニマムで出してみる。ミニマムの情報量、最小の作業量でまず出してみるっていうことが非常に重要なんですね。それでデータが取れる事がある。
伊藤:ウェブとかのEC運営しててよくあることは、実はAのほうが売れると思って情報集めてページを作り込んできたけども、手軽にやったらBのほうが売れちゃったみたいなことが結構あるんですね。
伊藤:WEBの場合はなんで、それが売れたかっていうところも全部数値化されていくので、まずはライトに出してみるっていうところをぜひ身につけていただきたいというのと、そこにプラスアルファで無料でできる施策っていうのが実はウェブにはいっぱいあるんです。
伊藤:無料でできる施策をすべてやり切るっていう、それによって担当者だったりチームに実力がついてくるので、必ずAかBかじゃなくてAもBもやり、セットで無料の施策をすべてやるっていう習慣をつけていただくと、非常にいいかなというふうに思います。
伊藤:T.Yさん質問の答えになっていたでしょうか。
T.Y:ありがとうございます。なってます。
伊藤:Y.Kさんいかがでしょうか。
Y.K:SEOとかどうやってウェブマーケティングをやっていくかということの中で、伊藤さんが15年間の経験の中でマインドマップで説明していただきありがとうございます。
Y.K:基本的にウェブマーケティングのやり方がSEOを基準にされているのと、あと最近AIがだいぶ検索で使われるようになってきたと思うんですが、このウェブマーケティングのやり方は、AI対策にも当然使えると思うんですが、そのへんのご見解を聞かせてください。
伊藤:そうですね。他の会議とかでもちょっとお話をさせていただいたんですけど、基本的にはあんまり変わらないかなっていうのが僕の見解になります。
伊藤:ただ、使い方の違いというのがあって、より詳しく文章を読み込んで理解をしようっていうのが検索のほうになると思うんですけど、AIのほうは、それのショートカットなんですね。
伊藤:別の会議でもお伝えしたのは、ショートカットとして一番最適なのは何だろうねってなったときに、動画なんですよね。ダイジェスト版の要約した動画みたいなものを作成してページに配置していくと、SEOからも入るし、AIOからも入るよねっていうところになってくるかなと思います。
伊藤:つまりAIとはショートカットであるっていうところを前提にアクションを起こしていくと、あんまりブレないかなというふうに考えています。
Y.K:はいどうもありがとうございます。ショートカットね。より早く情報にたどり着きたいっていう、それのショートカットもあるだろうし、簡単でいいやっていうショートカットもあるだろうし。ありがとうございます。
伊藤:はい、H.Rさんいかがですか。
H.R:今日の講義を受けていて、私が一番心に残ったのが嫌われる勇気を持ちましょうっていうところで、以前同じような講義を聞いたときにもそう思ったんですけど、SNSとかは結構怖くないので、毎日ぐらい投稿とかでできるんですけど、公式LINEってなると、どこまでやっていいものかっていうふうに思って、アレルギーがまだあるんですが、LINEやチラシとかの媒体でいくと、どのぐらいやったら嫌われるんでしょうか。どのぐらいやっても大丈夫なのかなと思って聞いていました。
伊藤:サービスのジャンルとかポジショニングにもよるとは思うんですけれども、週1回ぐらいだったら問題ないのかなっていうところがあります。
伊藤:実は同じようなことを飲食店のサービスマンに対しても言われてるんですね。つまり、テーブルについて接客する機会は少なければ少ないほうがいい。なので所作や技術を磨いて、接客の頻度を減らしなさいっていうふうに、20年前までは言われていたんですね。
伊藤:でも今その考え、僕の中にないんですね。つまり、面白いネタがあれば、お客さんと何回接してもいいじゃんっていうふうに考えてるんですね。
伊藤:先ほどのYMYLと同じような観点ですけども、お客さんに役立ったりとか、お客さんが面白いと思ってもらったら、僕は何回接客してもいいと思います。
伊藤:なので最低限、月に3回とか4回とか配信しながら、いかに面白い情報を出せるか、いかに役に立つ情報を出せるか、っていうところに注力するといいかなと思います。
H.R:はい。ありがとうございます。
伊藤:ただ一個気をつけていったほうがいいのは、配信者と実店舗のスタッフで情報が共有されてなくて、お客さんに何か言われたときに全く対応できないっていうのが、僕の経験としてあったので、そのあたりはスタッフの情報やりとりを密にしておくといいかなと思います。
H.R:はい。ありがとうございます。
伊藤:はい。では前半の部分が終了になりますので、このまま後半に移りたいんですけれども、T.YさんとH.Rさん、どちらが先行きますか?
[有料会員限定]見逃し配信を見る
今回の記事の配信データを有料会員様限定で公開中。繰り返し視聴する事でWEBマーケティングの力が身に付きます。
会員限定コンテンツ
ご覧になるには
メンバー登録が必要です。
オンラインサロン
「メタ思考のグリア」とは?
![[2025] Is marketing difficult? Online study session to understand the essence [2nd report]](https://bon-selle.co.jp/set_in_wdl/wp-content/uploads/2025/06/2025-Is-marketing-difficult-Online-study-session-to-understand-the-essence-2nd-report.jpg)