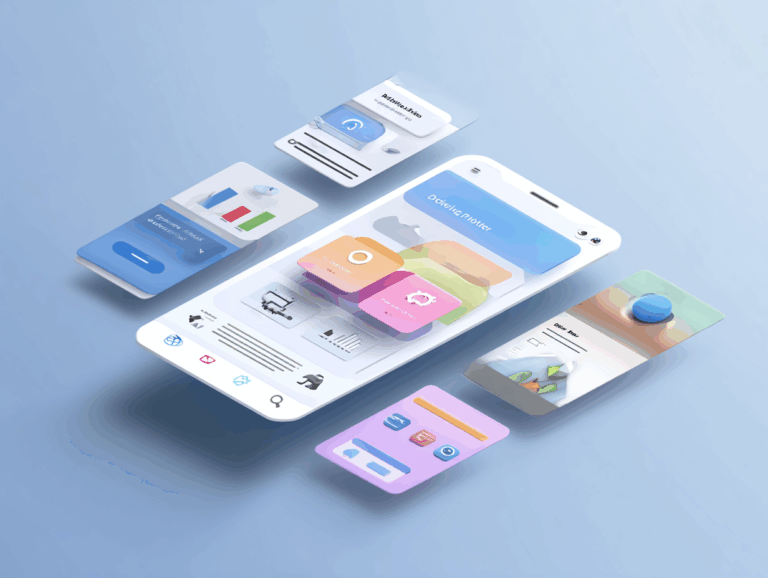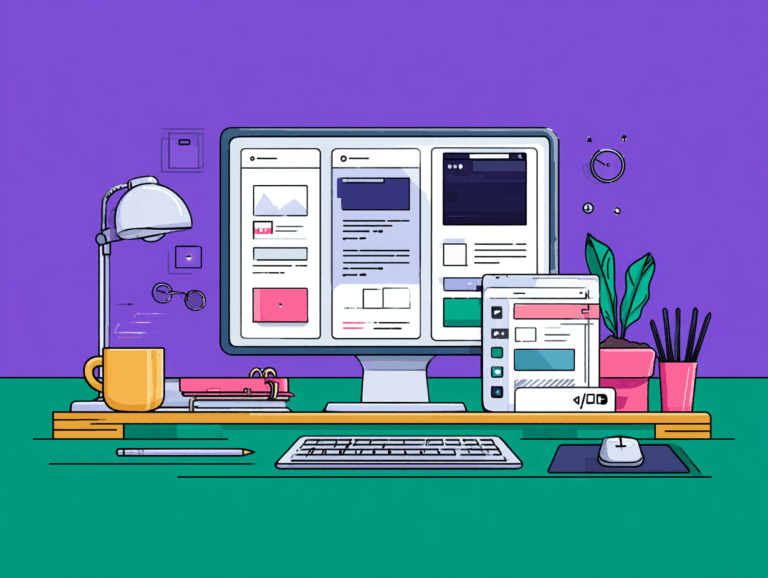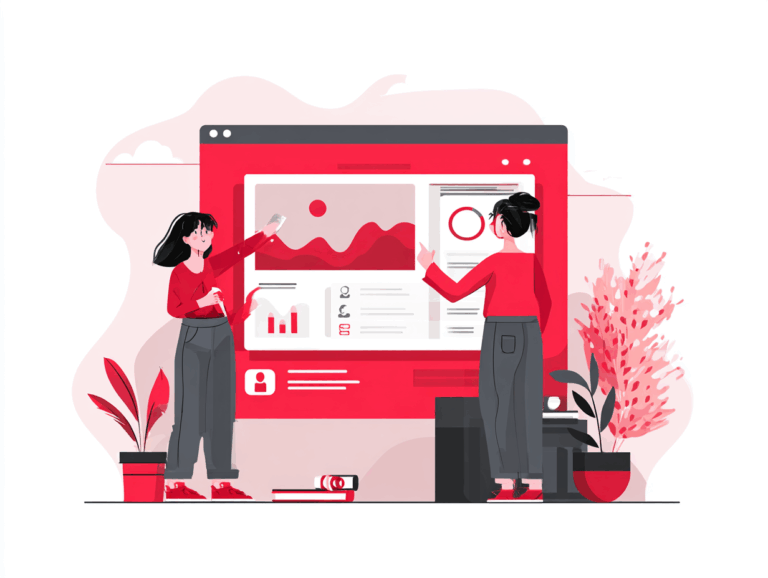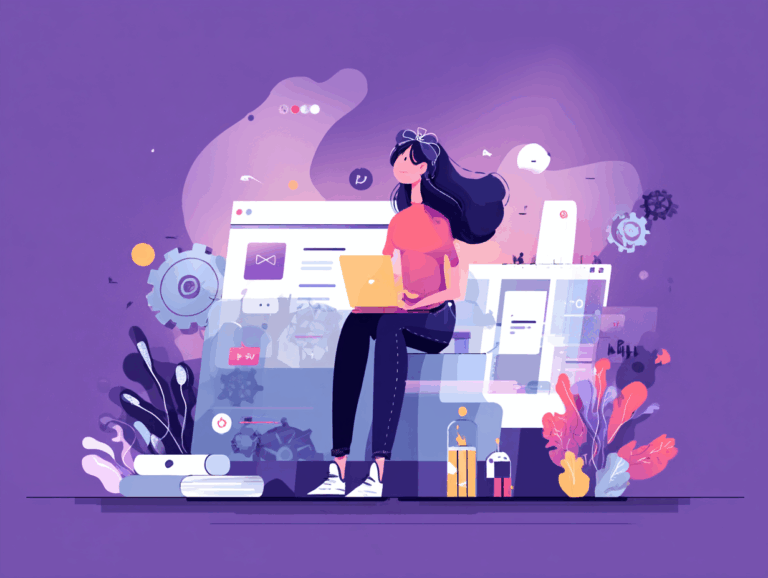LPに向く商品の選び方と効果的な構成法
伊藤:では続いてまいります。3番目ですね。商品の属性を把握しましょうということです。LPに向いている商品と向いていない商品があるんですね。なので、LPをどんどん作り込んで、一生懸命売ってやろうという気持ちは素晴らしいと思うんですけど、果たしてフィットしているかっていうところも確認が必要ということになります。
伊藤:我々いつも悩みがあるんですけども、自分たちが本当に売りたい商品っていきなりは売れないんですよね。つまりこういうことになります。本当に売りたい商品はバックエンド商品というふうに言われたりしています。反対に気軽に買ってもらえるよねっていう入り口、ハードルが低い商品のことをフロントエンド商品と言ったりします。
伊藤:バックエンド商品ってどんな属性があるかというと、そもそも価格が高かったりとか、売るのに説明が必要だったりとか。3000円以上のものって一般的にはネットでは衝動買いしてくれないので、じっくり売っていかないといけないですね。
伊藤:では、フロントエンド商品というのはどういうものかということですね。説明が不要で価格も安いということで。もっと言うと、商品を最初から売るのはやめたほうがいい場合があるんですね。つまり、見込み客を集めることに集中したほうがいい場合があります。
伊藤:例で言うと、サンプル品を配ったりとか、お試しセットを配ったりとかですね。あるいはホワイトペーパー、例えば3ヶ月で5キロ痩せる筋トレの方法をお送りしますみたいな。ホワイトペーパーと言われるものですね。ノウハウを情報として届けますよということですね。
伊藤:その代わり、メルマガ登録が必要になりますという形で、顧客リストを溜めていくという戦略を取る場合があります。最近だとメルマガでなくて、SNSに登録させるという方法もあったりするかなと思います。SNSでフォローしてもらって、特定のアカウントにDMでメッセージしてもらうと、何かしらの資料を渡しますよみたいなことをやる場合が多いです。
伊藤:なので、もしLPでバックエンドの商品を載せて売れない場合は、すぐにフロントエンド商品、入り口の商品に切り替えて広告を運用していくといいかなというふうに思います。
伊藤:続いてまいります。では、LPに何を書くべきかというところが、わりと僕もご質問いただく内容かなと思います。非常に古典的なんですけども、PASONAという記述の方法があってですね、そこに一旦乗っかって書いていくといいかなというふうに思います。
伊藤:PASONA、頭文字の略ですね。問題を提起して親近感を生み、そして解決策を提案し、それから絞り込みを行った後にアクションを起こさせるということになります。
伊藤:表現としてどんな内容かというとこんな感じですね。皆さん何々感じたことはありますか?例えば、通勤時間って無駄な時間だなと思うことありませんか?みたいな感じで英語の教材を売ったりとかですね。そんな感じですね。
伊藤:親近感ですね。かつて何回もチャレンジしたけども、私も失敗してきました。というところがですね、これまで全くなかった新しい方法が見つかりました。それをご紹介しますということですね。
伊藤:提案ですね。今買えばこういった生活が誰でも手に入れることができる。と、さんざん盛り上げといて一旦落とすんですね。あえて限定します。すべての人にオススメですっていうオファーはあんまり良くないとされているんですね。ただし、こういう人には絶対オススメできませんので。
伊藤:そうするとですね、見たユーザーはこれ私のための商品だっていうふうに感じて、より購入の確率が高まると言われています。
伊藤:それからアクションですね。先ほど言った、単価が安いものであれば購入につなげたり、あるいはホワイトペーパーを渡しますよ。それからSNS、それから最近多いのはオンラインセミナーに参加しませんか?みたいな形でコンバージョンさせるという手法が増えてきました。
伊藤:こんな構成で書くといいよっていうところなんですけど、別の軸で抜け漏れがないかどうかっていうところはチェックしたほうがいいかなと思います。これご自身で作る場合もそうなんですけども、外部に委託した場合もですね、結構抜け漏れがあったりするんで、これちょっとどうなのかなっていうのをチェックするためのリストをご用意しています。
伊藤:ブランドサイトのコンテンツという記述なんです。基本的にはこれ、LPもこの構成で考えていくといいかなと思います。一番重要なのは必要性と優位性ですね。つまりあなたの生活がガラッと変わるんですよっていうことをきちんと伝えた上で、なぜこの会社なのか、なぜ我々のサービスなのかっていうところを伝える必要がある。
伊藤:そのエビデンスとして信頼感であったり安心感っていうところを、ページの後半で伝えていくと良いとされています。わりと機能の説明とかばっかりしてしまってですね、なかなか感情に刺さらないようなLPだと失敗してしまうケースが多いですね。
伊藤:一番重要なのはやはり、ベネフィットの部分ですね。つまり性能とかメリットっていうのは、お客さんにとっては必要な情報なんですけれども、それだけでは十分ではないんですね。つまり生活とか人生とか、心の状態がどう変わるのかっていうところを、比較的ページの上のほうで十分に伝えていく必要があるわけです。
伊藤:それから重要な要素3つ目ですね。ファーストビューにこだわろうということです。ファーストビューというのは、ユーザーがそのページにアクセスしたときに最初に表示される部分になります。構成としてはメインのビジュアルと、それからキャッチコピーという構成になります。
伊藤:キャッチコピーもビジュアルにおいてもですね、単純にシンプルにですね、誰の何を改善するサービスなのかっていうのを直感的に伝える必要があるわけですね。この部分が整理できていないと、ページの滞在時間も短くなりますし、離脱率ですね、エンゲージメントの率が下がりますので、そこは非常に重要なポイントになるかなというふうに思います。
伊藤:で、そのファーストビューの下あたりにリード文と言われるような、だいたい200文字ぐらいの文章を配置するんですけども、そこをしっかり書くことで、読了率ですね、一番ページの下まで行ってもらえる確率が格段に上がっていきます。
伊藤:はい、ではここでまた問題をお出しします。先ほどはブログの見るべき指標がありましたが、今度はLPの指標になります。LPだとどんなものを見ていったらいいでしょうか。
Y.K:LPだとどんなものを見ていったらいいだろうか。僕が見るときは、上から下までザーッと見て、どんな構成になっているかっていうことを、どういう説明になっているか、どんな理論で進めてくるかっていうのを見るんですが、今伊藤さんが聞いているのは、LPを作ったときの評価基準をどこにすべきかということですか。
伊藤:リリースした後の数値です。
Y.K:コンバージョンとか。
伊藤:GA4の数値で何を見たらいいかってこと。
Y.K:コンバージョンとか成果だと思うので、ページのどこを見ている、どこを一番見られているかっていうことで、ちょっと文言がわからないですけど、ページのどこを皆さん見ているかっていうことと、あとは、ランディングページだから上から下まであるんで、何パーセント見て、どこで皆さん離脱しているかっていうことじゃないですかね。
伊藤:今、GA4においてというふうにお伝えしているので、どこを見ているかっていうのは、もちろん取れなくはないんですけど、それを見る場合はヒートマップツールというものを契約して、プログラムを入れないといけないんですね。15年ぐらい前は結構流行っていたんですけど、最近あんまりやっているところが少ないかなっていうふうに思っていて、なぜかというと、プログラムとして非常に重いので、ヒートマップツール自体が。それによってサイトが、ページのスピードが落ちてですね、離脱につながるんですね。なので本末転倒だなっていうところで、あんまり発展していない印象があります。もちろん見ることはできます。
伊藤:ブログと違った指標が少しあって、もちろんエンゲージメント率は重要なんですね。つまり、ファーストビューが悪いとエンゲージメント率が悪いんで、全体の数値が落ちてしまうよねっていうところです。なのでそこは改善したほうがいいです。
伊藤:もう一つはスクロール率ですね。つまり、ブログと違うのは縦に長いものなんで、最後まで見てもらえる可能性がどれぐらいあるのかなっていうところを見ていきます。一般的に言うと50%の部分ですね、全体のスクロールで、だいたい半分離脱するって言われているんですね。なので半分以上離脱していないかっていうところをチェックしたりして。
伊藤:これも実はスクロール率ってデフォルトでは設定がついていないので、Google Tag Managerとかで、あるいは別のもので、JSでもいいんですけど、プログラミングを仕込んで計測する形。スクロール率。なので業者に依頼するときは、もしスクロール率が入っていなければ、スクロール率を入れてもらったほうがいいかなというふうに思います。
Y.K:H.Rさん、スクロール率はいつも見ていますか?やっぱり動向はそこまで今しているかしていないか?
H.R:ランディングページは作っただけで、すみません。
Y.K:いいです。ごめんなさい。
H.R:全然その辺までやっていないです。
伊藤:はい。ここまで3番目4番目のところで何かご意見ご質問あればお願いします。
Y.K:H.Rさんの会社の社長はですね、PASONAっていう理論は生まれたときから身についているような気がしますが、PASONAっていうのを自分の商売に落とし込んで何かストーリーを組み立ててみると、仕事に使えるかなと思いました。ちょっとウェブのことではないですが、PASONAのことでそう思いました。以上です。
伊藤:最近やっぱり広告全般の打率っていうのは非常に悪くなっているんですね。昔から比べると。広告の単価も上がってきているんです。なのでやはり商品を売るっていうのは結構難しくなっているんですね。なので、お二人ともご商売の中で、ホワイトペーパーをどうダウンロードさせて顧客リストを取るか、みたいなところをお考えになったほうがいいかなと思うんですけども。
伊藤:ホワイトペーパーダウンロードで顧客リストゲットみたいなのが考えられそうですか。どうですか。
H.R:まだそこまで考えていなくて、顧客リストを取った後、自分がどういうふうにそれを活かしていったらいいのかっていうのが、まだわかっていない。顧客リストの重要性がまだ自分の中でわかっていないのもあって。
Y.K:伊藤さんちょっと一つ質問ですけど、例えば割引を配ったりするもののホワイトペーパーの中に入るわけですか。自社の情報やノウハウをホワイトペーパーっていうのはわかりますけど。
伊藤:クーポン券とかはここには含まれていないですね。割引をつけてもいいんですけどもね。有効期限付きのものを発行したりとかっていうのはありだと思いますけど、有効期限をつけたりするのもツールを使ったりしなきゃいけなかったりするんですね。
伊藤:なので資料ダウンロードできますっていうのは一番コスト的には安いし、お客さんとしては興味関心の度合いとしては強いんですよね。わざわざメールとかLINEを登録して資料をもらうわけです。つまり割引って割引好きの人がいて、そのお客さんってあんまりいいお客じゃない可能性があるんですね。
伊藤:どうでしょうか。ホワイトペーパーは何か作れそうですか。
Y.K:ホワイトペーパーであれば起業するときにするべき準備とか、そういうものがホワイトペーパーに当たるのかなと思いました。
Y.K:そうですね。そういうものを配布しておいて、いろんなクリエイターさんたちがいると思うので、その人たちの起業秘話みたいなものが、LINEなりメールマガジンなりで見れるよっていうふうになると、通常のレンタルスペースとは差別化していけるのかなと思います。起業するのに興味のある方がホワイトペーパーを取ってくださるので、まだ見込み客ですけど、ロイヤリティが高い。
伊藤:そうですね。
Y.K:情報の網羅性のところで抜け漏れの話をされましたけど、先ほど表を見せていただいたじゃないですか。ブランドサイトのコンテンツ。必要性・優位性・信頼性・安心感ということで。これは表はわかるし、表の考え方もわかるんですけど、自分の作ったものがちゃんと網羅性を担保してるかっていう、抜け漏れがないかっていうのは、今流行りのAIで何か指摘をしていただけるものがあるのか、それともやはりそれは専門家に見てもらったほうがいいのかっていうと、その選択だとどちらになるでしょうか。
伊藤:たぶんですが、Y.KさんはAIを十分に使いこなせてないと思うんですよ。僕から見るとですよ。他の一般的なほとんどの人も使いこなせてないので、たぶん専門家にお金を払って見てもらったほうがいいねっていうことだと思います。
Y.K:わかりました。
伊藤:AIの使い方で、芥川賞の作家の方が執筆にも使ったって言われていて、話題になりましたよね、2年ぐらい前に。でもやはり物を作り出すノウハウや品質のチェックができることが前提なので、そもそも作業のノウハウを持ってない人は、AIを使ってもあんまり良い結果にならない。もちろんご自身が手を動かすよりは品質は上にいくんですけど、絶対値が高いかっていうとそうではないと言われてる。AIには、能力の拡張の要素もあるんですけど、どちらかというと時短なんですよね、今の時点では。なので、僕はウェブサイトのノウハウを持ってるんで、僕がやると能力の拡張もあるんですけど、圧倒的に時短になる。だから現時点では、時短側で考えていったほうがいいかなというふうに思います。もちろんAIは遊びの中でいろいろアイデアを使っていくのはいいと思うんですけど、実際Y.KさんがAIを使ってるところを僕は見てないんで、評価ができないんです。
Y.K:わかりました。ありがとうございます。
H.R:今の時間でさっきの質問を考えてみたんですけど、うちでホワイトペーパー作るなら。
伊藤:お願いします。
H.R:亡くなった方のご家族向けに、やらなきゃいけないことを書いて、で、こんなことも必要だよ、あんなことも必要だよ、こんなことも必要だよっていうふうに書いていって、みたいなことで、最後に買取店でできますよ、みたいな感じが。
伊藤:遺品整理のノウハウですね。
H.R:遺品整理に関わる、不動産とか片付けとか買取とか、ここでこういう補助金もあるとか、そういう必要な知識みたいな。
伊藤:なるほど。それいいですね。
H.R:どうかなって思いました。
伊藤:そうですね。それがあると非常にいいかなと思います。いつかやらなきゃいけないなって、たぶんみんな思い始めると思うんですよ。50過ぎか60過ぎ。人によってタイミングが違うと思う。そういう資料があると、ちょっと手元に置いておこうかなってなりますよね。
H.R:なりますね。
H.R:この間Y.Kさんとお話ししたときに、亡くなる前にアプローチして、うちに頼んでくれるみたいなのができていけば話が早いっていう話もあったり。
Y.K:そりゃそうだ。
H.R:そういうところにアプローチしても面白いかなって。
Y.K:僕が死んだらここへ頼むみたいなね。
Y.K:今そんなこと考えてました。
H.R:ありがとうございます。