
WEBマーケテイングが学べて、個別相談もできるオンラインサロン開講
「マーケティングって結局、何なんだろう?」——これは私たち自身、ずっと抱えてきた問いです。広告やSNSだけでは語りきれない、でも確かに“売れる仕組み”をつくる営み。今回の勉強会では、その曖昧な輪郭を少しずつ言語化しながら、私たちなりの解釈を共有してみました。正解のない世界だからこそ、まずは基本に立ち返り、一緒に考えるところから始めてみましょう。
目次
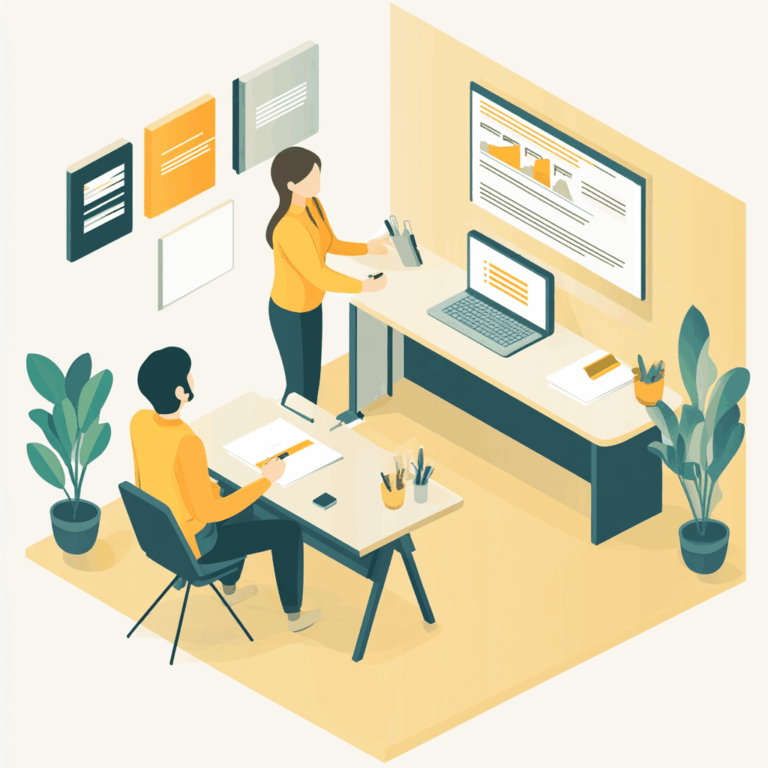
多くの誤解、マーケティング=広告ではない
伊藤:前回、ご説明の回(4月15日)にも、ご参加いただきましてありがとうございました。画面のトラブルがありまして、うまくお伝えしきれなかった部分もありますので、ちょっと冒頭におさらいをさせていただきます。
伊藤:「メタ思考のグリア」ということで、本日から全10回の開催となります。オンラインサロンでは、基本的に前半の無料枠では一般的な知識や最新のトピックなんかもお伝えしていくんですが、後半の有料枠は、メンバーの方の課題に寄り添いながら勉強会を進めていく予定になっております。
伊藤:スケジュールは、原則第3火曜日の17時から無料枠と17時半から有料枠がスタートということになります。
伊藤:さて、本日のテーマ、第1回目ということなので、「マーケティングとは何か?」ということについて概観ですね。総論的なところになるので、もしかしたら、既に知見があって、ちょっとつまらないなっていうふうに感じる方もいらっしゃると思いますけれども、結構大事な部分なので、繰り返し、この後見逃し配信なんかもしていく予定ですので、繰り返し見ていただけるといいかなというふうに思います。
伊藤:まずは、マインドマップのほうでご説明をしていきたいと思います。今日ご用意しているのは主に4項目になります。
伊藤:最初の項目ですね。マーケティングの目的とは何でしょうかと聞かれると、結構人によって回答が違ったりするんですね。マーケティングとかブランディングって非常に便利な言葉なんですけれども、何かを言ってるようで何も言ってない場合が結構多い。
伊藤:この勉強会では、こういうふうに定義をつけています。「商品やサービスが効率よく売れる仕組みづくり」のことですね。なので最近ですと、マーケティングイコールウェブ広告だみたいに考えていらっしゃる方も、若い方は特にいるんですけれども、そうではないということですね。
伊藤:若い方はマーケティングっていうと広告だと考えて、年配の方はそれはマーケットインであるって言ったりするわけですね。つまり年代によって、あるいはポジションとかによっても、マーケティングって何って聞いたときに、それぞれ別の回答や認識を持っているということですね。この辺りをきちんと整理した上で、各社の課題に向き合っていきたいなというふうに考えております。
伊藤:なお、従来のマーケティングには四つの要素がありました。ウェブ以前のものですね。いわゆる現在オールドメディアと言われているようなものも含まれてきます。つまり事前調査をし、それを分析した結果をもって、商品やサービスを企画開発していこうねっていうのがマーケティングの大きな枠組みになってくるわけですね。その後にようやく販促、いわゆる広告プロモーションの部分に関わってくるというわけです。
伊藤:では最後の部分ですね。プロモーションだけがなぜマーケティングではないのかっていうことに関してご説明をさせていただきます。
伊藤:若い方、特にウェブをやられてる方は、マーケティングイコール広告であるというふうに言われてる方も多いんですけれども、マーケティングの基礎的な知識が足りてないなっていう方が多くなってきました。
伊藤:この原因の一つとして、ウェブの制作とか運用に関わる補助金がたくさん出てるんですね。補助金で実はジャブジャブの業界であったりするわけです。なので高い金額、今ウェブサイトを作りましょうというと大体一撃で100万円ぐらい請求されるんですけども、デザインだけで、実は中身が全然伴ってないなっていうサイトもちらほらあります。あるいは実力がちょっと足りてないんじゃないか、知識が足りてないんじゃないかなっていう担当者の方もちらほら見受けられます。
伊藤:なぜそういうことが起きてしまったかという背景なんですけれども、実はこの前述の従来のマーケティング四つの要素というのは、別々の会社に外注していたんですね。調査と分析は、もしかしたら一度にやってくれる方もいるかもしれません。商品企画、これはまた別でプロフェッショナルがいます。そして販売促進も別のプロフェッショナルがいたということですね。
伊藤:ところがそこに変革が起きました。つまりWebでやるとこれが全てオールインワンでできるよねっていう世の中になってきたわけですね。そうなってくると、実はちょっと勉強すると内製化できるっていうことになります。
伊藤:この1年ぐらいで特にAIが非常に進化を遂げていて、実は広告代理店、あるいはWeb制作会社というのがAIに仕事を奪われてきてるんですね。いわゆるナレッジと言われるようなものは全てAIが吸収し、それが一般の方でも活用できるようになってきたということですね。
伊藤:ところがナレッジをゼロから学んでいくっていうのは、やはりいくらAIがあってもなかなか難しいものなんですね。なのでこういう勉強会を通じて、基礎的なことを学び、AIを活用しながら内製化して、ご自身のご商売に最適化されたマーケティングをやってみようというのが、このオンラインサロンの目的となります。
伊藤:では広告の活用方法を見ていきましょう。Web広告にはメリットとデメリットがあります。まずデメリットのほうからいきましょう。要はお金がかかるということですね。
伊藤:リアルの実店舗に比べると、Webの商売というのは実はイニシャルコストは非常に低いんですね。反対に何がかかるかっていうと、ランニングコストになります。特に近年言われてるのが、広告の単価がものすごく上がってきているということですね。
伊藤:先ほどもありましたように、AIを活用すれば専門家でなくても広告が出稿できるようになってきているということです。つまり参加するプレイヤーが増えたから、単価が上がっちゃうよねっていう世界がやってきたということですね。お客さんの獲得や販売にかかるコストが上がりすぎると利益が出ないよねっていうデメリットが一つあるわけです。
伊藤:それからもう一つが、ブランディングができないということが分かってきています。ウェブ広告だけでブランディングできない。なぜなのかということなんですけども、従来オールドメディアでもメディアミックス理論というのがありました。実はウェブのほうもメディアミックス理論が最近では言われ始めています。
この項のまとめ

WEBのメディアミックスについての誤解
伊藤:ではY.Kさんにご質問です。ウェブのメディアミックスは三つありましたけれども、何メディア、三つのメディアがありました。覚えていらっしゃいますか?
Y.K:オウンドメディア、三つ。オウンドメディアしかパッと頭に浮かんでこないですね。ちょっとすみません、申し訳ないです。
伊藤:はい、ありがとうございます。正解はこちらになります。ペイドメディア、お金を払って出すメディアですね。つまりリスティング広告とかディスプレイ広告のようなウェブ広告にあたります。
伊藤:それから二つ目がいわゆるSNSですね。FacebookであったりとかX、それからInstagramなどのSNSメディアになります。
伊藤:それから三つ目がオウンドメディアになります。これは自社のホームページであったり、ブログであったりというところですね。
伊藤:広告だけ使っていると、ペイドメディア、露出はするんだけれども、認知は進むんだけども、それってお金を出してるだけですよねっていうことで、普段の取り組みというのが全く見えてこないんですね。
伊藤:つまり、例えば、あんまり説明がいらない低単価の商品であれば、ペイドメディアだけで売れてしまうチャンスはあるんですけれども、説明が必要であったり、一品の単価が高いような商品やサービスというものは、広告だけではコンバージョン、お客さんは落ちないんですね。
伊藤:なので今言われてるのは、三つともバランスよくやっていきましょうということが言われています。これがWebのメディアミックス理論になります。
伊藤:もちろん、ペイドもアーンドもオウンドも全部やったほうがいいんですけども、もし1個しかできない、1個しかやる余力がないとするならば、一番やったほうがいいのは実はオウンドメディアなんですね。その代わりデメリットもあるわけです。それは広告のメリットと相反するものであったりするので、これを見ながら説明していきましょう。
伊藤:ではWeb広告のメリットは何かというと、結果が早く出るということですね。お金を出したりすれば検索の結果に出たり、あるいは関連性の高いサイトに表示されたりするので、ブログやSNSとはスピード感が違うんですね。
伊藤:例えばSEOで結果が出る、オウンドメディアでブログを書いていきましょうとなったときに、結果が出るのが最短で半年ぐらいと言われています。もっとかかる場合もありますね。1年とか1年半かかる場合も十分あるわけですね。
伊藤:それから広告のメリットは認知は上がるよねっていうところになります。ただ、あのお店この間見たなみたいな感覚だけなので、深い理解とか深い訴求力があるわけではないんですね。
伊藤:逆に深い訴求力を得ようとすると必要になってくるのは、やはり一番訴求力が強いのはオウンドメディアになってきます。
伊藤:なので使い方としては、ペイドメディアとかアーンドメディアでしっかりテストマーケティングをしながら、どんなブログを書くとお客さんに訴求力があるのかというところを組み立てる、テストマーケティングのツールとして使っていくことが好ましいかなと思います。
伊藤:もちろん先ほど申し上げたとおり、もう広告見てすぐコンバージョン、購入するみたいな属性の商品であれば、どんどん上の二つを活用したほうがいいと思うんですけども、じっくり時間かけないと売れないようなものは、三番目のオウンドメディアのウエイトが高くなるということになります。
伊藤:最後の項目ですね。今回の目的になります。正しいマーケティングの知識を習得していただきます。テクニックに走らず、より本質的になるということですね。
伊藤:テクニックに頼ってしまうと、われわれのこのウェブの業界というのは非常にサイクルが早いので、3カ月とか半年で全くルールが変わってきてしまうことが多いですね。そうなってしまうと、今まで使ってたテクニックってもう使えないよね、なので集客力が落ちたりとか売り上げが落ちたりっていうことが起きてしまうということになります。
伊藤:そこで古典的なマーケティングの概念を理解することが、非常に重要かなというふうに考えているので、この辺りも今後触れていきたいと思います。
伊藤:具体的に言うと、マッカーシーとかコトラーとか、ドラッカーとかをきちんと理解した上で、ウェブ上でどんなことをやるっていうふうに考えていくのが正しいかなというふうに思っています。
伊藤:簡単に触れていくと、この後、詳しくやりますけど、マッカーシーで言うと4Pというところが有名です。本当に古典的なマーケティングですね。
伊藤:それからコトラーは現代マーケティングの父と言われています。STP理論やマーケティング3.0みたいなことを提唱している学者ですね。お客さんも市場もどんどん変化してるんだよっていうところ。
伊藤:それから僕の大好きなドラッカー先生ですね。マーケティングの理想は販売を不要にするということですね。つまりマーケティングの反対語はセリングですね。売り込みであるということですね。売り込みを全くせずに自動的に売れるのがマーケティングの本質であるというふうに言われております。
この項のまとめ
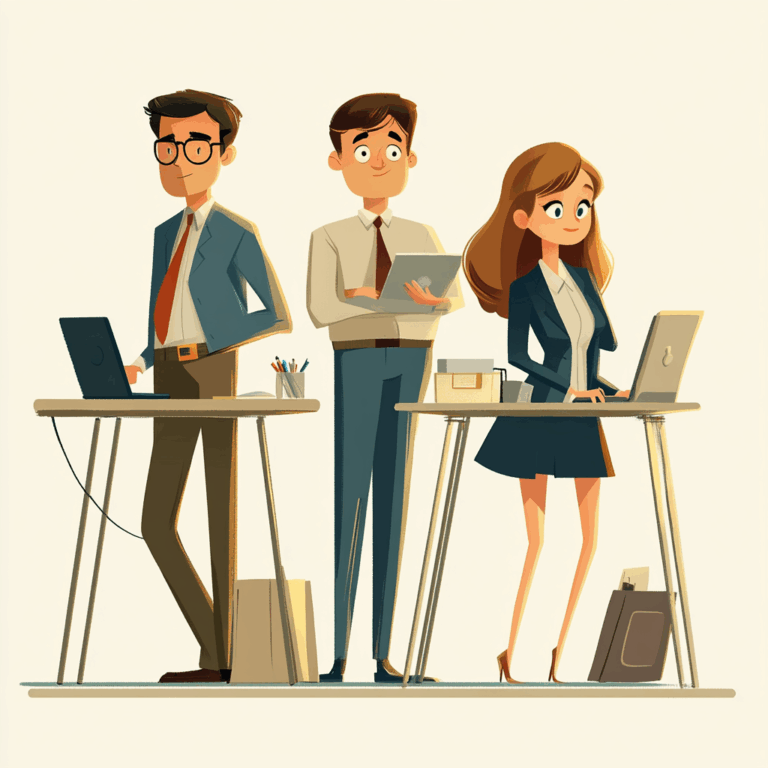
中小企業がとるべきWEBマーケティング戦略
伊藤:ばーっと座学的にお伝えをしてきましたけれども、何か感想とかご意見とかご質問あればお願いします。
Y.K:伊藤さん、今日はマーケティングの概論で、マーケティング全体のことをご説明していただいて、ありがとうございます。オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディア、業種によって使うメディアが変わってくるとは思うんですが、小売りだとやはりオウンドメディアを中心にしていくべきでしょうか。ちょっとその辺、短くでも結構なんでお伝えいただければ、どの優先順位になるのかっていうのを教えてください。
伊藤:ありがとうございます。非常にいい質問、具体的かつ非常にいい質問かなと思います。ECの世界でいうと、利益が出やすい出にくいの分岐点はバスケット単価が4,000円と言われています。
伊藤:基本的にお客さんというのは3,000円以下のものは衝動買いしてくれるんですね。なので、もちろん説明が必要な商品であれば3,000円以下でも戦略変わってくるとは思うんですけど、例えば3,000円以下のスイーツみたいなものは、お客さんは躊躇なく購入してくれるんで、その場合はペイドメディアやアーンドメディアで販売を戦略組んでいくっていうのは有効な手立てだと思います。
伊藤:ただし、一品単価が高い、あるいはバスケット単価が4,000円以上のものは、やはりちょっと説明が必要になってくるので、その場合はオウンドメディアのウェイトが相対的に上がってくる、上げたほうがチャンスが増えるんではないかなというふうに考えています。
Y.K:どうもありがとうございます。金額で一つ線引きをして考えるのは、ちょっと新鮮な発想だなと思って今聞いておりました。以上です。
伊藤:そうですね。ただ、先ほど申し上げたとおり、バスケット単価、1回の買い物の単価が4,000円以下だと売れるんですけど、売っても売っても利益が出ないっていう状況に陥りやすいんですね。なぜなら先ほど申し上げたとおり、EC、ウェブ全体そうなんですけど、ランニングコストは非常に高いんです。
伊藤:つまり3,000円に対してカード手数料であったり、送料であったりっていうところが乗っかってくるので、実は粗利は5割以上ないと成立しないんですね。なのでスイーツが何で売れてるイメージがあるかっていうと、原価がめちゃくちゃ安いんですね。つまりスイーツって技術料とかデコレーションのアイデア料だったりするんで。
伊藤:あとアパレルもそうですよね。例えばプラダみたいなもので、基本的にはデザイン料はありますけども、原価がめちゃくちゃ安いんで、そういうものがやはりネットとしては売り上げが伸びやすいという状況はあるかなというふうに思います。
伊藤:ではO.Mさんはいかがでしょうか。せっかく今日来ていただいたので、何かお感じになったことがあればお願いします。
O.M:ありがとうございます。先ほど3つのメディアがあるって言ってたんですが、これって事業規模に対して掛ける費用って、それぞれ違うと思うんですけど、大体その事業規模の何パーセントぐらいが広告として適切なんですかね。ちょっと標準価格というのが私もわからないので。
伊藤:そうですね。一般的には広告予算というのは売り上げの5%から10%というふうに言われています。なので先ほど申し上げたとおり、それは一品単価とかバスケット単価、あるいは原価率みたいなものによっても変わってくると思うんですけども、相場的にはそれぐらいになっています。
伊藤:一方で、中小企業に限定すると、やはり一般的なのは月額5万円から10万円っていうラインが妥当なのかなっていうところがあります。もちろん50万とか100万使われてる中小企業さんも中にはありますけれども、数的には非常に少ないかなというところがあります。
O.M:すみません、業種によってこの3つのうちどれに重きを置くかっていうのは、別にいろいろあると思うんですけど、中小企業の方だと一般的にどれをやるのが一番費用対効果というかいいのかなと思います。
伊藤:そうですね。広告を使ったほうがいいのは、いわゆる日用品みたいなところですね。例えばお米とかお水とかって、一度気に入ると定期的に購買してくれるので、最初にお試し品なんかを配ったりしてですね、化粧品なんかもそうですけども、リピートしてくれる、いわゆるLTVといいますけれども、ライフタイムバリューが高いような商材は割と広告で集めていくものが多いですね。
伊藤:アーンドメディア、SNSみたいなものは、例えば食べ物もそうですし、化粧品とかスキンケア系とかはですね、やはり第三者のレビュー、感想みたいなものが非常に重要になってくるんで、そういうものはSNSのウェイトが高いかなと思います。
伊藤:そして、オウンドメディアに関しては、先ほども一番やったほうがいいですよっていうのは、基本的にはしっかり骨太なブログを作るとですね、それのダイジェスト版を広告であったりとかSNSに流用していけばいいので、オウンドメディアがしっかり作れると、実は他の2つも非常にうまくいくパターンが多いですね。
伊藤:なので、業種によってウェイト比率が変わってきますけれども、基本的にはオウンドメディアをしっかりやっていくっていうところが、長期的に見たときには非常に有効なのかなというところが見えてきています。
O.M:ありがとうございます。
伊藤:ではT.Yさん、いかがでしょうか。
T.Y:そうですね。コトラーの話ですかね。マーケティング1.0、2.0、3.0の話のところなんですけど、マーケティング3.0の議論だけにフォーカスしないほうがいいのかなっていうふうに思ってて、これ積み重ねの議論なのかなっていうふうに思ってるんですよね。
T.Y:なので、社会的責任だけとか、利益より社会的責任ってなると、もともともない話になってるのかなっていうふうに思ってるので、この辺はしっかりした解釈で進めていかないといけないのかなっていうふうには思ってます。
T.Y:メディアの3つの話のところだと、自分もよくランディングページとかで転換してしまうものとかがあったりとかするんですけど、やっぱり皆さんも消費者として、この会社大丈夫なのかなとか、背景どんなことあるのかなっていうふうに、別にGoogleとかで検索すると、そこにはしっかりしたオウンドメディアというか自社のウェブ媒体でしっかりした製品のストーリーとか、そのサービス提供に当たった経緯だったりとか、そんな情報があると信頼感増して、会社さんとかこのサービス使ってみようっていうふうに思うことがあるので、結構その辺りが改めて整理できたかな、メタ思考として整理できたかなっていうような感想です。
伊藤:ありがとうございます。マーケティング3.0に関しては、僕もまだ勉強中ではありますけども、T.Yさんおっしゃったとおり、別々に存在しているものではなくて、1階建て、2階建て、3階建てみたいなイメージですよね。
伊藤:なので、社会にとって素敵なことをやっても、それって、じゃあどの層を取りに行く話なんですかっていうことになるし、そもそも商品として品質が良いことは当たり前だったりするんですよね。なので、しっかりこのピラミッドを積み上げるようにですね、1から2、2から3というふうに、企画の段階できちんとチェックしていけるといいかなと思います。
伊藤:3大メディアのことに関して言うと、やはり白物家電であれ、日用品であれ、贅沢品であれ、何でもそうなんですけども、広告を見てすぐ買うっていうことは結構レアケースなんですよね。広告を見たときに、その後にSNSで検索したりとか、Googleで検索した後に、やはり購買行動に繋がる。いわゆるAIDMAからAISASですね、購入の手前にサーチが入るっていうことなので、バランスよくやりましょうねっていうふうにお伝えをしたわけです。
伊藤:なので、ペイドメディアとアーンドメディア、つまり広告とSNSは非常にスピード感が早いので、うまく活用しながら、骨太な情報をお客さんに提供していくということが非常に重要になってくると思われます。
T.Y:ありがとうございます。
この項のまとめ
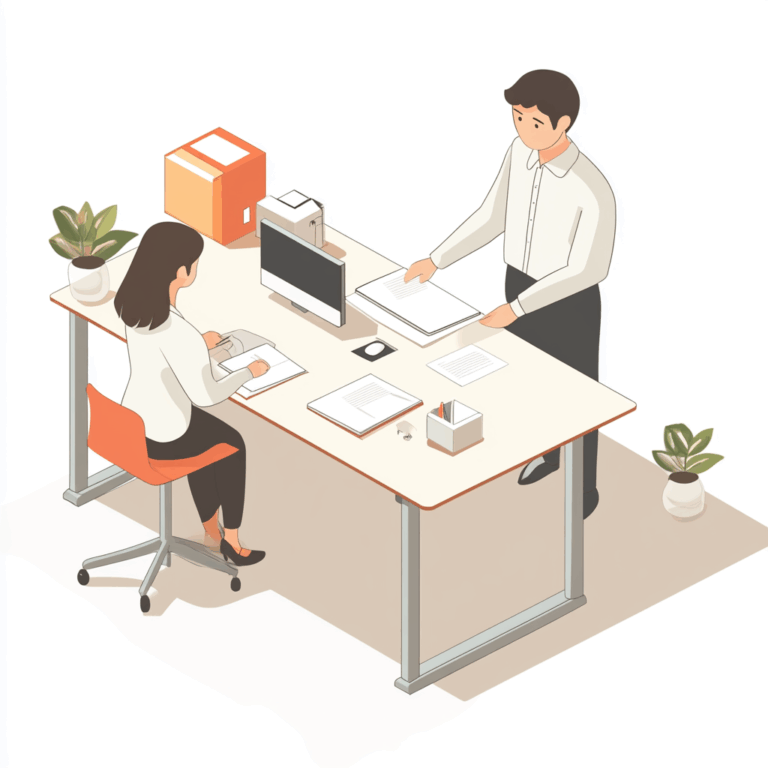
WEB最大の機能は「商圏の突破」と「データの蓄積」
伊藤:はい、ちょっとじゃあ先にマッカーシーの説明をしようかなと思います。マッカーシーの4Pと言われるものですね。この順番で昔は成立してたんですね。つまり何か商品を作ったときに、どういいものを作るか、デザイン的にどうか、ブランディングできるかどうかみたいなものを、まず固めていきます。
伊藤:それからその商品をいくらで売っていきますか、価格が適切かというところを討議していくわけですね。価格設定はフィロソフィーであるという言葉があります。何年か前にティファニーが安売りをしたんですね。そしたらですね、びっくりするぐらい不人気でですね、ほとんど売れなかったというケースがあります。
伊藤:先ほどの業種とか業種業態に近いお話になりますけれども、そもそもその商品が自家需要、自分で使うものなのか、自分で消費するものなのか、それとも贈答用の商品なのかっていうところによっても価格設定は変わってきたりするわけですね。
伊藤:それからプレイスですね。どこに流通させるべきなのかというところを議論してきました。実店舗であればどこに、デパートなのか、それとも小売店、専門店なのか、あるいはウェブ向きの商品なのかっていうところは非常に重要な点になってきます。
伊藤:よくある話ですね。コンビニで買うとコーラは200円位だけども、リッツカールトンでルームサービスで飲むと1杯1000円であるって話ですね。つまり場所によって価格も影響を受けてくるということになります。
伊藤:4つ目が今回のテーマにちょっと関わってきますけど、プロモーションですね。どのように知ってもらうかということですね。先ほどAIDMAという基本のキーワードが出ましたけれども、アテンションの部分ですね。どう注目させるかっていうところも非常に重要ですよというのが、古典的なマーケティング、マッカーシーの4Pになります。
伊藤:それからコトラーのSTP戦略ですね。セグメント、ターゲット、ポジションという3つをしっかり整理した上で行動を開始しなさいということが先生の教えですね。
伊藤:この3つの要素の中で実は一番重要なのは一番目のセグメントです。この中には、これ前ちょっとAIにリストアップさせたんですけども、年齢、性別、地域などが回答としてありました。しかしですね、近年言われてるのは、この情報だけではダメだと言われている。それが次のページですね。
伊藤:これは、デモグラの崩壊と言われている。いわゆる従来使われてきたマーケティングのセグメントが、実はほとんど効果を生まなくなってきているという話なんですね。その後どうなったかっていうとですね、左側、もう全然ダメな領域になっていて、この考え方は全く良くないですね。
伊藤:今有効だと言われているのがサイコグラフィックですね。その人がどんな性格なのかとか価値観はどうだとか、もっと言うとですね、どんな購買行動を普段してるのかによって、セグメントを分けなさいというふうに言われてきています。
伊藤:この辺り、T.Yさん、いろいろ試行錯誤されて実感があるのかなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。
T.Y:そうですね。先ほどのコトラーの4Pの話ともあわせて、デモグラ、サイコグラフィックの話もそうなんですけど、ユーザーのインタビューが結構大事かなというふうに思ってて、例えば20代女性、県内在住みたいなところでセグメンテーションを取ったとしても、例えば広告を打ったとしても何の学びもないんですよね。
T.Y:実際に売れたかどうかしか指標がなくて、じゃあ実際に細かいターゲティングにちゃんとできてるのかどうかというところでいくと、何か筋違いなところがあるのかなというふうに思っていて、もう少し軸を変えるというかの考え方のところで、こういう価値観とか趣味とか、例えば最近でいうとミニマリストみたいな表現がSNS上で出たりとかしますけども、こういうグループに対してアプローチしたらどうかみたいなところからターゲティングをちょっと考えると見える世界ってちょっと変わってきてるなというふうに思っているので。
T.Y:この二軸の考え方はすごくしっくりきてますし、ユーザーインタビューを通してこのサイコグラフィックを模索していくっていうのはありなんじゃないかなというふうに思っています。
伊藤:ありがとうございます。デモグラのほうはいわゆる大量生産、大量消費の時代に有効だった手法なんですけれども、現在のように多様化した社会では、実はほとんど効果を発揮しなくなってきているというのが実情ですね。
伊藤:一方で2000年以降、どんなショップが増えてきたかというと、ライフスタイルショップと言われるようなものが増えてきました。代表的な例でいうとアフタヌーンティーみたいなショップですね。つまり、そのものを売るのではなくて、生活とか生き方、暮らしそのものを売ってきますよという、そういうところに寄り添うときに、どうしてもこの右側の要素が必要になってくるということになるかなと思います。
伊藤:では30分あっという間ですね。ちょっと冒頭つまずいた部分もありますけれども、基本的には後半有料プランの方は、相談者メンバーの方の具体的なお悩み相談のコーナーになってくるんですけれども、もしY.Kさんがよろしければ、このままY.Kさんのお悩み相談のコーナーにこのまま移りたいかなと思うんですけど、どうでしょうか。今日はH.Rさんがちょっと出先で戻ってこれなくて、今日欠席になってしまったんですね。本当はH.Rさんに振ろうかと思ったんですけど、急遽代打でお願いできたらなと思いますけど、いかがでしょうか。
Y.K:どうもありがとうございます。今、レンタルスペースを運営をしておりまして、その運営をして、レンタルスペース・レンタルオフィスを利用される方にウェブページを作ってマーケティング、集客(送客?)をかけようと思ってるんですが、なかなか利用される方にそこまでの熱意がないのか意識がないのか、知り合いでなんとかなるっていうふうに思われてるっていうところがあってですね。
Y.K:まずは進捗が悪いのと、あとは伊藤さんから今AIを教えていただいてるんですが、AIで資料を作ると皆さんすごくびっくりされることがあるので。
Y.K:進捗としては、ワードプレスを教えていただきながら、うちの利用者のウェブページを今作成してる最中です。伊藤さん、すみません、こんなところでよろしいですか。もう少し深くしたほうがよろしいでしょうか。
伊藤:そうですね。今の部分で言うと、2つあって、1つがウェブのマーケティングを仕掛けるメリットが大きく分けて2つあります。それを満たさない場合は、ウェブマーケティングじゃないねっていうことになってくるんですけど、前回にもしたと思うんですけれども、覚えてますか?
Y.K ウェブはデータの蓄積と越境なので、その2つ。メリットはデータを蓄積することと、越境して狭い地域から広いところへ行くということで。
O.M:ローカルなのかブレイクスルーで外へ出てくるのか、その意味でよろしいでしょうか。
伊藤:ニュアンス的には合ってますけど、越境というと海外輸出になるので、正確には商圏の突破になります。例えば、Y.Kさんレンタルスペースなので実店舗で営業する、だから北海道で来週営業します、売上立てますっていうのはできないんですよね。将来的に商圏の突破ができるようなコンテンツができるかっていうところは議論が必要かと思います。
伊藤:もう1つが、いかにコンスタントにデータを蓄積していけるか。データというのは2つの属性があると思います。1つがコンテンツですね。ブログであったりとか、ウェブサイトの説明ですね。もう1つが顧客データをどうやって貯めていけるかっていうところになるかなと思います。
Y.K:うちには、レンタルキッチンがあり、起業家の方がですね、EC販売をする可能性が今でも数社あるので、そういう方たちにどういうふうに弊社が支援できるかなっていうことですね。
伊藤:そうですね。なので食品であったり、アクセサリー小物みたいなものは、比較的先ほど言った商圏突破に向いてる商品なので、そういったプラットフォームを将来的に整えていくっていうのは、商圏の突破につながるかなと思います。
伊藤:2つ目、思い出しました。現状は例えばキッチンのレンタルであるとか、コワーキングスペースとか、会議室のレンタルっていう情報がすべてトップページに集約されてるんですね。これって実はあんまりいい状態ではないんです。というのは、やはりGoogleがどういう評価を下すかっていうと、どれぐらい体系的にきちんと情報が整理されてるかっていうところを評価してくるので、現状はごちゃ混ぜの状態なので、何のサイトかの理解が進んでないんですね。
伊藤:なのでレンタルスペースであれば、会議室のカテゴリーを作って、会議室の情報をどんどん貯めていく。あるいは同様にコワーキングスペースとか、キッチン、あとはイベントの情報とかっていうところをきちんとカテゴリーで分けて、塊として見せていくっていうことは、Googleにとってもプラスだし、一般ユーザーさんにとっても情報が見やすいので、非常に有効な手立てになるかなと思います。
Y.K:利用される方のカテゴリー別に分けていくということですね。キッチンが欲しい方はレンタルスペースとかレンタルオフィスとかの情報はいらないですもんね。
伊藤:そうですね。はい。それがもしかしたら離脱につながっている可能性があるかなと。面白い内容があっても間接的に滞在時間を下げてしまう可能性があるということです。
伊藤:はい。ここまでのところで何かご意見とかご質問があればお願いします。何かY.Kさんに質問があればお願いします。
T.Y:ちなみレンタルスペースのビジネスモデルというか、マネタイズポイントってどこのポイント?
Y.K:マネタイズポイントは賃料ですよね。部屋貸しで、うちはもう場所貸しが基本ですので、それがマネタイズで月々、例えば3万とか5万とかの賃料をいただくっていう。マネタイズのポイントと、もう一つは利用される方がやはり商圏を突破して商品を売りたいときに、個人でなかなか商圏突破ができないので、弊社がプラットフォームで商圏突破をしていただく。
Y.K:その中の一つで、食品であれば、冷蔵でしたっけ?冷凍食品の販売の自動販売機、いろいろあるじゃないですかね。そういう自動販売機で冷凍食品を売るものをうちに設置したり、あとはふるさと納税で、利用者の作家さんがキッチンを利用してスイーツを作ったり、焼き菓子を作ったりされる方の販売の代行みたいなこと。
Y.K:ここがマネタイズ。マネタイズ2つで賃料ですね。場所貸しで大家さんという言い方が、大家さんなんで賃料と、ここを使う方の商品販売の手数料、何パーセントか20パーセントという話はしてますけど、それがマネタイズポイントです。
T.Y:ふるさと納税の観点からすると、越境っていう考え方がすごくつながってくる。県外からしてみたときに、何かが集まってるんだなっていうのは、例えばそれがオウンドメディアとかで配信とかされてたりとかすると、そこにストーリー性が生まれてきてくるのかなっていうのは、客観的には、すみません感想ですが。
T.Y:県外からするとどこにあるの、貸しスペースで、県外から借りることっていうのはない可能性が高い。メディア媒体に振っていく、領域はそこなのかなっていう風に。なのでそこの社会的な意味というか、みたいなところが表現ができたらいいんじゃないかな。
Y.K:現状は県外からレンタルスペースを借りに来るなんてことはもう99%ないと思います。弊社を利用する方の商品のeコマースの、ウェブ上での販売の代行なのか、うちのサイトを通じて販売なのか、その辺を考えてます。すみません、ありがとうございます。
伊藤:レンタルスペース自体は何年くらい前ですかね、10年くらい前から徐々に増えていって、おそらく飽和状態ではあると思うんです。高浜市に競合がいるかっていうと、そうではないと思うんですけども、いわゆる場所貸しっていうことに関してはコモディティ化しつつあるし、しやすい業態なんですね。
この項のまとめ

WEB上で事業ドメインを整理していく
伊藤:その観点、差別化ポイントに関して言うと、何かなって考えると、面白いおもしろいやつがいっぱい集まるレンタルスペースであるっていうことなんですね。その一つとして、Y.Kさん「止まり木」のお話をされたらいいかなと思うんですけど、進捗はいかがでしょうか。
Y.K:オフィスを借りてくれてる方がですね、いろんな悩み相談、まちの相談室をT.Sさんという方が運営していただいております。
Y.K:元学校の先生で教職生活36年をされて、生徒指導とかいろいろ発達障害、鬱ですとか、学習障害の相談に携わってきた方が、定期的に相談を受け付けているので、地域の方が、同じ方はなかなかお見えにならないんですけど、1週間に5人から10人弱の方が来店されるということがあります。
Y.K:その中でも、先生のT.Sさんという方が主催されているので、T.Sさんの教え子の方ですとか、同僚の方がお見えになります。面白い方がたくさんお見えになるという、先生がいることによって、地域の方の寄り合い所みたいな、そんなふうにも変わりつつあります。伊藤さん、こんなところでよろしかったですか。
伊藤:もちろん商売としてリアルが中心だと思うんですけども、コンテンツとして商圏を突破できる可能性があるかなと思うんですよね。臨床心理士とかカウンセラーとか、いろんないわゆる病院の治療はありますけれども、ジェネリック的に、その子だけじゃなくて、父兄に対しても寄り添うことができるサービスなので、個人情報云々みたいなところはセンシティブな問題ではありますけども、コンテンツとして価値が出てくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、皆さんいかがですか。
Y.K:社会性、公共性はあると思いますが、皆さんすいません、私の拙い説明でどこまでご理解いただけたかわかりませんが、何か質問とご意見があればいただければと思います。T.Yさんはいかがですか。
T.Y:コンテンツ化されていくといいのかなというふうに思いますし、ここに振っちゃってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。あれもこれもだと何もユーザーさんからすると、何の商売なのかっていうのがわからないところがあるので、たぶんどちらかというとワークスペースとかレンタルスペースみたいなところの棚は、後ろ側に持っていかれた方がいいかなというふうに思います。
Y.K:うまく今T.Yさんの言われることが理解できてなかったんですが、もう少しちょっとこう、違う言い方で、伝えてくれたら理解できるかなと思います。もう一度お願いできますか。
T.Y:つまりは、そのコミュニティの中でのいわゆる困ってる人とか、いろんなバックグラウンドがある中で、サービスを通して豊かな人生になっていくみたいな、そのプロセスをコンセプトにした方が意味がわかるというか、それでこういう場所を運営しているんだねっていうことが理解できると思うので、コンセプトに近いような話にこうなっていくのかなというふうには思っています。
T.Y:全く逆の角度からすると、例えば完全にビジネスとして見ていったときに、最近流行りのワーケーションとかあったりとかすると思うんですけども、そういうところへみたいになってくると思うんですけど、ワーケーションとかチームとか、そうですね。それって結局どこでもできるところだと思うんですね。Y.Kさんのここでしかできない価値って何なの?みたいなところの答えが、この「止まり木」にあるんじゃないかなと思いました。
T.Y:ここでしかでせない価値。ならでは感みたいなところが出てくる要素になりそうだなというふうに思いました。ならでは感、結局レンタルスペースどこでもできるじゃないですか。どこでもレンタルスペースあるので、ならでは感、ここのT.SさんとY.Kさんがいてくれる安心感とか、近くにいてくれる安心感みたいなところは、ウェブ化っていうことからするとブランディング化はされてくるんだろうな。
T.Y:家族感とか、ここに来たら安心していろいろ相談のってもらったよみたいなところに大きな価値があるんじゃないかなというふうに思いました。すいません、伊藤さん、マイク奪いました。
伊藤:T.Yさんありがとうございます。そうですね、経緯から言うと、もともと年4回ぐらい、いわゆるポップアップショップの集客イベントをやりましょうっていうところからスタートしていて、その後にキッチンスペースのレンタルが始まったんですね。そうするとキッチンでランチ営業してるんで、そこに付随してお客さんが集まるようになったので、その時の認知としては進んできたなというところがあります。
伊藤:T.Yさん言われるように、この場所ならではのステージに、次のステージに行くには何が必要かなっていうところを考えると、既存の作家さんたちも非常に協力的だし、面白いコンテンツになると思います。仮にT.Sさんを縦の軸として、そういったときに、例えばものづくりを通じて子どもたちは社会体験できるよとか、年4回のイベントを通じて色々体験できるし、学べるぜっていうところ。
伊藤:つまり、今までのやってる事と内容は変わらないんですけども、切り口が変わるとやはり皆さんの見え方が変わってくるんじゃないかなという、お話を聞いてて思いました。何を中心線に据えるかっていうところがネクストステージなのかなと思います。
Y.K:縦軸・横軸ってグラフのような縦軸・横軸、フォーマトリックスみたいな縦軸・横軸を伊藤さんはイメージされてましたか。
伊藤:何を主で何をフックにするかという言い方のほうが相応しいかもしれません。
T.Y:縦軸・横軸、今伊藤さんの解説がすごいしっくりきてて、先ほどの解説にあったサイコグラフィック・デモグラフィックの話があったと思うんですけども、サイコグラフィックでいくとY.Kさんの住まれている地域でしかマーケティングできてない領域があるんですけども、いわゆる価値観とか不登校とか、引きこもりとか社会的に困っている人たちのお助けっていうような価値観でマーケティングを考えたときに、ちょっとブレイクする要素が出てきてるんじゃないかなというふうに思います。
伊藤:T.Yさん、僕が言いたいことを言っていただいてありがとうございます。それやると特徴も出るし、応援したいぜっていう人も現れるし、遠くからでも見に行きたいねっていう人も。
伊藤:実際、過去に問い合わせがあって、来店されたかどうかわかんないですけど、ちょっと引きこもりみたいな小学生か中学生だったか忘れましたけど、キッチンスペースでお菓子を作りたいんだっていう子がいたので。
伊藤:そういう子が行ってみたいとか、父兄の方が事例のコンテンツもっと見たいっていう風になってくると、ユーザーの見え方がかなり変わってくると思うんですよね。作家さんの方もそういう支援をしたいですよっていう人もどんどん集まってくる。いつもどう旗振りするのかっていうところは、T.Yさんはいろいろお考えになってると思うんで、そこに近い考え方になってくるのかなと思います。
Y.K:はい、以前レンタルスペースにちょっと障害を持った中学3年生の方がですね、お母さんとお菓子を作りに来て、障害を持った方が活き活きされてるのを目の当たりにしたんで、それとT.S先生の「止まり木」っていうのはどこかで接点があればですね、そういうちょっと困っている方たちに、いろいろチャンスを与えられるかなと思いつきました。ありがとうございます。
T.Y:僕も最後一言だけいいですか。先ほど伊藤さんからの講義のマーケティング1.0から3.0の部分で、作家さんの作品って県外のユーザーさんからすると何のストーリーもないんですよ。楽天とかAmazonで並べ替えをすれば、価格が安い順に並べ替えられるものになってしまうんですけども、そのマーケティング3.0のところで、社会的責任の観点からこういう意味で、こういう商品が出てるのねっていうことが理解できたときに、県外のユーザーさんからすると買いたくなるよなっていうふうに思いました。
T.Y:そこの掛け合わせかなっていうふうには、今日の講演を聞いた、すいません後半ディスカッションだと思うので、すいません、
Y.K:掛け合わせね。
伊藤:そうですね、我々中小企業ですから、イノベーションを起こすっていうことはほとんど無理なんですね。青色ダイオードの中村先生みたいなケースはレアケースだと思いますので、改良と掛け合わせというところで、いかに生き残っていくかっていうところが中小企業のマーケティングの考え方の基本になるかなというふうに思います。
Y.K:ありがとうございました。大変参考になります。ちょっと掛け合わせ、掛け合わせ、掛け合わせ、探します、掛け合わせる人。
伊藤:はい、では6時を過ぎましたので、今日私の方でご用意したのは一旦以上になりますが、何か今日の流れの中でご意見やご質問、あるいは今後についてご要望などあれば皆さんお願いいたします。Y.Kさんいかがでしたか。
Y.K:はい、O.Mさん、T.Yさん、どうもありがとうございます。こういうセミナーという、こういうサロンもあるんだなっていうふうに思った。年齢のせいにしちゃいけないんですけど忘れっぽいので、これは伊藤さんにちょっと質問ですけど、これを後でどういうふうにしたら、この画像をチェックできたりとか復習できるのかっていうのをまた教えていただきたいなと思います。
伊藤:はい、ちょっと今回間に合わなかったんですけど、皆さんには弊社のサイトにアカウントを作っていただいて、ログインするとすべての情報にアクセスできるような形を取ります。またですね、前半の無料枠に関してはダイジェスト版の記事を作成して、これに関しては一般のユーザーさんも見れるような形になっていく予定です。
伊藤:そのコンテンツが積み重なっていくと先ほどの情報の蓄積ですね、重なっていくとウェブやってみたいぜとか、コンテンツは面白いから俺も参加したいぜみたいなことがですね、広がっていく予定になっております。
伊藤:大変お恥ずかしい話なんですけど、説明会でも言ったかもしれないですけど、Googleアナリティクスすら入ってない状態だったんですね。「紺屋の白袴」とは弊社だなと。現状弊社のアクセスは1日1件ぐらいしかないんですけど、これがじゃあ半年後にどうなってるかとか、1年後にどうなってるかというところをぜひ皆さんにお伝えできたらなと思います。
伊藤:それがオウンドメディアの効果だと思うので、なので今から始めても遅くないよっていうところを私が自身で体現したいなと考えています。
伊藤:O.Mさんいかがでしたか。
O.M:今日は勉強させていただき、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
伊藤:実はですね、ウェブってオールインワンでどこまでも着手できるんです。それぞれ割とハードルが高くて難しかったりするんですけど、そこにトライしておくとですね、事業承継とかあとは人材育成とか、あとは業態変更を考えている方には非常に効果的だったりするんですね。
伊藤:なのでウェブはあんまり興味ないけど、人材育成の一環として勉強会を提供できたらなと考えておりますので、そういうお客さんいたらぜひ一緒にご参加いただければなと考えています。よろしくお願いします。
伊藤:T.Yさん、いかがでしたでしょうか。
T.Y:メタ思考の考え方が、普段いわゆる仕事とかワークに入ってくると個別最適の話になっちゃうんですけど、やっぱり定期的にこのメタ思考で全体の議論をラップアップしていくというか、その概念的にどうだったんだっけみたいなところは定期観測的に情報入って、そこの上下運動だと思っているので、節目節目でやっぱりこういう場は必要だなというふうに思いました。ありがとうございます。
伊藤:今日、実はご欠席なんですけども、説明会に来られていたH.Rさんという方、20代の方ですけども。今日来る予定だったんですけど、ちょっと突然予定が入ってこれなくなりました。最近進捗どうですかって言ったらですね、今年の2月に昨年度の勉強会が終わって以降、やはりちょっと手数が止まってしまってるっていうことですね。
伊藤:当初いくらモチベーションが高くても、モチベーションは時間とともにどんどん低下してしまうんですね。なので月1回ぐらいリテンションしてですね、この勉強会を使ってですね、みんなも頑張ってるから自分も頑張らないといけないなっていうところも、このオンラインサロンの狙いだったりします。
伊藤:皆さんに是非お願いしたいのか、公式LINEには登録いただいてますか?LINEの方でもいろんな情報を配信していきますので、ぜひ営業のネタに使っていただけたらなと思います。ありがとうございます。
伊藤:はい、では以上です。今日ちょっと早いんですけども、後半の有料枠は30分1社で2枠ぐらいを考えていますので、ちょっと僕がまだ集客に踏み込めてないんですけども、毎回2社ぐらい取り上げて、課題解決をこんな感じでしていけたらなというふうに考えております。では本日ご参加いただきましてありがとうございました。
一同:ありがとうございました。
この項のまとめ
編集後記
如何でしたでしょうか?
本記事では、「マーケティングとは何か?」という根本的な問いに立ち返りながら、Webの世界における最新の動向と本質的な考え方を、参加者の熱意ある議論とともにお届けしました。
SNSや広告だけに依存せず、自らの想いを「伝える力」に変えていく——その手段としての「オウンドメディア」の可能性や、「サイコグラフィック」に基づいた共感のマーケティングは、多くの気づきを与えてくれたのではないでしょうか。
課題整理として、レンタルスペースというリアルな場に、志ある人々が集まり、地域と社会に温かな循環を生み出す——それをどう実現していくか、たのしみですね。
この対話と学びが、誰かの一歩につながることを願って。
[有料会員限定]見逃し配信を見る
今回の記事の配信データを有料会員様限定で公開中。繰り返し視聴する事でWEBマーケティングの力が身に付きます。
会員限定コンテンツ
ご覧になるにはメンバー登録が必要です。
オンラインサロン「メタ思考のグリア」とは?


