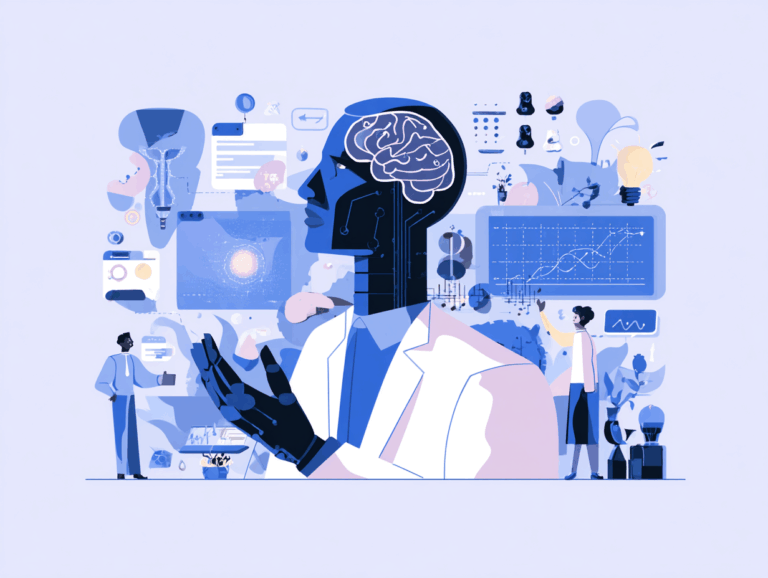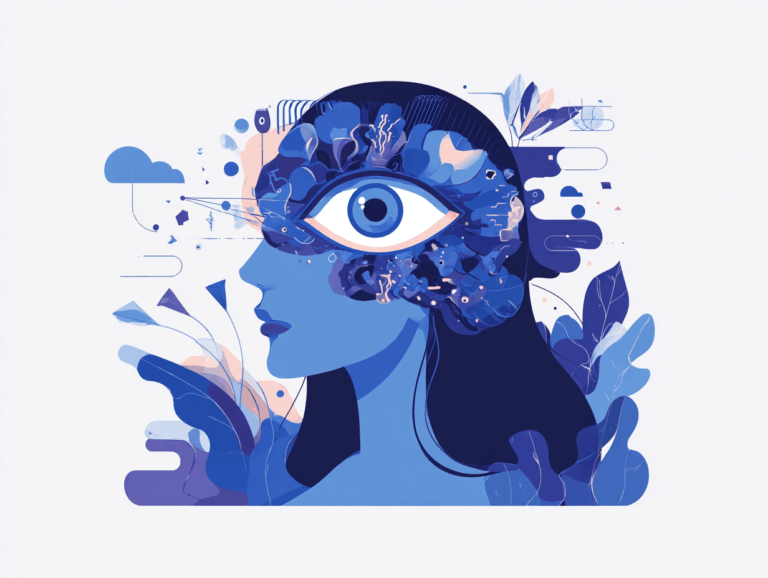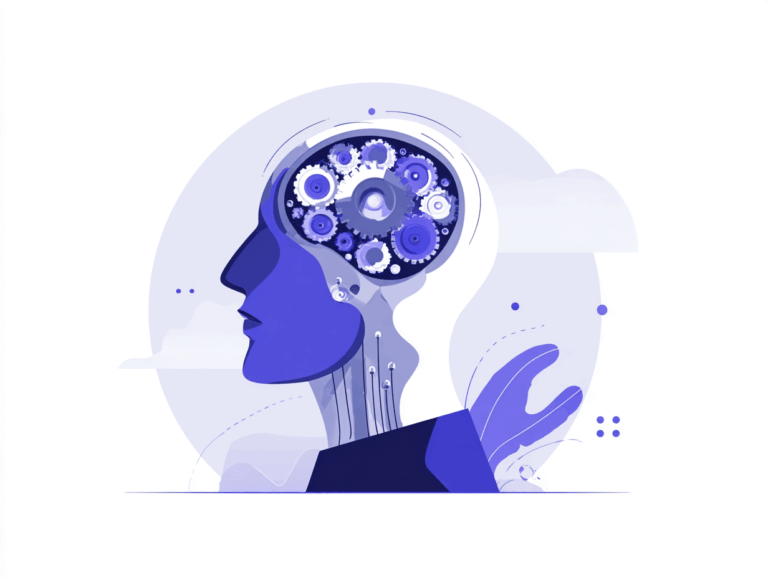AIが日常に溶け込んだ今、多くの経営者が「何から始めればいいのか」と立ち止まっている。ChatGPTを触ったことはあるが、業務効率化にどう活かせばいいのか見えない。そんな迷いを抱えながらも、競合他社の動向は気になる。本レポートでは、実際の現場で試行錯誤を重ねた事例を通じて、AIとの付き合い方を考える。技術の進歩に踊らされるのではなく、自社の課題に寄り添うAI活用を見つけていこう。
- 中小企業経営者・個人事業主
- AIツールの導入を検討しているが、具体的な活用方法が見えずに悩んでいる方
- 業務効率化やコスト削減の手段としてAIに期待している方
- マーケティング・Web担当者
- SEO対策からGEO対策への転換期に対応策を模索している方
- コンテンツ制作の自動化や品質向上を図りたい方
- デジタル変革に取り組む実務者
- 新しいツールを学びながら、実践的なノウハウを蓄積したい方
- 同業他社の事例を参考に、自社の取り組みを改善したい方
伊藤:それでは本日の流れからご紹介して参ります。今回のテーマなんですが、AIの現在地を知るということをテーマに説明させていただきます。最初にAIってどんな感じで今使われてるかっていうところの概論と、それから事例をいくつかご紹介した後に、最近話題になってきているGEOですね、またLLMOなどと言われてますけど、いわゆるAI経由での検索に対してどう対応していくかっていうところをご紹介できればなと思います。では早速まいりましょう。
伊藤:最初にAIの使い方概論ですね。基本的にはAIというのは二つの使い方があります。皆さんよくお使いになってるのは、ChatGPTとかGeminiにWebでアクセス、あるいはアプリでアクセスして文字を打っていく、いわゆる汎用機能の使い方ですね。左側の使い方をされてる方がほとんどだと思います。メリットとしては手軽にできるっていうところと、それから料金がかからないっていう大きな特徴があります。
伊藤:一方、我々が使ってるのは実は右側なんですね。専用機のほうはプログラミングの技術が必要になります。それから料金は従量課金制なんで、使えば使うほどお金がかかりますということなんですね。最大の違いは何かっていうと、学習に使われるか使われないかっていうことと、指示に忠実であるか忠実でないかっていうことになります。
伊藤:汎用機は、ChatGPTにWebでアクセスしていろんな指示を出していきますけども、大体理解してくれたかなと思って使っていくと、大体20回ぐらい同じものをパターン的に使っていくと、段々アレンジをしだすんですね。ではどうするか?そこに対して、実はこの汎用機でもない専用機でもない、間の使い方が実はもう一つあるんですね。三つ目の使い方がMyGPTという形になります。
伊藤:つまり専用機と汎用機の間のものを自作できますよというサービスがあります。一回こっきりでやるものは汎用機のほうで処理していけばいいと思うんですけど、定期的に何か処理をするようなものは、ぜひマイGPTのほうに移行して使っていただくといいかなというふうに考えております。
伊藤:MyGPTがちょっと最近画面が分かりづらくなったんですけども、これがChatGPTですね。最近5になりましたね。いろいろ移行期なのでちょっとトラブルがあったりとかっていうところはニュースでやったりしてますけれども、MyGPTのほうはここですね。左側のGPTをクリックして、この右上のMyGPTっていうところを押すと、自分用にカスタムした専用のAIを作ることができます。
伊藤:例えば、ブログの導入の文章を考えてくださいとか、ブログのセクションごとに構成してくださいねみたいなものを作ったりしています。作成する場合はGPTを作成するを押して、左側にこんなことやりたいなみたいなところを書いていくと、記録されて右側でその処理をしていくようなものになります。
伊藤:実際に使ってみましょう。今日はSNSのリライトをしてみましょう。SNSっていわゆるフロー型になっているので、一回こっきりで使い回しが効かないんですね。ただ、それだともったいないので、AIに文章の内容をリライトですね。テキストをちょっと変える指示を出して、再び再利用していくというような形を、今Y.Kさんと左官のサイトをやってまして、そちらのほうで実際に実装している機能になります。
伊藤:こちらですね。リライトのMyGPTがあらかじめ作成されています。構成でいうとこんな感じですね。こんな方に知ってほしいとか、こんな方に読んでほしいみたいなものを冒頭のほうに入れてねとか、割と細かな指示がこのように書かれています。いわゆるプロンプトというものです。
伊藤:実際に文字を入れてみましょう。これが投稿のリストですね。画像とそれからテキスト、それから投稿された日々がセットされております。なので例えばこれですね。これは外壁を塗っている写真の解説になりますけども、これをコピーしてマイGPTに入れていきます。
伊藤:そうすると、投稿内容を維持しつつ、言い回しをちょっと変えてくれたりとか、あとはハッシュタグとかを追加してくれるわけです。これをこのままXに投稿してもいいし、インスタに投稿してもいいですし、インスタはAPI通じて自動投稿できないので繋がってないんですけど、このスプレッドシートはXに繋がっていて、実は自動投稿をされています。
伊藤:こんな感じのものをいくつか作成していて、スケジュールで言うとこんな感じ。1日3つの配信はBotで行っています。昼の時間帯は新しいものを投稿している状況ですね。これが最初にご案内となります。以上がMyGPTの使い方になります。
伊藤:じゃあ皆さんのお話を聞いてみたいなと思うので、MyGPTを使っているよという方いらっしゃいますか?使っていない、MyGPT知ってたけど使ってないよという方。お二人ですね。分かりました。Y.Kさんいかがですか?知ってるけど使わない理由とか、なかなか設定のハードルが高いとか、あるいは使い道があんまり見つからないとか、いろいろあると思うんですけど、どんな理由でMyGPTは利用してない状況でしょうか?
Y.K:AIが出始めの頃にChatGPTを使い始めたんですが、やっぱりGoogleにGeminiが加わって、ドキュメントとスプレッドシートのところにGeminiのアイコンがあるので、Geminiを使うようになって、あとはGoogleでNotebook LMっていうのがあるので、そちらのほうになって、今9:1の割合でGemini、GoogleのAIを使うようになってきました。
Y.K:GoogleのGeminiでも今、MyGPTみたいな機能があるのかどうか、多分あると思うんですけど、伊藤さんがChatGPTで今MyGPTをやられてる、その理由を、GeminiではまずいのかClaudeではダメなのか、なんでそのChatGPTなのか。使わない理由は、Geminiのほうがやっぱり、Googleで使いやすかったっていうのが一つと、二つは、MyGPTの設定がやはり私のハードルが高かったなっていう、その二つの理由ですね。はい、以上です。
伊藤:分かりました。今ご質問に対しての、なぜ伊藤はChatGPTにこだわって使ってるかっていうところなんですけど、二つあって、一つが、僕自身がSEOで飯食ってるので、SEOの内容をそのままGeminiに作らせてそのままアップするっていうのがマイナスの方向に働くんじゃないかなと思って、今の時点では答えが出ていない、なので、なるべくGeminiには情報を晒さないほうがいいかなっていうふうに、ディフェンス的な側面で使ってないっていうところがあります。
伊藤:もう一つが、ChatGPTは日本人が割と嫌いなハルシネーションがあるんですよね。ハルシネーションとは、拒絶癖みたいなもの。つまり指定されてないことを突然言い出したりっていうのが、他のAIに比べて割合が大きいんですね。なので、もうやめちゃって違うもの、ClaudeだったりGeminiを使ってる方多いと思うんですけども、僕そこは良し悪しだと思っていて、つまりハルシネーションって成長痛だと思ってるんですよ。
伊藤:つまりエラーが起きるから、よりチャレンジングであり、成長が早いっていうふうに思ってるんですね。確実なものっていうのはやはり成長が遅いので、そういう意味でエラーを吐いたとしても、僕は成長が早そうなChatGPTを使い続けてるっていう二つの理由になります。
Y.K:了解です。ありがとうございます。
伊藤:はい。H.Rさん、いかがですか?
H.R:はい。MyGPTを知ってても使っていない理由は、一応の状態としてはChatGPTは今課金して使ってる状態になるんですけど、使ってる内容としては、ブランドの真贋を偽物か本物かっていうのを見分けるときに一個使っています。ロゴの見分けとか画像査定が人間よりも精度が高いときもあるなって思っていて使っているのと、あとはSNSとか周りのとこを大きく二つに分けて使ってるんですけど、設定をしなくても使えてしまっているっていうところが、自分が求めている内のものができちゃってるから、それ以上のことをもし設定したら返してくれるのかもしれないですけど、それをちょっと把握できてないので、まあいいかってやってないっていう感じになります。
伊藤:分かりました。H.Rさんは買取専門のショップを運営されてるので、確かに買取店とかだと、一つのものをたくさん処理するみたいなものって少ないんですよね。1個しかないけども多品種ありますみたいな処理なので、そういう場合はもしかしたらあんまりMyGPTはフィットしない可能性があります。一つのものをたくさん処理する、何回も処理するっていうところに向いているツールなので、ご商売であったり作業の内容であったりっていうところで、適切なAIを選択していけるといいかなというふうに思います。
伊藤:では先ほどの続き。今作業をご覧いただいたように、ファイルを作って管理をして、一定の周期でリライトをしていきます。それをGoogleスクリプトといいますが、GASから自動投稿をXに関しては行っています。Instagramに関しては自動投稿が不可なので、Slack経由で半自動投稿をしています。こんな感じで通知がくるんですね。朝、クイズのストーリーを上げてるので、このクイズをUPしなさいっていう形で、毎日三つストーリーを上げてますね。
伊藤:それからこちら、Xのほうになるんですけども、ブログの紹介の記事を上げてるんですね。そこに対してリンクを貼りに行く作業があるので、それをSlack経由で通知しています。何でSlackでやるかというと、他にも例えばGmailとかも通知ポップアップはあるんですけども、画面がアクティブでないとポップアップされないんですね。一番強力なポップアップはSlackだということが分かったので、Slack経由で作業を管理している状況になります。
伊藤:続いてまいります。左官のほうのサイトで用語集というものを作っています。こんな感じで、左官に関することメイン、あとは住宅建築に関する用語を1日1個作成しているので、その使い方をちょっとご紹介したいなと思います。こんな感じで、今後追加される予定の候補がたくさんあります。例えば「土間打ち」でいきましょうか。ドマウチを作成したいので、Excelにあらかじめ設定を管理して、MyGPTのほうに学習をさせています。用語集解説アシスタントですね。
伊藤:なのでこんな感じで、ドマウチについて解説してというふうに入れると、専門用語を解説してくれます。概要と詳細という形で、テキストを作成してくれます。それから関連用語も取得するように設定されています。用語集の目的なんですけども、内部リンクを生成するためのSEOツールになります。あらかじめMyGPTで定義をしていて、用語自体のリストアップと、用語集の作成。それから画像生成、ちなみに皆さん、画像生成は何のツール使われてますか?いろいろあると思うんですが。Y.Kさん、いかがですか?
Y.K:画像生成は使ったことは数回あるんですが、今は無料の画像のサイトから引っ張ってくることが多いので、画像生成はしてる、してないというところですね。生成というのは、検索して適切な画像をAIが選んでくれるのか、AIが作ってくれるのかっていうと、作ってくれるほうですよね。
伊藤:そうですね。はい。
Y.K:生成まではしてない。数回、本当片手ぐらいしかやったことないですね。
伊藤:分かりました。そうですね、いろんなツールがあるんですけれども、ChatGPTはあんまり画像生成に向いてないので、こんなふうに遅いし、変な字が入ることがあるんですね。キャプション入れないでって言ってるのに。
伊藤:なので、最近割といいなと思ってるのがMidJourneyという、MidJourneyこれをちょっと入れてみましょうか、試しに。
伊藤:速い。2つメリットがあって、そうですね、スピードが速いっていうのと、いくつも作ってくれるんです。複数、4パターンを作ってる。
伊藤:あとは画像が比較的軽いんですね。いつもChatGPTで作った場合は大体2メガぐらいのサイズになっちゃうので、この圧縮するサイトを使って圧縮してから上げるみたいな2工程になっちゃうんですけど、MidJourneyの場合はもう少し軽いので、そのまま使えたりします。
伊藤:ただデメリットがあって、日本語にとっても弱いんですね。なので今「土間打ち」って入れましたけど、多分意味をあんまり理解してなくて、こういう道路みたいなものを作ってしまう。
伊藤:なので英語に翻訳したものを入れると少し精度が上がってくるかなと思いますけど、かなり細かい指定をしないと自分が意図した画像がなかなか出てこないかなっていうところはあります。
伊藤:あとは字の描画っていうのはやっぱりまだまだ、あと手の指とかっていうところも画像生成はまだまだ追いついてないねっていうところ。それがAI画像生成の現状です。
伊藤:はい、ちょっと意図したものが作れませんでしたが、できたと仮定して作業を進めていきましょうか。
伊藤:もう一つの画像生成でいうと、用語集に付随して今やっているのが、こんな感じでクイズを作ってるんですね。なので、相応しい文面を、あらかじめフォーマットに用意しておいて、こんな感じでSNS投稿用の画像を生成してもらってます。
伊藤:出来上がったものは先ほどと同じようにデータベースのほうに入れておいて、自動的に時間がくると投稿されるという仕組みになっています。スケジューリングされてるわけですね。
伊藤:さっき作成依頼したGPTで土間打ちの画像が出来上がったんですかね。そうですね、できたけども、あんまり精度高くないですね。もう少しテキストの量を増やしてあげないと、何を望まれてるのかっていうのは明確にわからないので、この3倍から5倍ぐらいの文字を足してあげたほうがいいかなっていうところがあります。
伊藤:先週ぐらいかな、ちょうどGPTが4から5に移行したんですね。そこでハルシネーションが起きているようで、つまり単純に返したほうがいい問題なのか、それとも熟考したほうがいいのかっていうところの取り違いが起きてるらしいので、この1、2週間はあまりうまく指示が入らないというふうに予測されています。
伊藤:M.Mさん、ちなみに動画のほうはいかがですか?それで動画を作ろうかみたいなお話になったと思います。
M.M:いろいろ探してみたら、他のそれじゃないものでいろいろ今試行錯誤してるんですけど、具体的にはまだ動いてない感じですね。
M.M:動画よりも漫画でできないかなっていうのがあって。
伊藤:そうですね、漫画の生成とかのほうがもしかしたら伝わりやすい。やっぱりAIによってブレが結構出てきたりするので、もしかしたらシンプルな漫画のほうがサービスとしては伝わりやすい可能性がありますね。
M.M:漫画に音声を載せてっていうのを今考えてて。
伊藤:なるほど、わかりました。さて、こんな感じでクイズの投稿が完了しました。出来上がった感じがですね、こんな感じで今は毎日の8時台ですね、夜にこんな感じでクイズだけの投稿をしていってるところですね。
伊藤:まだちょっと前のバージョンが残っていて、今新しいものを書き換えている最中ではありますけども、Xで段々リアクションがついてきたので、もう少し頑張ってやっていこうかなと。
Y.K:これが自動投稿されてるやつですね。
伊藤:そうですね、以上が事例1になります。
伊藤:続いて、事例2、「音声文字起こし」。左官の職人さんたち、社長さんたちにインタビューを取ってるんですね。この左官工事ってどんなものですか、みたいなものがあってですね、それをZoomとかで録音しといてですね、それをテキスト化するものになります。
伊藤:文字起こし専用のツールもいっぱい出てるんですけど、実は結構精度が低かったりするんで、僕の場合はOpenAIのAPIを叩いて直接AIに処理をさせています。
伊藤:これだけ聞くと何言ってるかちょっと分かんないなっていうところなんで、実際にちょっと作業をしているところをお見せしたいと思います。
伊藤:所定のフォルダに音声のデータが入っています。Rubyという言語を使って、まず圧縮をかけていきます。
伊藤:なぜ圧縮をかけるんでしょうか?Y.Kさん分かりますか?
Y.K:圧縮をかける目的ですか?10分とか15分の短いものでも圧縮をかけるんでしょうか?それとも長いものを圧縮かけるんでしょうか?
Y.K:長ければやっぱり重たくなるので圧縮かけたほうがいいなと思うんですけど、ちょっとその辺がわからない。
伊藤:はい、重さという点でいうと、25メガ以上のものは処理できないんですね、弾かれてしまうので圧縮をかけるっていうのが一つと、もう一つが冒頭に申し上げた専用機の場合は従量課金なので、重たいとお金を余計取られちゃうねっていうことになるんですね。なので経費削減のために圧縮をかけているわけです。
伊藤:こんな感じでRubyで処理をして、次はOpenAIにアクセスして文字起こしの作業をしてもらっている最中になります。
伊藤:AIを活用していくのであればRubyもしくはPythonという言語を使うと便利だと言われてますね。
伊藤:今、コンテンツ記事というのは簡単に生成AIでできてしまいます。なので何を言ってるかよりも誰が言ってるかっていうところがより重要になってくるんですね。
伊藤:例えば、左官のサイトで言うと、全然関係ない部外者がAI使って書いたものがプロフェッショナルが喋ってるものより上に行っちゃうとやっぱりまずいんですよね、ウェブ業界としても。
伊藤:なので、今後は誰が言ってるかっていうところが重要になるし、こういったインタビュー形式の記事が主体になってくるだろうなというところを予測しているわけです。
伊藤:はい、ではこのようにですね、ベタ打ちですが文字起こしが完了しております。今度はですね、Claudeですね。三大AIの一つと言われていますが、GeminiやGPTと比べるとちょっと地味かなというところがあります。
伊藤:あらかじめプロンプトを用意してあるので、プロンプトと一緒に先ほどのデータをくっつけて処理をしてもらいます。
Y.K:Claudeで処理するんですね。
伊藤:なぜClaudeなのかっていうところなんですけれども、長文の日本語を書かせると今のところ一番うまいのがClaudeと言われています。
伊藤:ただしデメリットがあります。処理できる文字数の上限があるっていうのがデメリットの一つで、もう一つがスレッド間のデータを受け渡せないっていうデメリットがあるんですね。なので別のスレッドで処理した内容をこっちでも反映してっていう指示ができないと言われています。
伊藤:このあたり細かい機能の特徴というのがそれぞれありますので、そのあたりも今後ちょっとまとめて、どんな作業に向いてるかっていうところの一覧表なんかは皆さんに共有できるといいかなというふうに思っています。
Y.K:インタビューでブログ記事を作るときに、10分ぐらいのインタビューであれば文字数であれば5000文字はいきますかね?
伊藤:そうですね、安定してClaudeが処理できるアウトプットがだいたい5000文字ぐらいなんですね。なのでこれ見てみましょうか。
伊藤:基本的にはこの先ほどOpenAIのプログラミングの中で、大きすぎる場合は5000文字単位に区切って処理するようにしてるんですね。なのでファイルが分かれて出力される状態になります。
伊藤:このインタビューでは、文字数のカウントで言うと3600ぐらいですね。
Y.K:すみません、これ何分のインタビューでしたっけ?
伊藤:10分ぐらいですかね。
伊藤:そうですね、13分くらい。
伊藤:圧縮の処理とかをしてるのはFFmpegというソフトになります。Claudeからの文章を最後MyGPTで、要約とか、あとがきとかを追加してアップするという作業をしています。時間の関係で、事例3は一回飛ばして、もし最後ご要望があればというところで。
伊藤:SEOとGEOの違いって皆さん興味あります?
O.H:そうですね、SEOはすごく意識はしてるんですけど、まだGEOの知識があまりなくて、っていう感じですね。
Y.K:O.Hさんの自己紹介をちょっと短く。
O.H:結婚相談所やってますO.Hと言います。婚活パーティーとかで場所を貸していただくことでY.Kさんとのところでやらせていただいて、今回もお誘いいただきました。よろしくお願いします。
伊藤:宜しくお願いいたします、さて、僕もGEOのほうはそろそろやらなきゃなっていうふうに考えていて、GA4見ていると、実際サイトへのアクセスもちょろちょろAI経由のものが増えてきているんですね。なのでこのタイミングでちょっと早めに皆さんに情報共有だけさせていただければなというふうに思います。
伊藤:まず前提として、SEOいわゆる検索で上位っていうのはどうしたらいいのっていうところと、AIでどうやって紹介してもらうかっていうところは、そもそもアルゴリズムの法則が違うんですね。
伊藤:SEOのほうは従来通りキーワードとどれぐらい一致してるかっていうところとか、あとは内部リンクがたくさん生成されてるとか、あるいは外部からリンクが貼られてるみたいなところも評価に加わり、それから文脈的なところも重要だったりしますし、もっというとテキストの量ですね。できれば5000文字とか8000文字あったほうが上のほうに行きやすいよねっていう法則があります。
伊藤:一方、GEOのほうはE-E-A-Tがより重視されるということですね。E-E-A-T、専門性、信頼性、権威性、それから経験というふうに言われています。つまり全然ジャンルが違うところに言及しても、それは信頼性がないよねっていうことなので、専門の範囲内で記事を生成できるかっていうところが非常に重要と言われています。
伊藤:もう一つがですね、先ほどSEOのほうは文章の量が大事ですよっていうことなんですけども、GEOのほうは逆でですね、問いが簡潔であるか、いわゆるQ&Aがさっぱりしてるかっていうところが評価軸になるよと言われています。
伊藤:では、実施すべきことは何でしょうか?3つあります。まず先ほど言ったようにサイトの信頼性を高めましょうねっていうことですね。つまりいい加減な記事とか嘘が混じってはいけませんよ、それから専門性がやはり大事だということです。
伊藤:2番目ですね、記事トピックに関連した簡単な質問と回答を追加しておきましょうということですね。つまり、現状GEOだけやってもあんまり流入は少ないので、今あるしっかりボリュームのあるブログに対して簡単な質問と回答を用意していくと、よりピックアップされやすいでしょうということが見えてきています。
伊藤:3番目ですね、ユーザーの意図に沿うコンテンツを用意するっていうことですね。つまり何らかの問いかけをAIにしているわけなので、そこに対して素直にシンプルに回答していくっていうところを意識して記事を用意していきましょうということになってきます。
伊藤:では現状はですね、どれぐらいのサイト来訪の割合なのか、これちょっといろいろ諸説あって幅があります。1パーセントぐらいだって言っている人、あるいは、サイト全体の流入量の0.5パーセントしかないと言われています。
伊藤:しかしですね、2027年にはAIからやってくる人、サイト訪問する人と検索でやってくる人の比率がほぼ同じになっているという予測されているんですね。なので今日の時点ではGEOってこんなもんかっていうところでいいとは思うんですけれども、来年ですね、年明けぐらいから少しずつGEO対策を始めていくといいのかなというふうに、このデータを見る限りは予測されるわけです。
伊藤:ただですね、ちょっと前で言うとですね、実はこのAI経由のサイト来訪が5割になるっていうのは、半年前、1年前だとですね、2040年だって言われてたんですね。つまり相当早いスピードでAIが進化してるっていうことが分かるかと思います。
伊藤:現状は来訪低いから意味がないよねっていうことにも捉えられますけれども、実はGEOの目的はサイト来訪ではないと言われています。つまり結論で言うと、ブランディングのためにGEO対策をしなさいというふうに言われ始めているわけです。
伊藤:例えば結婚相談所みたいなもので、いろいろAIで調べてるときに、ベストアンサーみたいな形で紹介されていたらですね、そこの紹介所って信頼性高いよねって人間は思うわけですね。なのでサイト来訪、滞在時間やユニークユーザーを増やすという戦略ではなくて、あくまでもブランディング目的でさらっとやっとくといいよねっていうことになってくるかなと思います。
伊藤:SEOとGEOの話がバーッと来ましたけれども、何かご意見ご質問などがあればお願いします。Y.Kさんいかがですか?
Y.K:そうですね、まだAIが0.5%で2027年、たった2年ですよね。2年でそんなに変わるのかなって、やっぱ音声入力が増えるのかなっていうふうに直感的に思ったのと、ブランディングであればローカルビジネスなのか、広範囲のビジネスなのかで、ちょっとブランディングの作り方も変わってくるので、両方ともどういうバランスで使うのかっていうのが難しいなっていう印象です。私からは以上です。
伊藤:ありがとうございます。H.Rさん、今までのところでGEOだけじゃなくて何かご質問などあればお願いします。
H.R:感想としては、SEOで勉強して対策頑張ろうって思ってるところに新しいのが増えると大変だなっていう、いっぱいいっぱいになるんだろうなっていう印象でした。
H.R:AIについては使い分けっていうところを全然していなくて、絶大な信頼を置いてChatGPT一択でやってしまっているので、そこをそれぞれの特性に合わせて使い分けた方がいいのか、一個でもいいんじゃないかっていうのか、どのぐらいの使い分けをする、人にもよるんでしょうけど、メリットがあるのかなっていうのを聞いてみたいなというふうに思いました。以上です。
伊藤:いわゆる三大AIというところが汎用的に使っていけるんですね。ChatGPT、Gemini、それからClaudeになりますけども、実際にH.Rさんと同じように思っている方が非常に多いんですね。
伊藤:つまりさっき画像生成のスピードを見ましたよね。Midjourneyっていうのは画像生成に特化した専用機なんですよね。一方でChatGPTで作らせると時間もかかるし、画像も重たいし精度もあんまり良くないよねっていうところなんで、実は専用機をめちゃめちゃ使い込んだ方がクオリティがグッと上がるんです。
伊藤:ただ、この作業はこのAI、次の作業はこのAI、この作業はこれみたいなことになってくると、現場レベルで今起きているのがAIアレルギー。つまり精度高くなくてもいいから、なんか一個で処理したいねっていうのがやっぱり人の心らしくてですね。
伊藤:なのでメインで使うのが例えばChatGPTにしますという決めたんであれば、その他で一つ二つぐらいは専用機を使って、あとはもうなるべく一箇所で処理しようねっていうのも戦略の一つかなというふうに思います。
伊藤:新しいツールとか便利な使い方が出ればですね、またこのオンラインサロンでご紹介できればなと思いますので、ご興味あるものあるいは使えそうだなってものをちょっといじってもらうっていう感覚で、恐らく良いのかな。本当にフィットするものがどれかみたいな、総あたりでやっていくのはあんまり上手く無いかなというふうに思います。
伊藤:M.Mさんいかがでしょうか?何かご意見、ご感想あれば。
M.M:二つあって、一つは今例えば言語、日本語の精度の高さっていうところで、一度英語にしてそれを翻訳するっていうのがあったんですけど、例えばこの三大ではなく日本人が作成したような、そういったものって出てきてるんですかね?日本人にフォーカスしたような国内の。
伊藤:そうですね、出てきてるっていう話は聞いてて、すいませんちょっと僕もまだいじれてないので、また具体的なものがあればご紹介できればなと思うんですけども、LLMといういわゆる大規模言語モデル、M.Mさん非常にいいご指摘だったと思います。やっぱりその言語がどれぐらいAIの中で使われてるかっていうところが、アウトプットの精度に関わってくるんですね。
伊藤:なので今後起きてくるのは、英語、中国語、スペイン語、フランス語はものすごく発展するけれども、日本語とドイツ語は多分落ちていくと思うんですよね。つまり1億人ぐらいしか使わない、使用頻度が全然違うんで、使用頻度が高い言語を使った方がいいよねって話どうしてもなってくるかなと。
伊藤:なので今言われた日本語でやりやすいものを今は探した方がいいですけど、やっぱり他の言語でAIを使っていくっていう方が、将来的にはそっちが主流になってくるんじゃないかなと考えています。
M.M:わかりました、ありがとうございます。もう一ついいですか?音声変換など何かいいものあるんですかね?
伊藤:音声を、例えば男の人の声を女の人の声にするみたいなことですか?
M.M:いや、テキストを音声にすることとして。
伊藤:テキストの読み上げですか?
M.M:そうですね、例えばその感情表現の部分でも、ちょっとため息を付くとか、細かいところまで拾い上げるような。
伊藤:そうですね、音声系で言うとWhisperとか、あとはAmazonが精度が高いって言われてるんですが、それ多分ビジネス文書的な処理だと思うんですよね。僕もまだ使ったことないんですけど、音声が「ひろゆき」になるみたいな、最近SNSでありますよね。あのあたりはかなり精度高くなってきてるかなとは思うんですが、あれなんかちょっと高いんですよね確か。
M.M:課金とかするか。
伊藤:課金制ですね、そうですね。なので音声はどうなんですかね。そこなんか皆さん面白がってやってるし、トップレベルの人は多分それで食べていけると思うんですけど、例えばゲームのグラフィックとか、エフェクトみたいな感じで、1回目はわーってなるんです、でも2回目とかそれ以降のものは、価値が出てこないと思う。なかなかその人間という感覚が慣れてきちゃうので。
伊藤:一番を取れるような人は食べていけるし、使い込んでいく価値があると思うんですけども、いわゆるデジタルなので、模倣品が出てくるんですよね。なのでそこよりはなんか、リアルで撮ったものをうまく加工していく方が価値が高いような気がします。
伊藤:音声の読み上げに関しては、NotebookLMとか、自動生成のものをうまく使いながらっていうところ、なので先ほどコンテンツのところでも申し上げたとおり、インサートカットでうまく使っていくぐらいであれば、お金も掛からないし良いねっていうところなんですけど、それをフル動画で作ったりとかっていうところはなかなか難しいし、そういうものが大量生産されたときに、価値を失うことになるので。
伊藤:僕今考えているのは、デジタルが発展した結果、より戻しでリアルの価値がもっと上がるよねっていうところの世界がおそらく出てきてくるかなと思います。なので簡単に使えて、シーンとシーンの区切り目で、インサートカットで入れられるようなものがもしあれば、またご案内できればなというふうに思います。
伊藤:ありがとうございます。もしよければO.Hさんも何か、AIのことのご質問があったら。
O.H:すみません、ちょっとまた話が戻ってしまうんですが、さっきのSEOとGEOの話で、2点ちょっとお聞きしたいことがあって、今ホームページ上のブログで、だいたい5000文字で書くようにしているんですね。その中でなるべく拾ってもらえるようにということで、Googleで拾ってもらえるようにということで、Geminiを今使っている。
O.H:あえて意識してGoogleはGeminiを出しているので、そちらのほうがいいかなと思って、前はChatGPTを使っていたんですが、今はGeminiを使うようにしているんですけど、そういうのってどちらのほうがいいとか、たまに変えたほうがいいとか、何かそういうことっていうのはありますか?
伊藤:僕もこないだ気になったので、Geminiに聞いてみたんですね。SEOの評価を、AIが作ったものと人間が作ったものと区別する可能性があるかということについて質問をしてみました。
伊藤:テキストに関しては、よっぽど長いものでない限りは、AIが生成したものと判定をすることがほぼできないというふうに回答してるんですね。
伊藤:画像と動画に関しては、これ実装されてるかどうかちょっとまだ不明なんですけど、ヨーロッパの法律では、もう明示しなさいということになっているんですね。おそらくそれが世界基準になっていると思うんですけど、まだ時間がかかるということ。
伊藤:でも、一つ言われてるのが、人の目には見えないウォーターマーク、つまり画像に何らかの見えない処理がされていて、それがAIで作られたものだということで特定できてしまうらしい。なので画像動画に関しては、ちょっとまだペナルティーがあるか、マイナスの要因となるかというところは可能性があるんですけども、テキストに関しては、それほど影響がないと言われている。
伊藤:重要なのは、そのテキストを読んだときに、ユーザーがどんなアクションを取るかというところで評価をしているので、もちろん文字そのものを見ると言われてるんですけども、それよりはユーザーがきちんと興味を持って見てるかっていうところを評価しているので、僕は今一旦避けてますけど、GeminiでもChatGPTでも、AIで作った文章を差別しないという回答が今出ています。
O.H:ありがとうございます。もう一ついいですか?これからSEOからGEOの方に流れていくという話だったんですけど、それを意識して今から対策として、普段ブログを上げたりだったりとかするときにやっていけること、質問と回答とか専門性とかっていう話があったんですけど、そういうのをブログだったりとか、そういうInstagramとか、そういうSNSだったりとかで出していくところで意識していけばいいのか、何か今から具体的にできる対策っていうのはありますか?
伊藤:そうですね、まだGEO自体が確定したものではないんですけど、現段階で見えてる施策としては2つあるかなと思っています。重要なことはGEOとSEOを分けて考えないということなんですね。つまり現状GEOに特化したページを作るっていうのは、コスト的に合わないんですよね。なのでSEOのページにGEOの工夫を追加するっていうことをやっていただければなと思います。
伊藤:やることは2つで、1つが先ほど申し上げた通り。。。
==================
「詳細は会員登録すると閲覧できます。」
==================
伊藤:もう1つが、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に。。。
==================
「詳細は会員登録すると閲覧できます。」
==================
伊藤:つまりAIの検索、AIで調べるっていうのの目的は何かっていうと、本来的にはいろんなページを調べてみて、どうもこれが正しいよねっていうのをその中で集約して結果を得ていたのが、AIに聞くと5つぐらいのサイトの情報がギュッとまとまって手に入るねっていうこと
伊藤:つまりいかに人間の知りたいことをショートカットしてあげるかっていうところがAI利用の目的なので、そこに従ったアクションを取っていくと、SEOも維持したままGEOも得られるかなという風に私は予測しています
O.H:ありがとうございます。
伊藤:他に何かAI関係でご意見ご質問などございますでしょうか?Y.Kさん大丈夫ですか?
Y.K:今は大丈夫です。どうもありがとうございます。わかりやすかったですね
Y.K:僕は今はジェミニだけですけど、ちょっとチャットGPTとClaudeにちょっと挑戦してみます
伊藤:ジェミニ、今度僕に教えてください
伊藤:前半講義の部分は終わりになります。この後少し休憩を挟んで各社のお悩み相談のコーナーになりますが、今日はどなたがやられますか
伊藤:H.Rさんいかがですか
H.R:今日やろうと思ってたんですけど、時間的にまた今度にしても大丈夫ですか
H.R:一応ホワイトペーパーだけ目次とちょっと数ページは作ってみたんですけど、まだ全部できてないのでまた次回の時までに作っておきます
伊藤:わかりました。Y.Kさんいきますか
伊藤:そうですね。少しFAQとかの変更をしたのと、あとはトップページとバナーのほうの変更の案が出てきたので。
Y.K:私のほうで伊藤さんお願いします
伊藤:ではゲストのお二人の方もお時間を許す限りいただいて一旦区切りますので
M.M:また参加させてください。どうもありがとうございました。
伊藤:みなさんありがとうございました
[有料会員限定]見逃し配信を見る。
今回の記事の配信データを有料会員様限定で公開中。繰り返し視聴する事でWEBマーケティングの力が身に付きます。
会員限定コンテンツ
ご覧になるには
メンバー登録が必要です。
オンラインサロン
「メタ思考のグリア」とは?